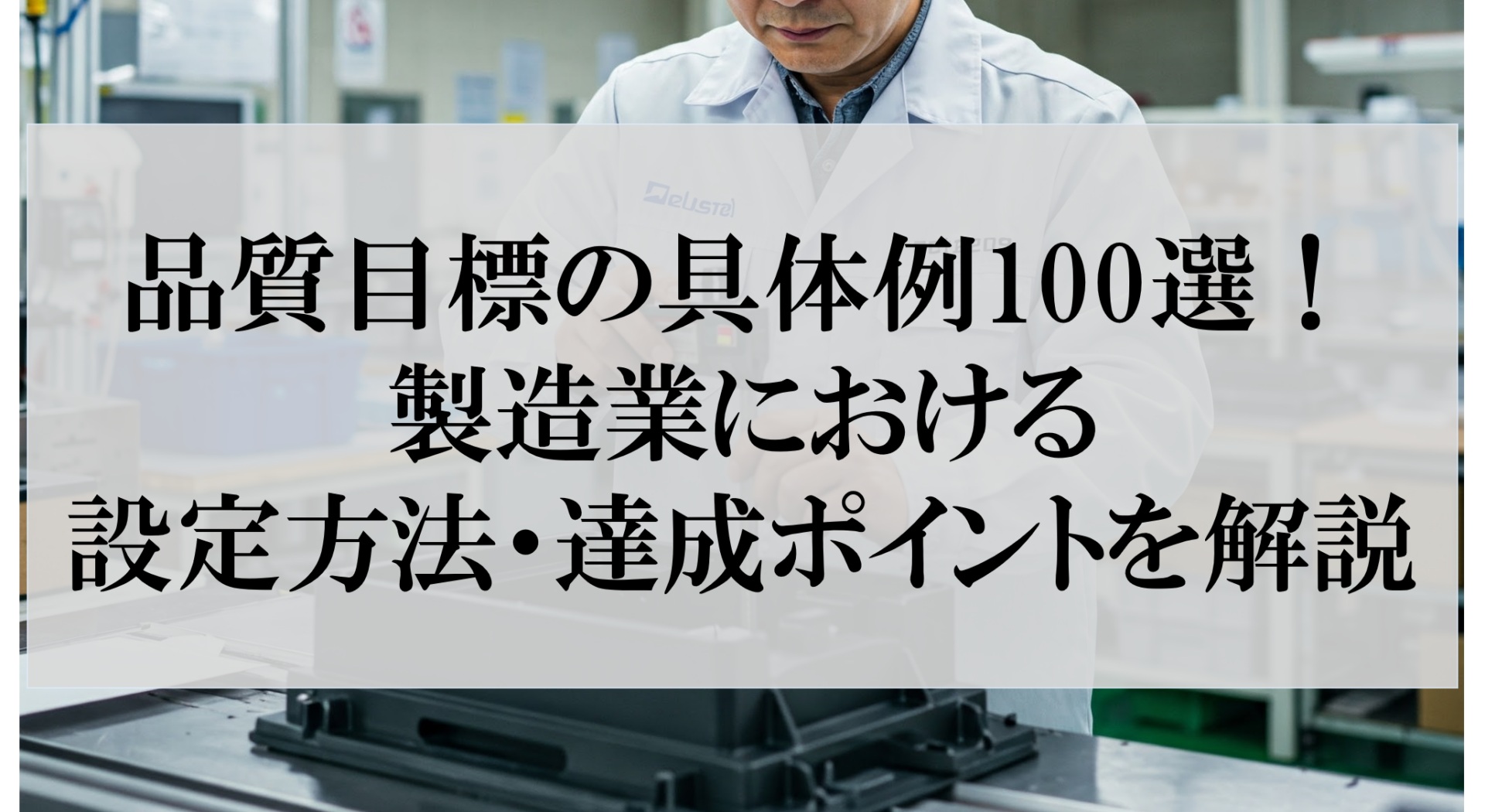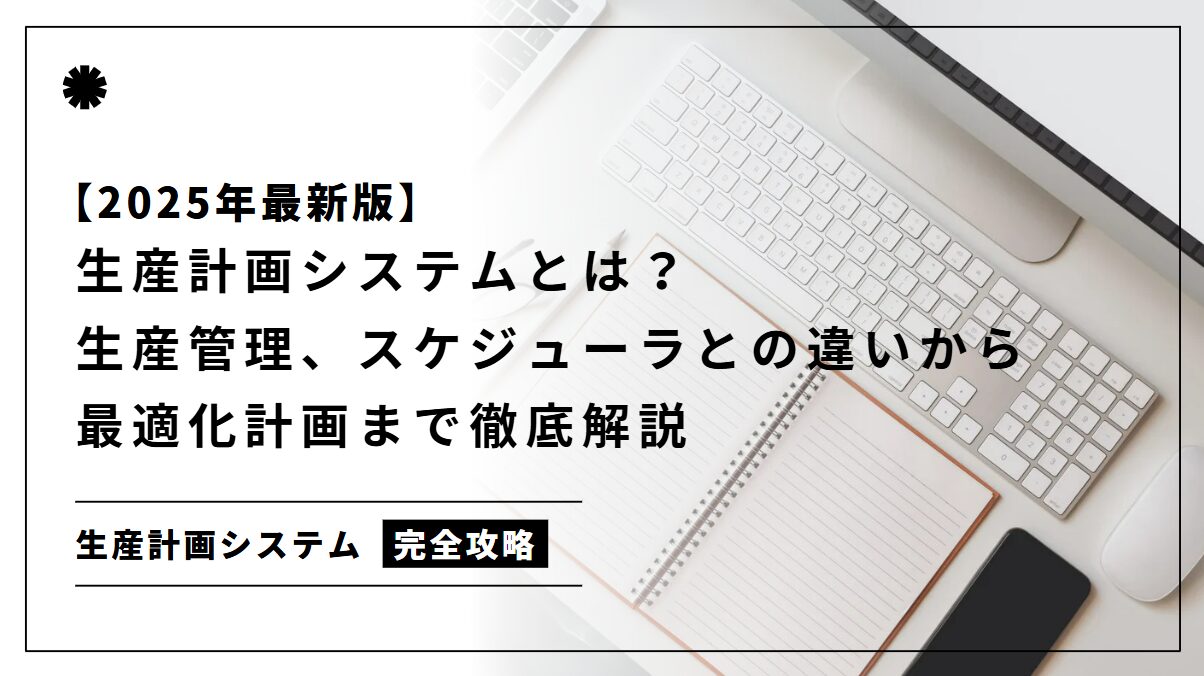【事例公開】地方中小企業でも年収アップ!DXで間接業務9割削減の秘訣!
2025.07.02
いつもお世話になっております。
今回は8月22日(金)14:30~17:30に開催予定の
船井総研スマートファクトリー経営部会でご講演いただく
三共電機株式会社様のDX成功事例をご紹介します。
従業員数58名。愛知県稲沢市に本社を構え、制御盤の設計・製造などを手掛ける同社では、DXに関する取り組みを通じて、単なる業務効率化に留まらず、社員の年収アップ、雇用創出、残業時間削減、売上高約1.5倍、間接業務9割削減といった多岐にわたる経営指標の改善に成功されました。特に、DXの実現を通じて、一般社員の平均年収は450万円あまり、管理職は820万円にまでアップしたとのことです。
地方の中小企業でありながら、どのようにして社員の年収アップ、生産性向上、
そして「昭和の工場」からの大改革を実現したのか、その全貌を3つのパートに分けてお伝えします。
1. 日常業務のDXで生産性の飛躍的な向上を実現!
三共電機株式会社様は、かつて「ありとあらゆる作業が手書き、Excel・メモ帳管理」というアナログな業務環境を抱えていました。特に、制御盤製作に不可欠な約2,000種類もの在庫部品の手配業務は、必要な時に都度手書きで依頼し、型式や数量の書き間違い、二重手配、過剰手配といった問題が頻発していました。また、在庫管理の責任者が「仕事ができる人」になりがちで、そのためにその人の生産性が落ちるという課題もありました。
年に2回行われる棚卸業務も大きな負担でした。手書き・手計算で行われ、集計に1週間以上を要し、誤記入や誤集計、集計漏れが常態化し、決算期の生産性にも悪影響を及ぼしていました。
これらの課題に対し、同社はDXを推進。在庫棚に貼られたQRコードを読み取るだけで部品を手配・計上できるアプリを導入しました。手配担当者への「確認要求自動メール」送信機能も構築され、発注ミスや重複を激減。棚卸業務もアプリ化され、わずか半日で完了するようになりました。写真を見ながら作業できるため、商品知識がないパート社員でも正確に対応可能となり、全社員で棚卸作業に参加できる体制が整いました。結果として、在庫数・金額の正確性が向上し、過剰在庫の削減にも成功しました。
2. 社会課題解決のDXで社員の働きがい向上!
同社は、社員の働きがい向上にもDXを積極的に活用しました。以前は、労働者の権利である有給休暇の取得が難しく、紙の申請書を社長(前社長)に直接提出する形式であったため、社員が「申請しづらい」と感じる雰囲気がありました。また、有給申請後の予定表や勤怠管理システムへの反映は手入力で行われており、従業員が増えるほど労務管理者の手間が増大し、従業員満足度やモチベーションの低下につながっていました。
そこで、同社は有給申請のアプリ化を実施。社員はアプリ上で希望日と理由を設定して申請でき、Teams上で承認プロセスが完結し、その状態が可視化されます。さらに、Power Automate®と連携することで、Outlookの共有予定表に自動で反映される仕組みを構築しました。
このDXにより、社員は上司の顔色をうかがうことなく有給申請できるようになり、有給取得率が抜本的に向上しました。申請・承認作業がクラウド化されたことで、いつでもどこでも承認・却下が可能になり、労務管理の手間も大幅に削減されました。結果、従業員満足度が向上し、QOL(生活の質)の向上やモチベーションアップという好循環を生み出しました。この仕組みは休日出勤申請にも横展開されています。
3. 経営のDXで「データドリブン経営」を実現!
経営の根幹を支える経営指標の作成においても、同社は大きな課題を抱えていました。以前は、売上データや仕入データなどの経営指標のグラフ作成に過剰な時間を費やし、「グラフづくり」が「目的化」してしまうという問題がありました。原価が変更されるたびにCSV出力し、Excelグラフを更新するといった煩雑な手作業が、迅速な経営判断を妨げていたのです。
同社はこの課題を解決するため、基幹システムからのデータ取得にRPAを導入して自動化し、さらにクラウドデータベースをBIレポートに直接連携させることで、リアルタイムな経営データの可視化を実現しました。
この取り組みにより、同社は「データドリブン経営」を実践できるようになりました。BIレポートについて、一度ひな形を作成すれば、決まった時刻に最新データが自動配信される仕組みを確立。これにより、売上アップ・粗利アップ・利益アップ・コストダウンといった具体的な成果に向けて“即行動”できる体制が整ったのです。
4.さいごに
三共電機株式会社様の事例は、DXが単なる業務効率化に留まらず、社員の年収アップ、雇用創出、残業時間削減、売上高約1.5倍、間接業務9割削減といった多岐にわたる経営指標を改善し、企業の持続的な成長を可能にすることを示しています。特に、DXの実現を通じて、一般社員の平均年収は450万円あまり、管理職は820万円にまでアップしたとのことです。
本事例の詳細について、8月22日(金)14:30~17:30に開催予定の
船井総研スマートファクトリー経営部会(@船井総研グループ東京本社)にて、
三共電機株式会社 代表取締役 三橋 進様よりご講演をいただきます。
本事例の詳細に関するご講演に加えて、当日限定で三橋様による「経営指標のリアルタイム見える化」の実演もを予定しています。
スマートファクトリー経営部会のお試し参加にご興味のある方は、
「今すぐ」以下のURLからお申し込みください。
https://lpsec.funaisoken.co.jp/study/smart-factory/047708/
《無料お試しご参加条件》
・本研究会に過去ご参加された経験のない企業様
・経営者様、経営幹部の皆様
※ご参加は1回限りです。当日のプログラム全体終了直後に、本研究会へご入会するか否かのご判断をいただきます。事業の経営判断ができる方がご参加ください。
8月22日(金)14:30~17:30
ものづくり経営研究会スマートファクトリー経営部会
お試し参加ご案内
https://lpsec.funaisoken.co.jp/study/smart-factory/047708/ いつもお世話になっております。
今回は8月22日(金)14:30~17:30に開催予定の
船井総研スマートファクトリー経営部会でご講演いただく
三共電機株式会社様のDX成功事例をご紹介します。
従業員数58名。愛知県稲沢市に本社を構え、制御盤の設計・製造などを手掛ける同社では、DXに関する取り組みを通じて、単なる業務効率化に留まらず、社員の年収アップ、雇用創出、残業時間削減、売上高約1.5倍、間接業務9割削減といった多岐にわたる経営指標の改善に成功されました。特に、DXの実現を通じて、一般社員の平均年収は450万円あまり、管理職は820万円にまでアップしたとのことです。
地方の中小企業でありながら、どのようにして社員の年収アップ、生産性向上、
そして「昭和の工場」からの大改革を実現したのか、その全貌を3つのパートに分けてお伝えします。
1. 日常業務のDXで生産性の飛躍的な向上を実現!
三共電機株式会社様は、かつて「ありとあらゆる作業が手書き、Excel・メモ帳管理」というアナログな業務環境を抱えていました。特に、制御盤製作に不可欠な約2,000種類もの在庫部品の手配業務は、必要な時に都度手書きで依頼し、型式や数量の書き間違い、二重手配、過剰手配といった問題が頻発していました。また、在庫管理の責任者が「仕事ができる人」になりがちで、そのためにその人の生産性が落ちるという課題もありました。
年に2回行われる棚卸業務も大きな負担でした。手書き・手計算で行われ、集計に1週間以上を要し、誤記入や誤集計、集計漏れが常態化し、決算期の生産性にも悪影響を及ぼしていました。
これらの課題に対し、同社はDXを推進。在庫棚に貼られたQRコードを読み取るだけで部品を手配・計上できるアプリを導入しました。手配担当者への「確認要求自動メール」送信機能も構築され、発注ミスや重複を激減。棚卸業務もアプリ化され、わずか半日で完了するようになりました。写真を見ながら作業できるため、商品知識がないパート社員でも正確に対応可能となり、全社員で棚卸作業に参加できる体制が整いました。結果として、在庫数・金額の正確性が向上し、過剰在庫の削減にも成功しました。
2. 社会課題解決のDXで社員の働きがい向上!
同社は、社員の働きがい向上にもDXを積極的に活用しました。以前は、労働者の権利である有給休暇の取得が難しく、紙の申請書を社長(前社長)に直接提出する形式であったため、社員が「申請しづらい」と感じる雰囲気がありました。また、有給申請後の予定表や勤怠管理システムへの反映は手入力で行われており、従業員が増えるほど労務管理者の手間が増大し、従業員満足度やモチベーションの低下につながっていました。
そこで、同社は有給申請のアプリ化を実施。社員はアプリ上で希望日と理由を設定して申請でき、Teams上で承認プロセスが完結し、その状態が可視化されます。さらに、Power Automate®と連携することで、Outlookの共有予定表に自動で反映される仕組みを構築しました。
このDXにより、社員は上司の顔色をうかがうことなく有給申請できるようになり、有給取得率が抜本的に向上しました。申請・承認作業がクラウド化されたことで、いつでもどこでも承認・却下が可能になり、労務管理の手間も大幅に削減されました。結果、従業員満足度が向上し、QOL(生活の質)の向上やモチベーションアップという好循環を生み出しました。この仕組みは休日出勤申請にも横展開されています。
3. 経営のDXで「データドリブン経営」を実現!
経営の根幹を支える経営指標の作成においても、同社は大きな課題を抱えていました。以前は、売上データや仕入データなどの経営指標のグラフ作成に過剰な時間を費やし、「グラフづくり」が「目的化」してしまうという問題がありました。原価が変更されるたびにCSV出力し、Excelグラフを更新するといった煩雑な手作業が、迅速な経営判断を妨げていたのです。
同社はこの課題を解決するため、基幹システムからのデータ取得にRPAを導入して自動化し、さらにクラウドデータベースをBIレポートに直接連携させることで、リアルタイムな経営データの可視化を実現しました。
この取り組みにより、同社は「データドリブン経営」を実践できるようになりました。BIレポートについて、一度ひな形を作成すれば、決まった時刻に最新データが自動配信される仕組みを確立。これにより、売上アップ・粗利アップ・利益アップ・コストダウンといった具体的な成果に向けて“即行動”できる体制が整ったのです。
4.さいごに
三共電機株式会社様の事例は、DXが単なる業務効率化に留まらず、社員の年収アップ、雇用創出、残業時間削減、売上高約1.5倍、間接業務9割削減といった多岐にわたる経営指標を改善し、企業の持続的な成長を可能にすることを示しています。特に、DXの実現を通じて、一般社員の平均年収は450万円あまり、管理職は820万円にまでアップしたとのことです。
本事例の詳細について、8月22日(金)14:30~17:30に開催予定の
船井総研スマートファクトリー経営部会(@船井総研グループ東京本社)にて、
三共電機株式会社 代表取締役 三橋 進様よりご講演をいただきます。
本事例の詳細に関するご講演に加えて、当日限定で三橋様による「経営指標のリアルタイム見える化」の実演もを予定しています。
スマートファクトリー経営部会のお試し参加にご興味のある方は、
「今すぐ」以下のURLからお申し込みください。
https://lpsec.funaisoken.co.jp/study/smart-factory/047708/
《無料お試しご参加条件》
・本研究会に過去ご参加された経験のない企業様
・経営者様、経営幹部の皆様
※ご参加は1回限りです。当日のプログラム全体終了直後に、本研究会へご入会するか否かのご判断をいただきます。事業の経営判断ができる方がご参加ください。
8月22日(金)14:30~17:30
ものづくり経営研究会スマートファクトリー経営部会
お試し参加ご案内
https://lpsec.funaisoken.co.jp/study/smart-factory/047708/