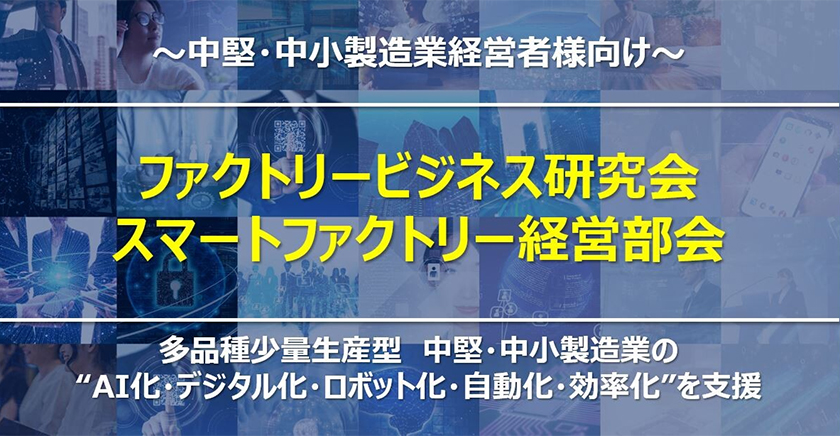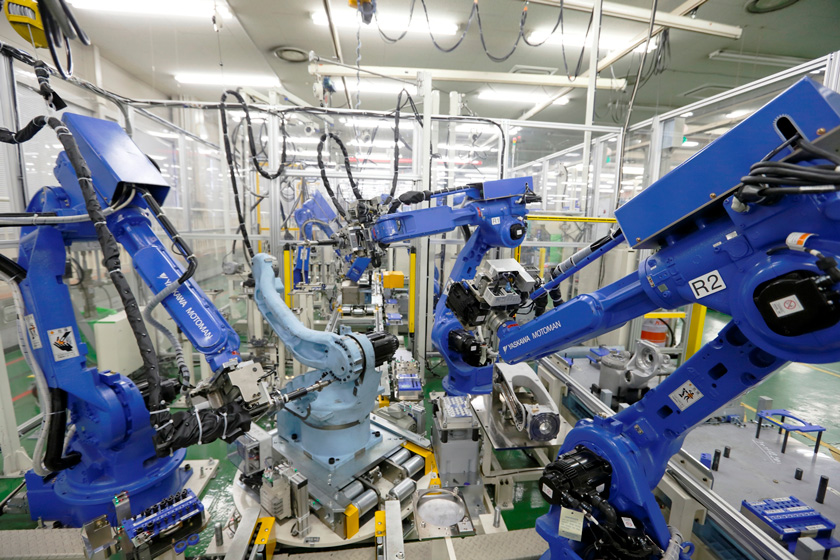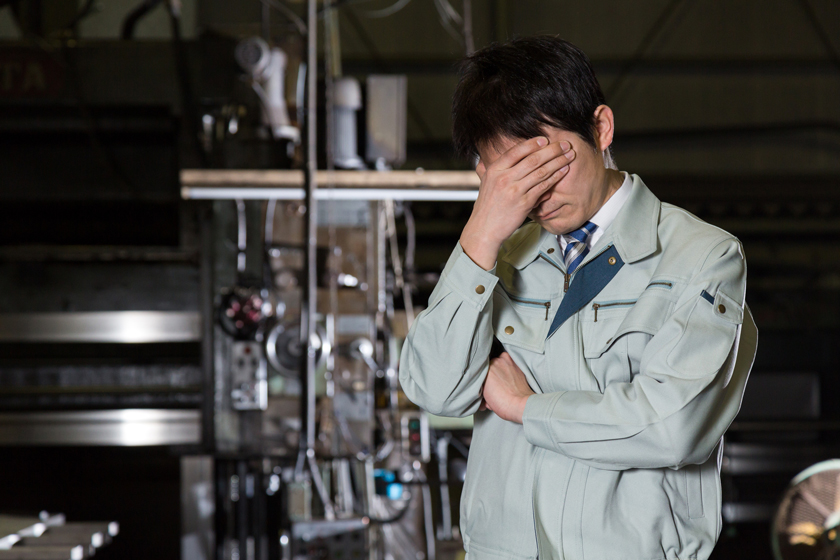
「DXは取り組まない!」と言ってみたら
2022.03.28
Ⅰ.日本におけるDX推進の現状
「なぜDXをしなければならないのか」と考える社長や幹部・従業員は多いかと思います。
「周りが騒いでいるからウチも始めないと」と思いながら取り組み始めている企業も多いかもしれません。
様々なきっかけがあるかと思いますが、その中で「本気で取り組まなければ潰れてしまう」と思って取り組んでいる企業は、どれほどあるでしょうか。
そもそもDXとは、パソコンの導入や情報システムを導入するとった従来のIT化とは異なり、経営判断やビジネスモデルなど様々な判断にIT(デジタルデータ)を活かすという意味でよく定義されます。
毎日のようにTVや新聞、雑誌などでDXが取り上げられている中で、「興味がない」とそっぽを向ける企業はいないでしょう。どの企業もDXを会社方針のどこかに位置づけ、年始に発表したことと思います。
しかし、DXについて理解している方は意外に多くありません。
アイブリッジ社の20代~60代の会社員を対象に実施した「DXに関する調査」によると、DXを理解している人は全体の2割程度にとどまっていることが分かりました。
また、経済産業省が示す「DX推進指標」では、DXの成熟度レベルと特性を表1のように定義し調査を行ったところ、図1に示すようにレベル3を下回る企業が全体の95%程度を占め、DXが進んでいないことが改めて浮き彫りになりました。
表1. DX推進指標の定性指標における成熟度レベルと特性
図1. DX推進指標の分析結果(出典:経済産業省「DXレポート2 中間とりまとめ」)
上記の他、DXを進めるにあたり、理解しないまま、もしくは取り組む意味に疑問を持ちながら実施している企業も多くあるのだと思います。
このコラムでは「なぜDXに取り組むか」の説明より、「DXは取り組まない!」と宣言した場合にどういうことが起こりえるか考えていきましょう。
ブームだからといってわけもわからず中途半端に取り組むのが、コスト面でも従業員のモチベーション面でも一番悪影響を及ぼします。
DXに取り組まないなら「DXしない宣言」=今のままのアナログ的に行くんだ!と宣言した方がよほど従業員は腹を決めて切り替えができます。
良くないのは、自分の会社がそういう取組で積極的なのかそうでないのかよくわからない状況で、月日が流れていくことです。
DXに取り組むのか取り組まないのか曖昧にせず、まず会社方針を明確にするのが大切なことだと考えています。
Ⅱ.あなたが「DXしない宣言」をした場合に想定できること
では、あなたが「DXしない宣言」をした場合、どのようなことが起きるでしょうか。考えていきましょう。
①2025年の崖問題に直面する
2018年に経済産業省は日本が抱えるIT課題を指摘し、その中でもレガシーシステムから脱却することが急務であることを提言しました。
それを「2025年の崖問題」と言います。
古いシステムはベンダーのサポートが終了すると不都合に対応できなくなるだけでなく、新たにシステムを構築しようとした場合に既存データを取り出せないなどのリスクが発生する可能性があります。
DX化する中で、これまで蓄積してきたデータを活かすことができれば、その段階でそのデータは会社の大切な資産となりますが、DX化しなければその資産を自ら失うことになります。
②市場に取り残される
「日本の製造業の品質は高い」と評価され、他国に比べて価格帯が少々高くても需要のある時代もかつて存在しましたが、今は一概にはそうとは言えない時代になりました。
それは、GAFAに代表されるアメリカ企業や中国企業は当然ながら、アジアの中でも企業の中には徹底的なDXを進めて(データを活用して)高品質・低価格を実現している企業も多く存在するからです。
日本のお家芸だった職人芸の技術もどんどんロボットに置き換わっていきます。
また、大量で正確なデータからスピーディーに確度の高い経営判断を行う企業が増えていきます。
これまでの5年で皆さんの仕事の仕方はあまり変わらなかったかもしれません。
ただ、これからの5年で以前と変わらなければ、間違いなく市場に取り残されるでしょう。
③新人・若手が定着しない
Paperlogic社の調査によると、2021年2月25日の段階で2021年の新卒社員の43.1%が、企業のDX推進具合を企業選考の基準としていたことが分かりました。
DX推進具合を企業選考の基準とした理由としては「DXに限らず、今後必要になってくる事を積極的に取り入れる会社かどうか見極めるポイントになると考えたから」「社会情勢に応じて、柔軟な対応ができる企業に勤めたいと思っていたから」などが挙げられていました。
新型コロナウイルスによって、より社会の変化に敏感になっている学生や若手社員にとって、DXへの姿勢は「この先やっていけるか」を判断する大変重要な要素になるということが分かります。
いかがでしょうか。上記の内容を覆せる大事な信念があれば、「DXしない宣言」はアリだと思います。しかし、株主や従業員、協力会社を説得する材料がないのであれば、きちんとした対応をとる必要があります。
いずれにせよ、まずはDXに取り組む/取り組まないの方針を明確にすることは社長・幹部の重要な仕事になるでしょう。
“積算・見積もりAIシステム”事例解説レポート
▼事例レポート無料ダウンロードお申し込みはこちら▼
https://www.funaisoken.co.jp/dl-contents/smart-factory_smart-factory_00702
AIを活用し「積算・見積もりのドンブリ勘定」からの脱却を実現!
AI活用を通じて“ベテラン社員の働き方改革”を推進!
積算・見積もり業務の“標準化・脱属人化・技術継承”実践事例とは?
「こうなりたい!」と思っている経営者様におすすめ
見積もり業務の属人化を解消したい
見積もり業務の標準化を図りたい
見積もり業務にAIを活用したい
積算・見積もり業務の“標準化・脱属人化・技術継承”をしたい
AI活用を通じてベテラン社員の働き方改革を進めたい
■オンラインセミナー開催のお知らせ
製造業の為のAI活用戦略!経営者セミナー
製造業の取組事例に学ぶ!製造業経営者が知っておくべきAI活⽤戦略!
▼セミナーお申し込みはこちら▼
https://smart-factory.funaisoken.co.jp/event/
このような方にオススメ
AIに関心はあるが、自社の経営・営業にAIを具体的にどう活用できるかを知りたい”製造業経営者”
営業部門がまだまだ属人的で、個々の営業スタッフの経験や勘に依存していると感じている”製造業経営者”
生産技術・生産計画・生産管理を特定の熟練者に依存していてブラックボックス化していると感じている"製造業経営者"
製造現場では匠の技が駆使されていて、AI化・IoT化・ロボット化・デジタル化が進んでいないと感じてる”製造業経営者”
営業管理・生産管理・原価管理等の基幹システムに課題があり、非効率的で改善が必要と感じている”製造業経営者”の方
講座内容
第一講座 AI取組事例講座編 「全国各地で見られる製造業でのAI取組事例」
営業部門でAIを活用し、属人化した営業スキルの標準化に取り組んでいる製造業の事例
見積・設計業務にAIを活用して、見積業務効率化・見積精度UP、設計業務効率化に取り組んでいる製造業の事例
成功する原価管理システムの業務改善手順と具体的導入プロセス
生産計画・生産管理にAIを活用して、生産計画作成の自動化・最適化&生産管理の効率化に取り組んでいる製造業の事例
製造現場でのAI化・IoT化・ロボット化・デジタル化により職人依存体制からの脱却を目指している製造業の事例
経営管理全般でDX化に邁進している製造業の事例
第二講座 AI活用戦略講座編 「製造業経営者が取り組むべきAI活用戦略」
製造業の経営にAIを活用する方法
”経営者目線”で知っておくべき製造業で実践できる具体的なAI活用とは?
漠然とした理論・概論ではなく、現場で即使えて実践的なAI導入手順
全てオンラインでの開催となります
PCがあればどこでも受講可能です
2022/04/12 (火)13:00~15:00
2022/04/14 (木)13:00~15:00
2022/04/20 (水)13:00~15:00
2022/04/21 (木)13:00~15:00
お申し込みはこちらから⇒
このセミナーは終了しました。最新のセミナーはこちらから。
https://smart-factory.funaisoken.co.jp/event/
Ⅰ.日本におけるDX推進の現状
「なぜDXをしなければならないのか」と考える社長や幹部・従業員は多いかと思います。
「周りが騒いでいるからウチも始めないと」と思いながら取り組み始めている企業も多いかもしれません。
様々なきっかけがあるかと思いますが、その中で「本気で取り組まなければ潰れてしまう」と思って取り組んでいる企業は、どれほどあるでしょうか。
そもそもDXとは、パソコンの導入や情報システムを導入するとった従来のIT化とは異なり、経営判断やビジネスモデルなど様々な判断にIT(デジタルデータ)を活かすという意味でよく定義されます。
毎日のようにTVや新聞、雑誌などでDXが取り上げられている中で、「興味がない」とそっぽを向ける企業はいないでしょう。どの企業もDXを会社方針のどこかに位置づけ、年始に発表したことと思います。
しかし、DXについて理解している方は意外に多くありません。
アイブリッジ社の20代~60代の会社員を対象に実施した「DXに関する調査」によると、DXを理解している人は全体の2割程度にとどまっていることが分かりました。
また、経済産業省が示す「DX推進指標」では、DXの成熟度レベルと特性を表1のように定義し調査を行ったところ、図1に示すようにレベル3を下回る企業が全体の95%程度を占め、DXが進んでいないことが改めて浮き彫りになりました。
表1. DX推進指標の定性指標における成熟度レベルと特性
図1. DX推進指標の分析結果(出典:経済産業省「DXレポート2 中間とりまとめ」)
上記の他、DXを進めるにあたり、理解しないまま、もしくは取り組む意味に疑問を持ちながら実施している企業も多くあるのだと思います。
このコラムでは「なぜDXに取り組むか」の説明より、「DXは取り組まない!」と宣言した場合にどういうことが起こりえるか考えていきましょう。
ブームだからといってわけもわからず中途半端に取り組むのが、コスト面でも従業員のモチベーション面でも一番悪影響を及ぼします。
DXに取り組まないなら「DXしない宣言」=今のままのアナログ的に行くんだ!と宣言した方がよほど従業員は腹を決めて切り替えができます。
良くないのは、自分の会社がそういう取組で積極的なのかそうでないのかよくわからない状況で、月日が流れていくことです。
DXに取り組むのか取り組まないのか曖昧にせず、まず会社方針を明確にするのが大切なことだと考えています。
Ⅱ.あなたが「DXしない宣言」をした場合に想定できること
では、あなたが「DXしない宣言」をした場合、どのようなことが起きるでしょうか。考えていきましょう。
①2025年の崖問題に直面する
2018年に経済産業省は日本が抱えるIT課題を指摘し、その中でもレガシーシステムから脱却することが急務であることを提言しました。
それを「2025年の崖問題」と言います。
古いシステムはベンダーのサポートが終了すると不都合に対応できなくなるだけでなく、新たにシステムを構築しようとした場合に既存データを取り出せないなどのリスクが発生する可能性があります。
DX化する中で、これまで蓄積してきたデータを活かすことができれば、その段階でそのデータは会社の大切な資産となりますが、DX化しなければその資産を自ら失うことになります。
②市場に取り残される
「日本の製造業の品質は高い」と評価され、他国に比べて価格帯が少々高くても需要のある時代もかつて存在しましたが、今は一概にはそうとは言えない時代になりました。
それは、GAFAに代表されるアメリカ企業や中国企業は当然ながら、アジアの中でも企業の中には徹底的なDXを進めて(データを活用して)高品質・低価格を実現している企業も多く存在するからです。
日本のお家芸だった職人芸の技術もどんどんロボットに置き換わっていきます。
また、大量で正確なデータからスピーディーに確度の高い経営判断を行う企業が増えていきます。
これまでの5年で皆さんの仕事の仕方はあまり変わらなかったかもしれません。
ただ、これからの5年で以前と変わらなければ、間違いなく市場に取り残されるでしょう。
③新人・若手が定着しない
Paperlogic社の調査によると、2021年2月25日の段階で2021年の新卒社員の43.1%が、企業のDX推進具合を企業選考の基準としていたことが分かりました。
DX推進具合を企業選考の基準とした理由としては「DXに限らず、今後必要になってくる事を積極的に取り入れる会社かどうか見極めるポイントになると考えたから」「社会情勢に応じて、柔軟な対応ができる企業に勤めたいと思っていたから」などが挙げられていました。
新型コロナウイルスによって、より社会の変化に敏感になっている学生や若手社員にとって、DXへの姿勢は「この先やっていけるか」を判断する大変重要な要素になるということが分かります。
いかがでしょうか。上記の内容を覆せる大事な信念があれば、「DXしない宣言」はアリだと思います。しかし、株主や従業員、協力会社を説得する材料がないのであれば、きちんとした対応をとる必要があります。
いずれにせよ、まずはDXに取り組む/取り組まないの方針を明確にすることは社長・幹部の重要な仕事になるでしょう。
“積算・見積もりAIシステム”事例解説レポート
▼事例レポート無料ダウンロードお申し込みはこちら▼
https://www.funaisoken.co.jp/dl-contents/smart-factory_smart-factory_00702
AIを活用し「積算・見積もりのドンブリ勘定」からの脱却を実現!
AI活用を通じて“ベテラン社員の働き方改革”を推進!
積算・見積もり業務の“標準化・脱属人化・技術継承”実践事例とは?
「こうなりたい!」と思っている経営者様におすすめ
見積もり業務の属人化を解消したい
見積もり業務の標準化を図りたい
見積もり業務にAIを活用したい
積算・見積もり業務の“標準化・脱属人化・技術継承”をしたい
AI活用を通じてベテラン社員の働き方改革を進めたい
■オンラインセミナー開催のお知らせ
製造業の為のAI活用戦略!経営者セミナー
製造業の取組事例に学ぶ!製造業経営者が知っておくべきAI活⽤戦略!
▼セミナーお申し込みはこちら▼
https://smart-factory.funaisoken.co.jp/event/
このような方にオススメ
AIに関心はあるが、自社の経営・営業にAIを具体的にどう活用できるかを知りたい”製造業経営者”
営業部門がまだまだ属人的で、個々の営業スタッフの経験や勘に依存していると感じている”製造業経営者”
生産技術・生産計画・生産管理を特定の熟練者に依存していてブラックボックス化していると感じている"製造業経営者"
製造現場では匠の技が駆使されていて、AI化・IoT化・ロボット化・デジタル化が進んでいないと感じてる”製造業経営者”
営業管理・生産管理・原価管理等の基幹システムに課題があり、非効率的で改善が必要と感じている”製造業経営者”の方
講座内容
第一講座 AI取組事例講座編 「全国各地で見られる製造業でのAI取組事例」
営業部門でAIを活用し、属人化した営業スキルの標準化に取り組んでいる製造業の事例
見積・設計業務にAIを活用して、見積業務効率化・見積精度UP、設計業務効率化に取り組んでいる製造業の事例
成功する原価管理システムの業務改善手順と具体的導入プロセス
生産計画・生産管理にAIを活用して、生産計画作成の自動化・最適化&生産管理の効率化に取り組んでいる製造業の事例
製造現場でのAI化・IoT化・ロボット化・デジタル化により職人依存体制からの脱却を目指している製造業の事例
経営管理全般でDX化に邁進している製造業の事例
第二講座 AI活用戦略講座編 「製造業経営者が取り組むべきAI活用戦略」
製造業の経営にAIを活用する方法
”経営者目線”で知っておくべき製造業で実践できる具体的なAI活用とは?
漠然とした理論・概論ではなく、現場で即使えて実践的なAI導入手順
全てオンラインでの開催となります
PCがあればどこでも受講可能です
2022/04/12 (火)13:00~15:00
2022/04/14 (木)13:00~15:00
2022/04/20 (水)13:00~15:00
2022/04/21 (木)13:00~15:00
お申し込みはこちらから⇒
このセミナーは終了しました。最新のセミナーはこちらから。
https://smart-factory.funaisoken.co.jp/event/