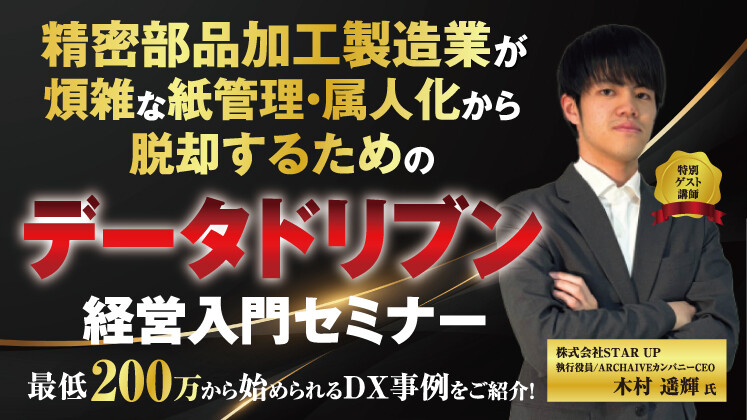記事公開日:2025.10.30
最終更新日:2025.10.30
月次決算ではもう遅い!“リアルタイム原価管理”なくして、中小製造業に未来はない

月末、経理担当者から上がってくる試算表。社長室で、あなたはその一枚の紙をじっと見つめます。
「今月も売上は目標達成。利益もまあまあ出ているな。しかし、どうも手元のキャッシュが増えている実感がない…」
「相変わらず、材料費と外注費が高いな。一体、どの製品がコストを圧迫しているんだ?」
多くの経営者が、この月次の損益計算書(P/L)を頼りに経営判断を下しています。
しかし、その数字が示すのは、あくまで「過去一ヶ月間の結果」でしかありません。
例えるなら、バックミラーだけを見て車の運転をしているようなもの。
目の前で起きている変化や、これから進むべき道筋を判断するには、情報が古すぎるのです。
特に、多品種少量生産が主流となり、顧客からの短納期要求やコストダウン要請が厳しさを増す現代において、この「月次決算頼み」の経営は、致命的な弱点を抱えています。
なぜ「どんぶり勘定」から抜け出せないのか?
中小製造業の多くが、製品ごと、案件ごとの正確な原価を把握できていない「どんぶり勘定」に陥りがちです。その原因は、従来の原価計算の仕組みそのものにあります。
- 煩雑すぎる実際原価計算
製品ごとの正確な原価を把握するためには、直接材料費、直接労務費、直接経費、そして製造間接費を、製品ごとに集計し、配賦するという非常に煩雑な計算が必要です。
現場作業員は、どの製品の加工に何時間かかったのかを日報に手書きで記入し、経理担当者がそれを月末にまとめてExcelに打ち込み、集計する…。
このプロセスには膨大な手間と時間がかかり、人為的なミスも発生しやすくなります。
結果として、「正確な原価計算は手間がかかりすぎる」と、標準原価や過去の実績に基づく大まかな原価計算で妥協してしまうのです。 - 見えない「労務費」と「間接費」
材料費は請求書が来るので比較的把握しやすいですが、厄介なのが労務費と間接費です。
特に、一人の作業員が複数の製品を掛け持ちで加工したり、段取り替えに時間がかかったりした場合、その作業時間をどの製品の原価として計上すべきか、正確に把握するのは困難です。 - 経営判断のタイムラグ
月末にようやく計算された原価を見て、「この製品、実は赤字だったのか…」と気づいたとしても、すでに手遅れです。
その製品は一ヶ月間、作れば作るほど会社の体力を奪っていたことになります。
価格交渉や生産方法の見直しといった対策を打つタイミングを、一ヶ月も逸してしまっているのです。
このスピード感の欠如が、じわじわと会社の収益性を蝕んでいきます。
「この製品の加工時間は、だいたい2時間くらいだろう」
という現場の感覚値で計上されているケースも少なくありません。
これでは、本当に儲かっている製品と、実は手間ばかりかかって利益を圧迫している「不採算製品」を見分けることはできません。
リアルタイム原価管理がもたらす「強い工場」への変革
こうした課題を根本から解決するのが、「リアルタイム原価管理」という考え方です。
これは、IoTセンサーやバーコードリーダー、タブレットといったツールを活用し、現場で発生する作業時間や設備稼働状況、材料使用量といったデータを、その場でデジタルデータとして収集・集計する仕組みです。
これにより、何が変わるのでしょうか?
愛知県にある従業員100名の自動車部品加工会社は、まさにこのリアルタイム原価管理を実践し、大きな成果を上げました。
彼らは、生産管理システムとIoTを活用し、現場の作業時間や設備稼働データをリアルタイムで収集。
その結果、製品ごと・工程ごとの実際原価が、いつでも即座に可視化できるようになったのです。
この変革がもたらしたものは、計り知れません。
- 不採算案件の即時特定
「この案件、今のペースだと労務費がかかりすぎて赤字になるぞ」といったことが、リアルタイムで分かります。すぐさま現場と連携し、作業方法の改善や応援人員の投入といった手を打つことができます。 - 見積もり精度の劇的な向上
過去の類似製品の「実際にかかった原価データ」を基に見積もりを作成できるため、勘や経験に頼らない、根拠のある価格設定が可能になります。これにより、安請け合いによる赤字受注を防ぎ、適正な利益を確保できます。 - 現場のコスト意識の向上
自分たちの作業時間が、製品の原価にどう反映されるのかが「見える化」されることで、現場の従業員一人ひとりにコスト意識が芽生えます。「どうすればもっと効率的に作業できるか」「段取り替えの時間を短縮できないか」といった、自主的な改善活動が生まれる土壌が育つのです。
「IoTなんて、大掛かりな設備投資が必要なのだろう?」
そんな心配は無用です。
今の時代、中小企業でも導入しやすい安価なセンサーや、スマートフォン・タブレットを活用したシンプルな仕組みから始めることが可能です。
重要なのは、完璧なシステムを最初から目指すのではなく、まずは「一番知りたい情報」からデータを取り始めることです。
来る「紙管理脱却のための中小製造業データドリブン経営入門セミナー」では、このような中小製造業が実践できるリアルタイム原価管理の具体的な手法や、導入しやすいツールについて、多くの事例を交えながら解説されます。
特に第三講座では、船井総合研究所の熊谷 俊作 氏が、損益計算書から見た原価管理の重要性や、稼働率向上・原価低減といった新たな指標獲得に向けたステップを体系的に語ります。
月次の試算表を眺めて溜息をつく経営は、もう終わりにしませんか。
リアルタイムのデータに基づき、次々と的確な手を打っていく「データドリブン経営」へ。
その第一歩は、自社の原価を正確に、そしてリアルタイムに知ることから始まります。
脱!紙・Excel日報・紙図面!中小製造業が「高収益工場」に変わるデータ活用術
紙管理脱却のための中小製造業データドリブン経営入門セミナー
「忙しいのに儲からない」その原因は、見えないコストにあるのかもしれません。本セミナーでは、IoTや安価なツールを活用したリアルタイム原価管理の手法を徹底解説。どんぶり勘定から脱却し、データに基づいた的確な経営判断で「高収益工場」へと生まれ変わるためのヒントがここにあります。
開催日時(オンライン):
2025/11/28 (金) 13:00~15:00
2025/12/02 (火) 13:00~15:00
2025/12/03 (水) 13:00~15:00
紙管理脱却のための中小製造業データドリブン経営入門セミナー
https://www.funaisoken.co.jp/seminar/134272
紙管理脱却のための中小製造業データドリブン経営入門セミナー
「忙しいのに儲からない」その原因は、見えないコストにあるのかもしれません。本セミナーでは、IoTや安価なツールを活用したリアルタイム原価管理の手法を徹底解説。どんぶり勘定から脱却し、データに基づいた的確な経営判断で「高収益工場」へと生まれ変わるためのヒントがここにあります。
開催日時(オンライン):
2025/11/28 (金) 13:00~15:00
2025/12/02 (火) 13:00~15:00
2025/12/03 (水) 13:00~15:00