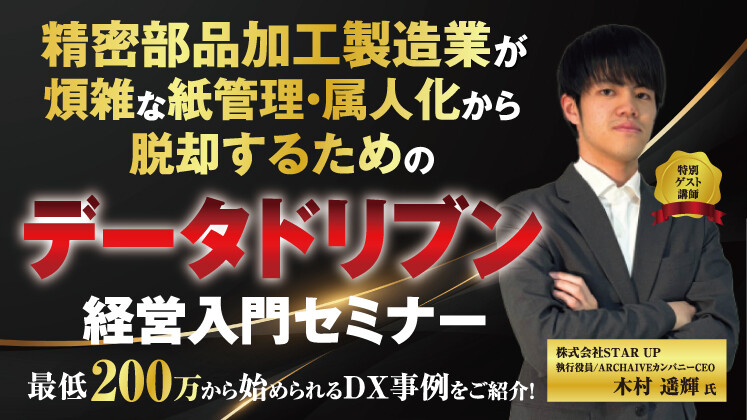記事公開日:2025.11.04
最終更新日:2025.11.04
生産性20%向上の裏側!愛知の多品種少量生産工場が、勘と経験の“呪縛”を断ち切れたワケ

「うちは多品種少量生産だから、生産管理なんて無理だよ」
「毎日作るものが違うのに、どうやって効率化すればいいんだ?」
「結局、現場のベテランの経験と勘で回すしかないんだよ」
多品種少量生産を手掛ける多くの中小製造業の現場で、このような諦めの声が聞こえてきます。
製品の種類は数百、数千に及び、ロット数は1個から。生産計画は目まぐるしく変わり、段取り替えに追われる毎日…。
このような複雑な状況下では、標準化や効率化は困難であり、個々の職人のスキルと臨機応変な対応力に頼らざるを得ない、と考えるのも無理はありません。
しかし、もし、その「常識」を覆し、データ分析によって生産性を20%も向上させた企業があるとしたら、あなたはその秘密を知りたいと思いませんか?
愛知県にある、ある多品種少量生産の企業。
彼らもまた、かつては皆様と同じ悩みを抱えていました。
紙の図面や手書きの日報が飛び交う工場内では、情報共有は常に遅れがち。
どの工程がボトルネックになっているのか、なぜ特定の製品で不良が多発するのか、その原因は誰も正確に把握できていませんでした。
「おそらく、あの機械の調子が悪いんだろう」
「きっと、あの作業のやり方に問題があるはずだ」
――すべてが、曖昧な推測の域を出なかったのです。
この「勘と経験」に頼った現場改善は、一見、熟練の技のように見えますが、実は大きな問題をはらんでいます。
それは、「本当に解決すべき問題」を見誤ってしまうリスクです。
なぜ、あなたの現場改善は空振りに終わるのか?
- 「声の大きい人」の意見に流される
現場で一番経験豊富なベテランや、一番声の大きいリーダーの「あそこが問題だ」という一言で、改善の方向性が決まってしまう。
しかし、その指摘が本当に的を射ているとは限りません。
実は、もっと根本的な原因が別の場所にあるにもかかわらず、目先の現象に囚われてしまうのです。 - 問題の「真因」にたどり着けない
例えば、「不良品の発生」という問題に対して、
「作業員のスキル不足だ」と結論づけて、研修を強化したとします。
しかし、もし真因が「特定のロットの材料の質が悪かった」
あるいは「その日の工場の温湿度が影響していた」としたら、いくら研修をしても不良はなくなりません。
データという客観的な事実に基づかなければ、こうした真因を見つけ出すことは極めて困難です。 - 改善効果を客観的に測定できない
「改善活動を行った結果、どれくらい生産性が上がったのか?」
と問われて、
「なんとなく、早くなった気がします」
としか答えられない。
これでは、その改善が本当に正しかったのかを評価できず、次の打ち手にも繋がりません。
改善活動が、やりっぱなしの自己満足で終わってしまうのです。
データが暴いた「工場の真実」
この愛知県の企業は、こうした「勘と経験の呪縛」から脱却するために、大きな決断をしました。
タブレットと生産管理システムを導入し、製造実績や設備稼働状況をデジタルで記録し始めたのです。
最初は、現場からの抵抗もあったかもしれません。
「ただでさえ忙しいのに、そんな面倒な入力作業はできない」と。
しかし、経営陣の強いリーダーシップのもと、データ収集を徹底しました。
そして、集まったデータを分析した結果、彼らは驚くべき「工場の真実」を目の当たりにします。
- 思わぬ「ネック工程」の発見
これまで誰も問題視していなかった、ある前処理工程が、実は工場全体の生産スピードを律速する最大のボトルネックであることが判明しました。 - 不良発生の意外な傾向
特定の曜日や時間帯、あるいは特定の機械と作業員の組み合わせで、不良率が突出して高くなるというパターンが可視化されました。 - 「チョコ停」の実態
設備が数秒から数分間停止する「チョコ停」が、彼らの想定をはるかに超える頻度で発生しており、合計すると膨大なロスタイムになっていることが明らかになったのです。
これらはすべて、データという客観的な証拠がなければ、決して気づくことのできなかった事実でした。
この「気づき」こそが、変革の原動力となります。
彼らはデータに基づき、ネック工程に改善リソースを集中投下し、不良発生のパターンから再発防止策を講じ、チョコ停の原因を一つひとつ潰していきました。
その結果、生産性は20%向上し、リードタイムも大幅に短縮されたのです。
勘や経験に頼っていた現場改善が、データに基づいた客観的で、誰が見ても納得できる科学的なアプローチへと進化した瞬間でした。
あなたの工場にも、まだ誰も気づいていない「改善のヒント」が、日々の生産活動の中に必ず眠っています。それを掘り起こす道具が「データ」なのです。
「多品種少量生産だからこそ、データ活用は必須である」
この逆説的な真実に気づき、具体的な一歩を踏み出したいとお考えの経営者様は、ぜひ「紙管理脱却のための中小製造業データドリブン経営入門セミナー」にご参加ください。
第一講座では、まさにこの愛知県の事例が、より詳細に解説されます。
彼らがどのようにしてペーパーレス化を進め、データを分析し、現場を巻き込みながら改善を実践していったのか。
その具体的なプロセスを知ることは、あなたの会社が「高収益工場」へと生まれ変わるための、最高の道しるべとなるでしょう。
脱!紙・Excel日報・紙図面!中小製造業が「高収益工場」に変わるデータ活用術
紙管理脱却のための中小製造業データドリブン経営入門セミナー
「うちは多品種少量だから…」という諦めを、確信へと変える2時間です。データ分析による現場改善で生産性20%向上を実現した工場の生々しい事例から、あなたの会社でも明日から実践できる改善のヒントを学びませんか?勘と経験だけに頼る経営から、データに基づいた科学的アプローチへ。その変革の第一歩を、このセミナーから踏み出してください。
開催日時(オンライン):
2025/11/28 (金) 13:00~15:00
2025/12/02 (火) 13:00~15:00
2025/12/03 (水) 13:00~15:00