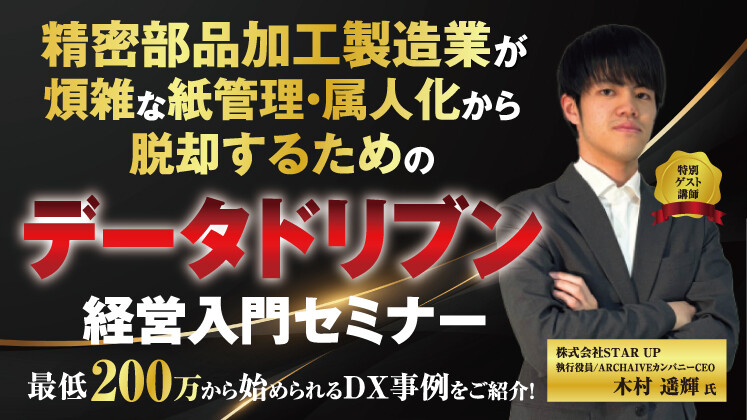記事公開日:2025.11.26
最終更新日:2025.11.26
「失敗から学ぶ製造業DX・3つの落とし穴」フライデーコラム:シオタ

「DXの重要性は理解している。高額なAIやIoTの予算も付けた。しかし、現場では一向に使われる気配がない…」
「データを集めて『可視化』はしたが、そこから先、一向に利益に結びつかない…」
お世話になっております。船井総研の塩田です。
製造業のDX推進において、このような「やったつもりDX」に陥っているケースは後を絶ちません。最新鋭の技術を導入しても、なぜか成果が出ない。その原因は、技術そのものではなく、その「進め方」や「マインドセット」にあることがほとんどです。
多くの企業がつまずく共通の「落とし穴」。今回は、特に陥りがちな3つ落とし穴を、処方箋とともに解説します。
目次
落とし穴1:「とりあえずAI」がすべてをダメにする【目的化の罠】
最も多く、そして根深いのがこの罠です。「手段」であるはずのツール導入が、いつの間にか「目的」にすり替わってしまいます。
典型的な失敗例は、「競合のA社がAIによる画像検品を導入したから、ウチも遅れてはならない」「国から大型の補助金が出るから、このIoTパッケージシステムを導入しよう」といったように、「ツールありき」でプロジェクトがスタートするケースです。しかし、いざ導入してみると、現場の本当の課題(ペイン)とズレていることが発覚します。
現場が本当に困っていたのは「検品作業」ではなく、「頻繁な段取り替えの手間」や「ベテランのノウハウの属人化」だったかもしれません。その場合、高額なAI検品システムは「余計な仕事」と見なされ、結局「従来通りの目視検品の方が早い」と埃をかぶることになります。
【処方箋】
DXは「デジタル”で”トランスフォーメーション(変革)する」ことである、という原点に立ち返るべきです。まず問うべきは「どのツールを使うか?」ではありません。「自社のどの課題を解決し、どのような姿に変革したいのか?」です。
「AIを導入したい」ではなく、「熟練工でしかできなかった検品作業を自動化し、工数を30%削減する。その人員を、より付加価値の高い改善活動にシフトさせる」という明確な「目的」を先に立てる必要があります。課題ドリブンで考えることこそ、DX成功の第一歩です。
落とし穴2:社長の「よろしく」が現場の士気を下げる【経営丸投げの罠】
DXは、既存の業務プロセスや組織の壁を打ち破る「変革」活動です。その推進を現場やIT部門だけに「丸投げ」した瞬間、失敗が約束されます。
例えば、経営会議で社長が「DXは重要だ。予算はつける。あとはDX推進室(またはIT部門)で、うまくやってくれ」と指示だけ出すケースがこれにあたります。推進担当者が現場のDX、たとえば生産データと設計データの連携などを進めようとすると、製造部門と設計部門の間で「データの形式が違う」「ウチの仕事が増える」といった根強い利害対立が発生します。
ここで経営層に仲裁や意思決定を求めても、「現場同士でうまく調整してくれ」と差し戻されてしまうのです。トップの本気度が見えないと、現場は「どうせまた掛け声だけだろう」「面倒なことを押し付けられた」と冷めてしまいます。抵抗勢力を前に、推進担当者だけが疲弊し、プロジェクトは静かに塩漬けとなります。
【処方箋】
DXは「経営マター」であると断言できます。DXを阻む最大の壁は、技術ではなく「組織の壁」と「古い慣習」です。
これを打ち破る権限を持っているのは、全社を動かせる経営トップ以外にいません。
社長の仕事は、予算をつけることやハンコを押すことではありません。明確なビジョン(DXによって会社をどう変えるか)を発信し続け、変革を阻害する古いルールや部門間の壁を自ら先頭に立って壊し、そして失敗を恐れず挑戦する現場を賞賛し、責任を取ることです。DX担当者を任命して終わりではなく、社長自身が「DX最高責任者」としての覚悟を示す必要があります。
落とし穴3:「目先の利益」だけを追い、大きな構想を見失う【近視眼の罠】
DXを「既存業務のちょっとした改善」や「単発のコストダウン」の手段としか捉えていないと、本質的な変革のチャンスを逃してしまいます。
典型的なのは、現場の「紙の帳票をタブレット入力にしたい」という要望に応え、システムを導入するようなケースです。確かにペーパーレス化は実現し、現場は一時的に満足するかもしれません。これが「目先のメリット」です。
しかし、その入力データが「どの工程の品質向上に使えるか」「設計部門にフィードバックして開発に活かせないか」といった、部門を横断したデータ活用の構想が全くないとどうなるでしょう。結果、データは入力されるだけで活用されず、「デジタル化(Digitization)」はしたものの、会社全体の「変革(Transformation)」には繋がらないのです。これでは、高価な「デジタル文房具」を買っただけで終わってしまいます。
【処方箋】
DXの真価は、個別の「点」の改善ではなく、それらを繋げて「線」や「面」にし、製造プロセス全体、さらにはビジネスモデル自体を変革することにあります。
「その投資は、目先の工数削減(点)だけでなく、5年後のサプライチェーン全体の最適化(面)にどう繋がるのか?」「そのデータは、単なる可視化(点)だけでなく、将来の『技術継承』や『予知保全』(線)にどう貢献するのか?」
このように、より大きな構想、広いスパンで考えることで、一見バラバラに見える投資が「意味を持った未来への布石」となります。「木を見て森を見ず」になっていないか。自社のDX構想を、もう一度大局観で捉え直すことが不可欠です。