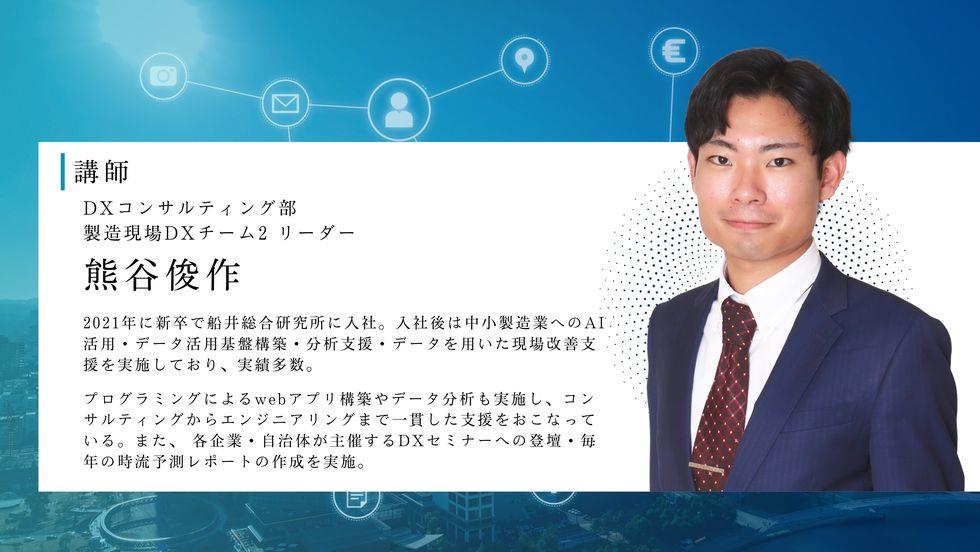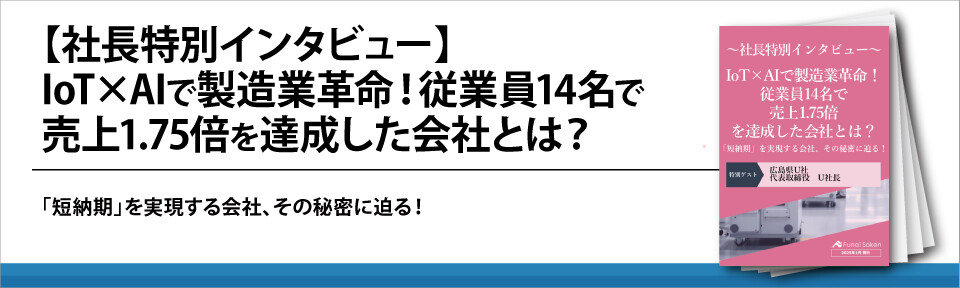記事公開日:2025.03.24
最終更新日:2025.03.25
原価企画とは?【徹底解説】初心者でもわかる目的・進め方・成功の秘訣集
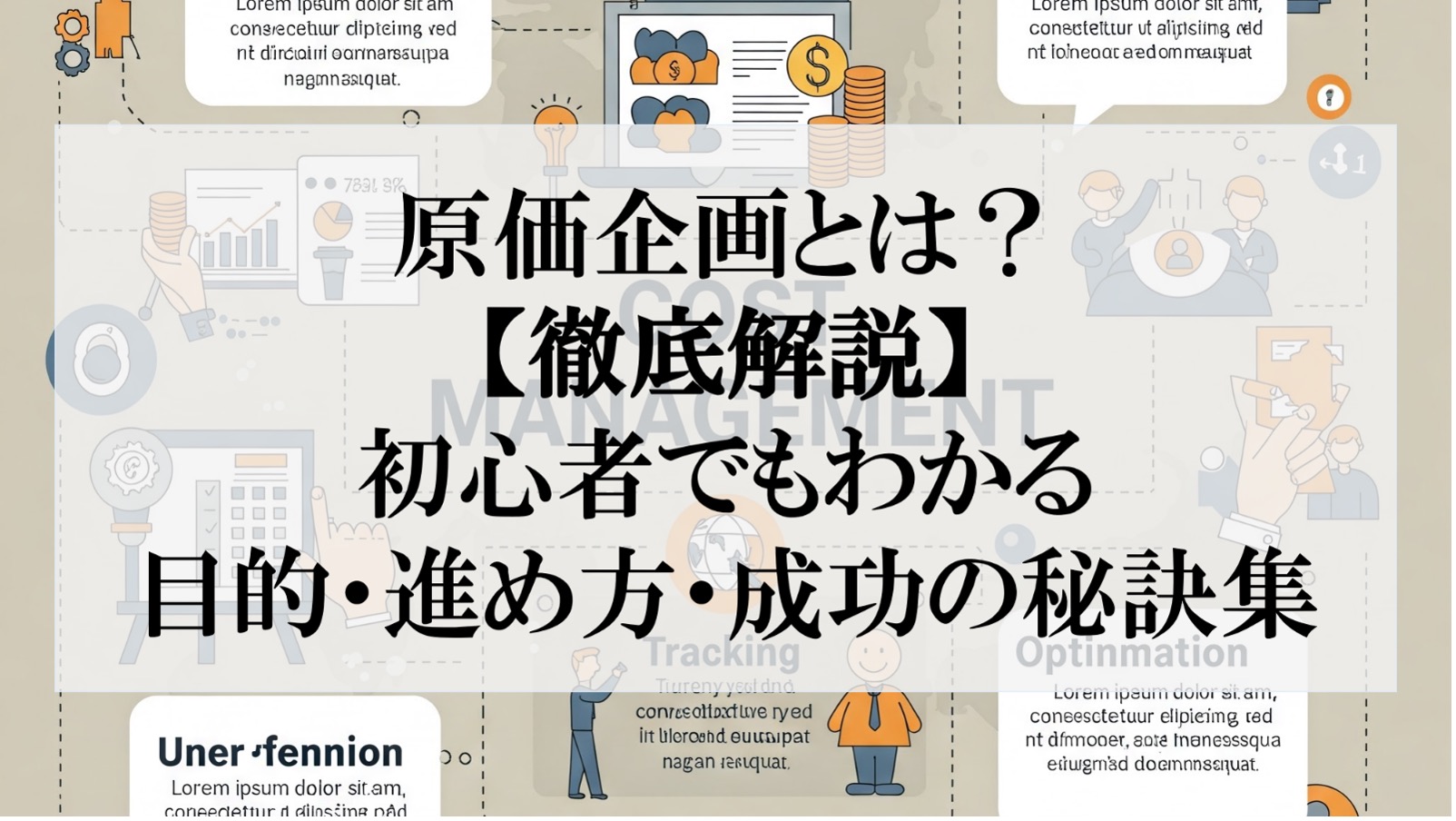
原価企画とは?
製品の初期段階から製造コストを抑えるための活動を徹底解説。
初心者でもわかる進め方や管理方法、設計段階からの参考情報も満載。コスト削減に繋がる企画の進め方を解説します。
目次
はじめに
いつも本コラムをご覧いただき、ありがとうございます。
多品種少量生産という特性上、どうしても複雑になりがちなコスト管理でお悩みを抱えていませんでしょうか?原材料費の高騰、人件費の増加、そして多様化する顧客のニーズに応えるための製品開発。これらの要素が複雑に絡み合い、気がつけば利益が圧迫されている、そんな状況に直面している経営者の方や現場の担当者の方もいらっしゃるかもしれません。
本日は、そんな皆様の悩みを解決する鍵となる原価企画について、徹底的に解説いたします。この記事を読むことで、原価企画とは何かという基本的な知識から、具体的な進め方、そして成功のための秘訣まで、初心者の方にもわかりやすくご理解いただけます。
具体的には、原価企画の定義、その必要性、そして実際にどのように導入し、活用していくのかをステップごとにご紹介します。また、多品種少量生産という特性を持つ中小・中堅製造業ならではの視点も踏まえ、明日から実践できる具体的な方法やポイントを盛り込みました。
この記事は、以下のような方に特におすすめです。
- 原価企画という言葉は聞いたことがあるけれど、具体的に何をすればいいのかわからない方
- 現在行っているコスト管理に限界を感じている方
- 新しいコストダウンの手法を模索している中小・中堅製造業の経営者や担当者の方
- 製品開発の初期段階からコストを意識した取り組みを始めたい方
2025年最新版として、最新の動向や情報も交えながら、原価企画の全貌を明らかにしていきますので、ぜひ最後までお読みください。
きっと、皆様のビジネスに役立つ情報が見つかるはずです。
第1章:原価企画とは?その基礎知識をあっという間に理解

1-1. 原価企画とは何か?初心者向けわかりやすく解説
まず、原価企画とは一体何なのでしょうか?
原価、企画、とはという三つのキーワードを分解して考えてみましょう。原価とは、製品やサービスを生み出すためにかかった費用のことです。材料費、労務費、製造にかかる間接費などが含まれます。企画とは、目標を達成するために計画を立て、実行していくことです。
つまり、原価企画とは、製品の開発や設計の初期段階から、目標とする原価を達成するために、具体的な計画を立て、実行していく一連の活動を指します。これは、単に製造した後でコストを削減する原価低減活動とは大きく異なります。
従来の原価管理は、主に製造が始まった後のコストを把握し、管理することに重点が置かれていました。例えば、実際にかかった原価を計算し、予算と比較したり、無駄なコストを探して削減したりする活動が中心です。
しかし、原価企画は、もっと川上の段階、つまり製品のコンセプトを考え、設計を行う初期の段階から、目標とする原価を織り込んでいく点が特徴です。これにより、製造が開始された後の手戻りを防ぎ、より効果的なコストダウンを実現することが可能になります。
なぜ今、原価企画が注目されているのでしょうか?その背景には、市場の急速な変化やグローバルな競争の激化といった外部環境の要因があります。顧客のニーズは多様化し、製品ライフサイクルは短期化しています。このような状況下では、従来の原価管理だけでは、十分な利益を確保することが難しくなってきています。
そこで、製品の開発の初期からコストを意識し、目標とする原価を達成するための計画を立てる原価企画が、競争力を高めるための重要な戦略として、多くの企業に認識されるようになってきたのです。特に、多品種少量生産を行う中小・中堅製造業においては、一つ一つの製品にかかる実際のコストをしっかりとコントロールすることが、経営の安定に直結するため、原価企画の重要性はますます高まっています。
1-2. 原価企画の目的:コスト削減だけではない真の狙い
原価企画の主な目的は、コスト削減であることは間違いありません。
しかし、その狙いは単にコストを下げることだけではありません。より深く掘り下げていくと、以下のような重要な目的が見えてきます。
まず、第一に挙げられるのは利益創出への貢献です。製品の開発段階から目標原価を設定し、それを達成することで、販売価格を抑えながらも十分な利益を確保することが可能になります。これは、競争が激しい市場において、企業が持続的に成長していくための重要な要素となります。
次に、製品開発における初期段階の重要性です。設計が完了し、製造段階に入ってからコストを見直すのは、時間も手間もかかり、抜本的なコストダウンは難しいものです。原価企画では、製品のコンセプト設計や基本設計の段階からコストを意識することで、より効果的にコストをコントロールすることができます。この初期の段階での取り組みが、最終的な製品の原価を大きく左右すると言えるでしょう。
さらに、競争優位性の確立も原価企画の重要な目的の一つです。他社よりも低い原価で高品質な製品を提供できれば、市場における競争力を高めることができます。これは、中小・中堅製造業が大手企業と差別化を図り、独自のポジションを築く上で非常に有効な手段となります。
そして、イノベーションの促進も原価企画の隠れた目的と言えるかもしれません。目標原価を達成するために、従来のやり方にとらわれず、新しい技術や材料、製造プロセスを検討する過程で、イノベーションが生まれる可能性があります。制約があるからこそ、新しい発想が生まれるというのは、よく言われることですが、原価企画もその一例と言えるでしょう。
このように、原価企画は単なるコスト削減の手段ではなく、利益の創出、効率的な製品開発、競争力の強化、イノベーションの促進など、多岐にわたる目的を持っているのです。これらの目的をしっかりと理解し、原価企画に取り組むことで、中小・中堅製造業はより強固な経営基盤を築くことができるでしょう。
1-3. 原価企画の必要性:変化する時代に対応するために
現代社会は、目まぐるしい変化の時代です。
中小・中堅製造業を取り巻く環境も例外ではありません。ここでは、原価企画がなぜこれほどまでに必要とされているのか、その背景にある要因を詳しく見ていきましょう。
まず、市場ニーズの多様化と短期化が挙げられます。顧客の好みや要求は多様化し、製品のライフサイクルは以前に比べて格段に短くなっています。このような状況下では、常に新しい製品を迅速に、かつコストを抑えて市場に投入する必要があります。原価企画は、このようなスピード感のある製品開発を可能にするための重要なツールとなります。
次に、グローバル競争の激化です。インターネットの普及により、世界中の企業が競争相手となり得る現代において、コスト競争力は生き残りのための必須条件です。原価企画を通じて製品の原価を徹底的に見直すことで、国際的な市場でも十分に戦える競争力を身につけることができます。
また、資源価格の変動リスクも無視できません。原材料やエネルギーの価格は常に変動しており、これらの価格変動は製品の原価に大きな影響を与えます。原価企画では、このようなリスクを予測し、変動に強いコスト構造を持つ製品を開発することが求められます。代替材料の検討や、長期的な視点での調達戦略などが重要になります。
そして、売れる製品開発への貢献も原価企画の重要な側面です。単にコストを下げるだけでなく、顧客が求める品質や機能を維持しながら、目標原価を達成することが、売れる製品を生み出すための鍵となります。原価企画は、顧客のニーズとコストのバランスを取りながら、製品開発を進めていくための羅針盤となるのです。
このように、現代のビジネス環境は、中小・中堅製造業にとって多くの課題と機会をもたらしています。原価企画は、これらの課題に対応し、機会を最大限に活かすための強力な武器となります。変化の激しい時代を生き抜くために、原価企画の導入と活用は、もはや避けて通れない道と言えるでしょう。
第2章:原価企画の進め方:ステップごとに徹底解説【実践編】
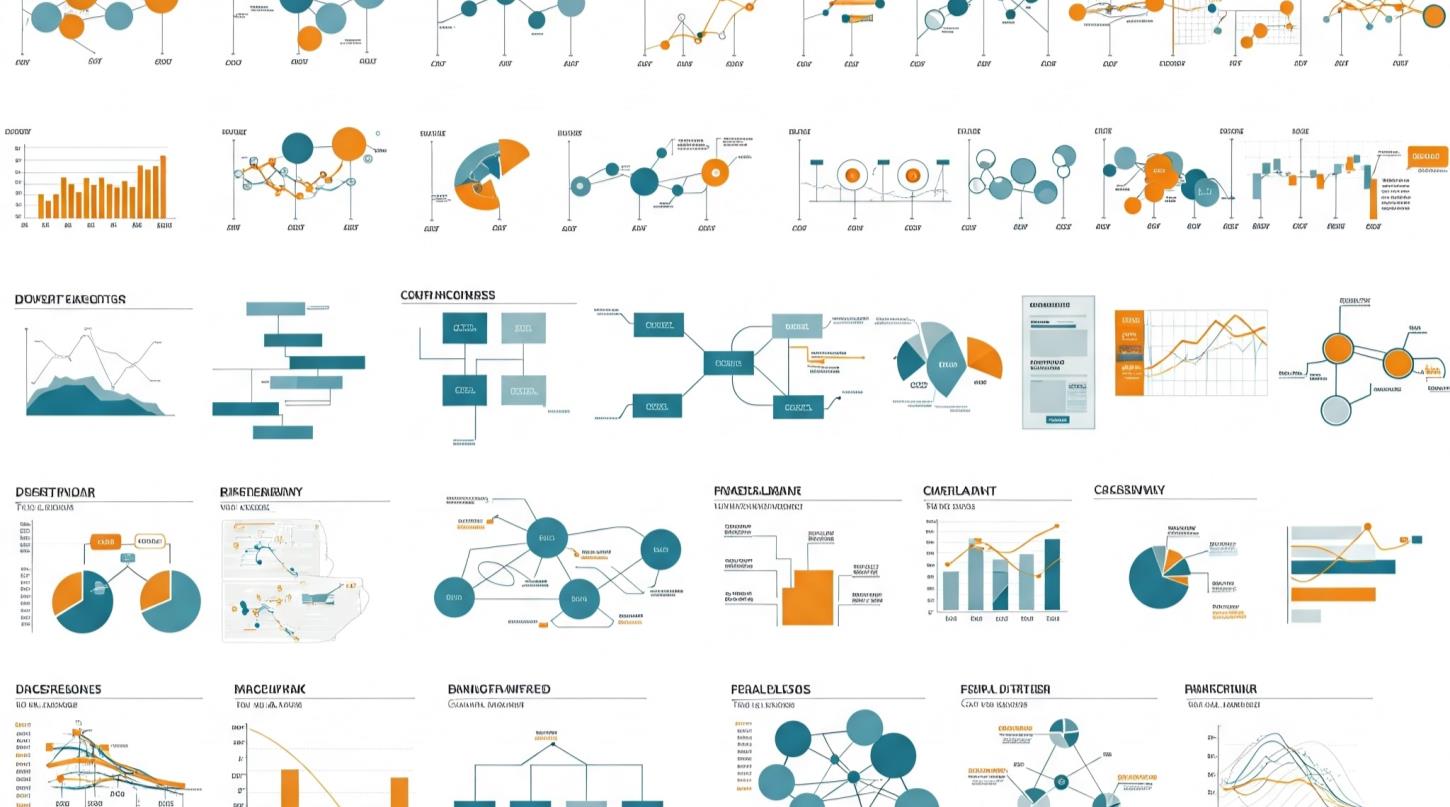
原価企画の必要性や目的をご理解いただけたところで、ここからは実際にどのように原価企画を進めていくのか、具体的なステップを解説していきます。中小・中堅製造業の皆様が、自社で実践できるよう、各ステップを丁寧に見ていきましょう。
2-1. ステップ1:目標原価の設定
原価企画の最初のステップは、目標原価を設定することです。
目標原価とは、開発しようとする製品について、達成すべき原価の目標値のことです。この目標原価の設定が、その後の原価企画の成否を大きく左右するため、非常に重要な段階と言えます。
目標原価を設定するためには、まず市場調査と顧客ニーズの分析を徹底的に行う必要があります。どのような顧客層が、どのような価格帯の製品を求めているのか、競合となる他社の製品はどのような価格で販売されているのか、といった情報を収集し、分析します。この分析結果が、目標価格を決定する際の重要な判断材料となります。
次に、競合製品の原価分析を行います。他社の製品がどのようなコスト構造になっているのかを推定し、自社の製品が競争力を持つためには、どの程度の原価に抑える必要があるのかを検討します。可能であれば、分解調査などを行い、より詳細な原価情報を入手することも有効です。
そして、目標利益の設定を行います。企業として、その製品からどれだけの利益を得たいのかを明確にします。これは、経営戦略に基づいて決定されるべき事項であり、目標価格と目標原価の差として表されます。
これらの情報を総合的に考慮し、最終的な目標原価を決定します。この際、実現可能性を考慮した目標設定が非常に重要です。あまりにも非現実的な目標を設定してしまうと、その後の企画活動が頓挫してしまう可能性があります。過去の実績や、現在の技術力、サプライヤーとの協力体制などを考慮しながら、ストレッチ目標でありつつも、達成可能な目標を設定することが求められます。
2-2. ステップ2:機能分析とコスト分析
目標原価が設定されたら、次のステップでは、製品の機能分析とコスト分析を行います。
ここでは、製品が顧客にどのような価値を提供しているのかを明確にし、そのためにどれだけのコストがかかっているのかを詳細に把握します。
まず、製品の機能を明確化します。顧客がその製品に求めている主要な機能、付加価値となる機能などをリストアップし、それぞれの機能が顧客にとってどれほどの価値を持つのかを評価します。この際、顧客ニーズをしっかりと捉えることが重要です。
次に、各機能に必要なコストの洗い出しを行います。それぞれの機能を実現するために、どのような部品や材料が必要なのか、どのような製造工程を経るのかを詳細に分析し、それぞれの段階で発生するコストを算出します。このコストには、直接的な材料費や労務費だけでなく、間接費も含まれます。
そして、コスト構造の見える化を行います。どの機能にどれだけのコストがかかっているのかをグラフや表などで分かりやすく整理することで、改善の余地がある部分を特定しやすくなります。この見える化によって、コストの無駄や非効率な部分が明確になり、具体的な改善策を検討するための土台が築かれます。
この段階で有効な手法の一つが、バリューエンジニアリング(VE)の導入です。VEとは、製品の機能価値を維持しながら、ライフサイクル全体にわたるコストを最小化するための組織的な取り組みです。VEを通じて、製品の機能とコストのバランスを最適化し、目標原価の達成を目指します。
2-3. ステップ3:アイデア創出と代替案検討
機能分析とコスト分析を通じて、コスト削減の余地がある部分が明らかになったら、次のステップでは、具体的なコストダウンのためのアイデア創出と代替案検討を行います。
ここでは、自由な発想で様々な可能性を探ることが重要です。
コストダウンのための多角的な視点を持つことが求められます。例えば、以下のような視点からアイデアを検討します。
- 設計の見直し(設計段階からのコスト削減):部品点数を減らす、標準化された部品を使用する、より安価な材料で代替する、など。
- 材料の変更や調達先の見直し:より安価で品質の良い材料を探す、複数のサプライヤーから見積もりを取り比較する、長期契約によるボリュームディスカウントを交渉する、など。
- 製造プロセスの効率化:作業手順を見直す、自動化を導入する、不良率を低減する、リードタイムを短縮する、など。
この段階では、特定の部署だけでなく、営業、開発、製造、管理など、様々な部門の担当者が集まり、それぞれの専門知識や経験を活かしてアイデアを出し合うことが効果的です。ブレーンストーミングなどの手法を用いて、活発な意見交換を行うと良いでしょう。
また、単にコストを下げるだけでなく、品質を維持、あるいは向上させるためのアイデアも同時に検討することが重要です。安易なコストダウンは、製品の品質低下を招き、顧客満足度を損なう可能性があります。
さらに、環境負荷の低減や、持続可能な社会の実現に貢献するようなアイデアも、検討の対象に入れると、企業のイメージ向上にも繋がる可能性があります。
このステップでは、検討された複数の代替案について、それぞれのコスト削減効果、実現可能性、リスクなどを評価し、最適な案を選択していきます。
2-4. ステップ4:目標原価達成のための施策実行
アイデア創出と代替案検討のステップで最適な案が選択されたら、次のステップでは、目標原価達成のための施策実行に移ります。ここでは、具体的な計画を立て、実行に移していく段階です。
まず、具体的な改善策の実施計画を策定します。いつまでに、誰が、何を、どのように行うのかを明確にし、スケジュールを立てます。この計画には、必要なリソース(人員、設備、資金など)も明記します。
関連部署との連携(管理部門との連携)も非常に重要です。原価企画は、特定の部署だけで完結するものではなく、設計、開発、製造、購買、営業、管理など、多くの部署が連携して取り組む必要があります。それぞれの部署が、それぞれの役割を理解し、協力し合うことで、計画は円滑に進みます。特に、管理部門は、コストに関する専門知識やデータを持っているため、積極的に連携を図ることが求められます。
また、サプライヤーとの協力体制構築も重要なポイントです。材料費の削減や、より効率的な調達方法の実現には、サプライヤーとの協力が不可欠です。目標を共有し、共にコストダウンに取り組むための良好な関係を築くことが、成功への鍵となります。
施策の実行にあたっては、進捗状況を定期的に確認し、管理することが重要です。計画通りに進んでいない場合は、原因を特定し、必要に応じて計画を修正します。この段階では、柔軟に対応することが求められます。
2-5. ステップ5:効果測定と管理、見直し
施策が実行されたら、最後のステップとして、効果測定と管理、見直しを行います。ここでは、実際にどれだけのコスト削減効果が得られたのかを検証し、今後の原価企画活動に活かすための反省点や改善点を見つけ出します。
まず、実績原価の把握を行います。施策実行後の実際の原価を正確に計算し、把握します。これには、材料費、労務費、間接費など、全てのコストが含まれます。
次に、目標との差異分析を行います。設定した目標原価と、実際に発生した実績原価を比較し、どれだけの差異があったのか、その原因は何だったのかを分析します。差異が大きかった場合は、その理由を詳細に調査し、今後の対策を検討します。
そして、改善効果の測定を行います。実施した施策によって、どれだけのコストダウン効果があったのかを数値で明確に示します。この効果測定の結果は、社内への報告や、今後の原価企画活動へのモチベーション向上に繋がります。
最後に、次期企画へのフィードバックを行います。今回の原価企画活動全体を振り返り、うまくいった点、課題となった点、改善すべき点などを洗い出し、その教訓を次回の原価企画に活かします。原価企画は一度行ったら終わりではなく、継続的に改善していくことが重要です。
この5つのステップをしっかりと踏むことで、中小・中堅製造業においても、原価企画を効果的に進め、目標とするコストダウンを実現することが可能になります。
第3章:原価企画を成功させるための秘訣とポイント
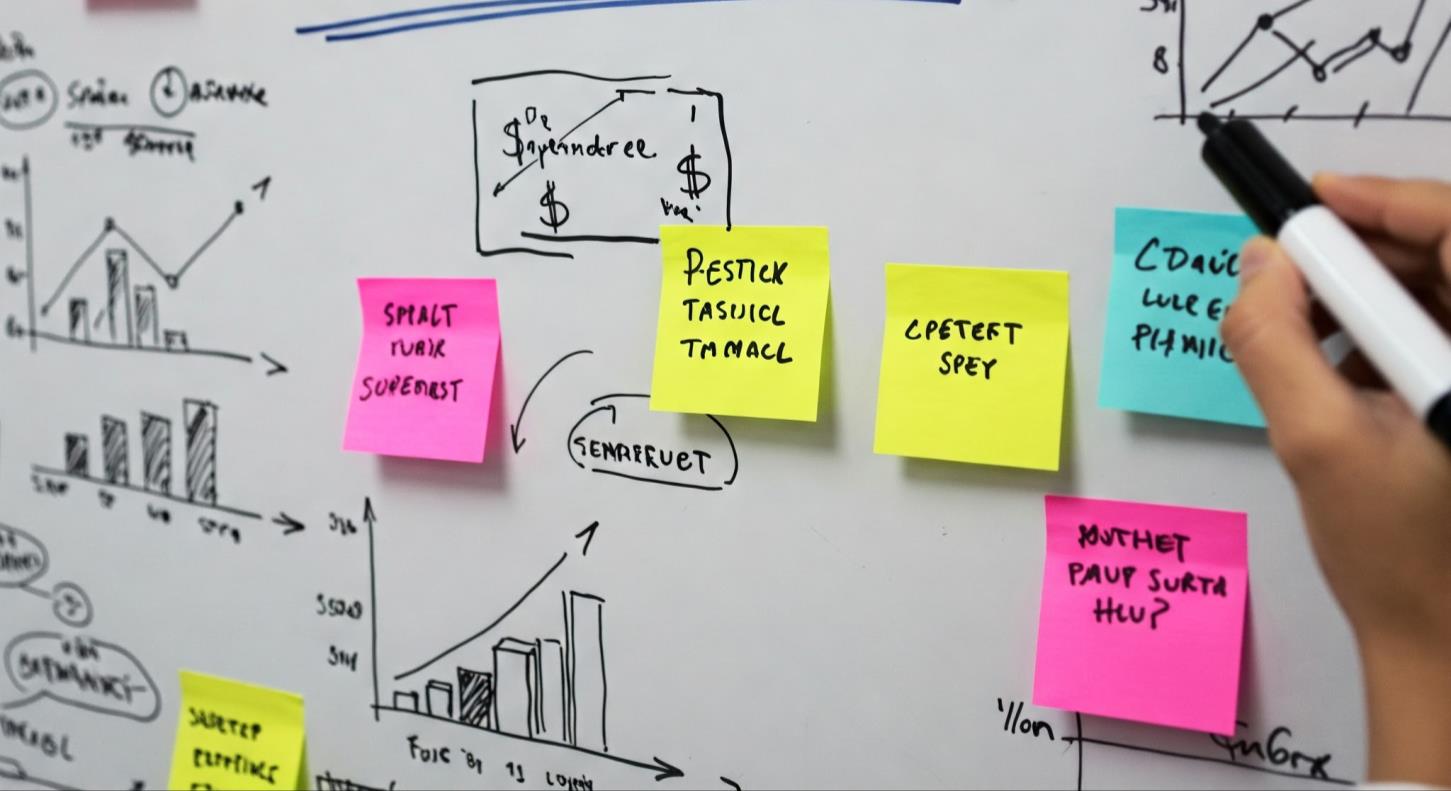
原価企画を導入し、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要な秘訣とポイントがあります。ここでは、中小・中堅製造業が原価企画を成功させるために、特に意識すべき点を詳しく見ていきましょう。
3-1. 経営層の理解とコミットメントの重要性
原価企画を成功させるためには、何よりも経営層の理解とコミットメントが不可欠です。
経営トップが原価企画の重要性を認識し、積極的に推進する姿勢を示さなければ、社内にその意識は浸透しません。経営層が目標を設定し、必要なリソースを確保し、進捗状況を定期的に確認することで、全社的な取り組みとして原価企画を根付かせることができます。
3-2. 部門間の連携と情報共有の促進
前述の通り、原価企画は、単一の部門だけで完結するものではありません。
設計、開発、製造、購買、営業、管理など、様々な部門がそれぞれの専門知識を持ち寄り、連携して取り組む必要があります。そのため、部門間の壁を取り払い、円滑な情報共有を促進するための仕組みづくりが重要です。定期的な会議の開催や、情報共有ツールの導入などが有効です。
3-3. チームワークとモチベーションの維持
原価企画は、原価改善までを含めると長期にわたる取り組みとなることもあります。
そのため、プロジェクトに関わるメンバーのチームワークを醸成し、高いモチベーションを維持することが重要です。目標達成に向けた一体感を高め、成功体験を共有することで、更なる取り組みへの意欲を引き出すことができます。
3-4. データに基づいた意思決定
原価企画の各段階において、客観的なデータに基づいた意思決定を行うことが重要です。
勘や経験に頼るのではなく、市場調査データ、競合製品の原価分析データ、自社のコストデータなどをしっかりと収集し、分析した上で判断を下すことで、より効果的な企画を進めることができます。
3-5. 継続的な改善活動の推進
原価企画は一度実施したら終わりではありません。
市場環境や顧客ニーズは常に変化するため、原価企画も継続的に見直し、改善していく必要があります。定期的に活動の成果を評価し、反省点や改善点を見つけ出し、次の企画に活かすサイクルを確立することが重要です。
3-6. 初期段階からの綿密な計画
原価企画は、製品開発の初期段階から始めることが最も効果的です。
コンセプト設計や基本設計の段階でコスト目標を織り込むことで、その後の設計変更の手戻りを減らし、より効率的に目標原価を達成することができます。初期の段階での綿密な計画が、成功の鍵を握ると言えるでしょう。
3-7. 最新技術やシステムの活用
近年では、コスト管理や設計支援など、様々な業務を効率化するための最新技術やシステムが登場しています。
これらのツールを積極的に活用することで、原価企画の精度を高め、作業負荷を軽減することができます。自社の課題やニーズに合わせて、適切なツールを導入することを検討しましょう。
3-8. 外部のコンサルティングサービスの活用
もし、自社内に原価企画に関する十分な知識やノウハウがない場合は、外部のコンサルティングサービスの利用も有効な手段です。専門的な知識や豊富な経験を持つコンサルタントのサポートを受けることで、より効果的な原価企画を導入し、成功に導くことができます。
これらの秘訣とポイントを踏まえ、自社の状況に合わせて原価企画に取り組むことで、中小・中堅製造業はコストダウンを実現し、競争力を高めることができるでしょう。

第4章:原価企画に関する事例紹介
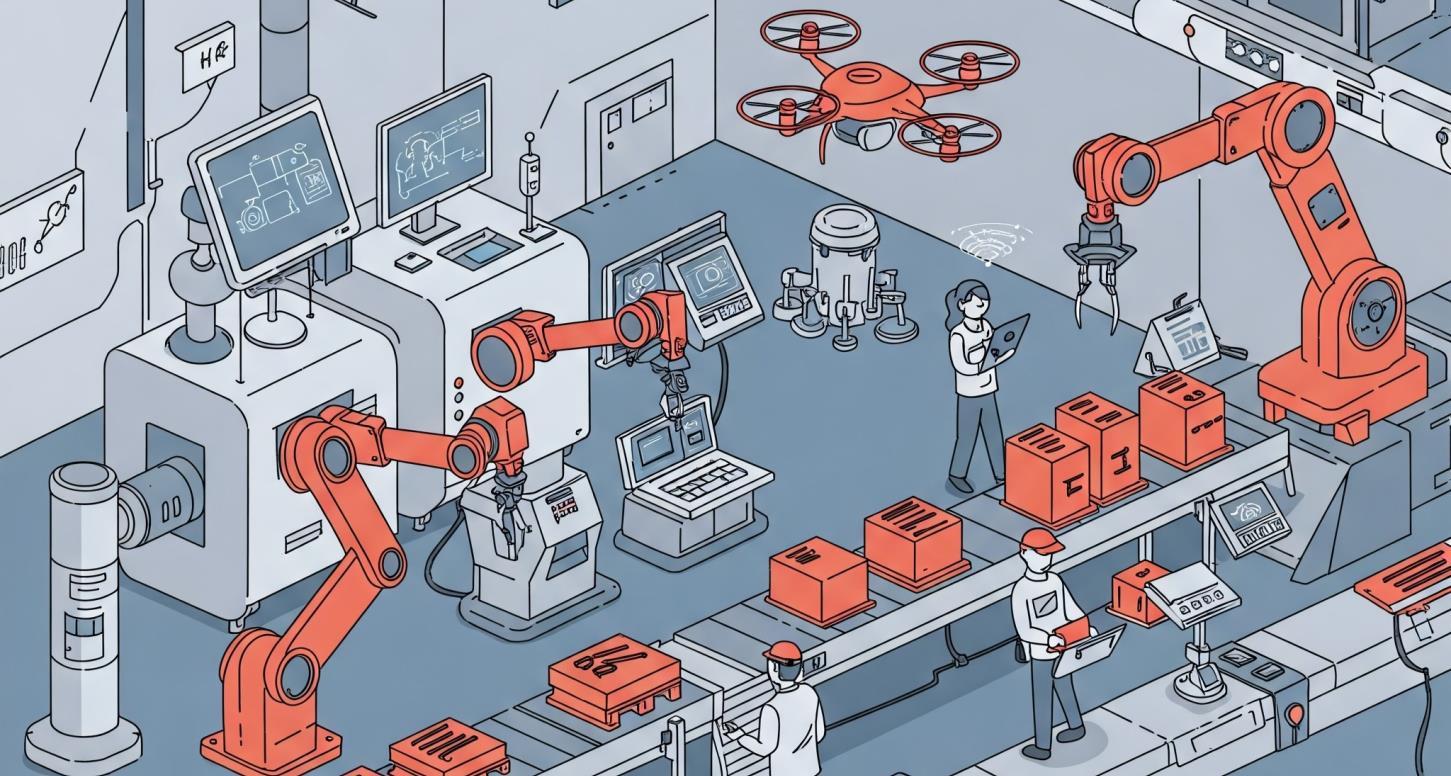
ここでは、原価企画に関するより深い理解を得ていただくために、事例紹介を行います。
4-1. 原価企画の理論と実践のギャップ
原価企画の理論は理解できても、実際に自社で実践するとなると、様々な壁にぶつかることがあります。
例えば、目標原価を設定しても、それを達成するための具体的な方法が見つからない、部門間の協力体制がうまく構築できない、といったケースです。
このようなギャップを埋めるためには、単に理論を学ぶだけでなく、実際に原価企画を導入し、成功させている企業の事例を参考にすることが非常に役立ちます。他社がどのように課題を乗り越え、目標を達成しているのかを知ることで、自社に合った進め方を見つけるヒントが得られるはずです。
また、原価企画は、一朝一夕に効果が出るものではありません。継続的な取り組みと、失敗から学び、改善していく姿勢が重要です。実践の中で得られた経験を社内で共有し、ノウハウとして蓄積していくことが、長期的な成功に繋がります。
4-2. コラム:原価企画でイノベーションは生まれるのか?
原価企画というと、どうしてもコスト削減というイメージが先行しがちですが、実はイノベーションを生まれるきっかけにもなり得ます。目標原価という制約の中で、製品の機能や品質を維持、あるいは向上させるためには、従来のやり方にとらわれず、新しい技術や発想を取り入れる必要が出てきます。
例えば、より安価で高性能な代替材料を探したり、全く新しい製造プロセスを開発したりする過程で、イノベーションが生まれることがあります。また、顧客のニーズを深く理解し、それを満たすための新しい機能を低コストで実現しようとすることで、画期的な製品が誕生することもあるでしょう。
原価企画は、単なるコストダウン活動ではなく、企業の成長と発展に繋がるイノベーションの源泉となる可能性を秘めているのです。
4-3. 事例紹介:成功企業の原価企画事例
ここでは、原価企画を効果的に導入し、成功を収めている企業の事例をいくつかご紹介します。
例えば、とある製造業では、製品開発の初期段階から徹底的な原価企画を行い、高品質でありながらも競争力のある価格の製品を市場に提供しています。同社では、VE活動を積極的に推進し、サプライヤーとの連携を強化することで、コストダウンを実現しています。
中小・中堅製造業においても、原価企画を導入し、成功している企業は数多く存在します。
例えば、従業員数30名の金属加工業では、原価企画を通じて、材料の調達方法を見直し、歩留まりを改善することで、大幅なコストダウンを達成しました。多品種少量生産ですが、類似の製品で分類分けを実施し、同じ分類の製品ごとの原価率を指標として設定することで現場における実際の現場改善も実現しています。
また、別の機械メーカーでは、設計段階からコストを意識した設計ルールを導入することで、製造コストを大幅に削減することに成功しています。
これらの事例からわかるように、原価企画は、規模の大小に関わらず、様々な製造業において有効な手法であることがわかります。
4-4. 事例紹介:中小・中堅企業における原価企画の導入事例
中小・中堅企業においては、リソースが限られているため、原価企画の導入に二の足を踏むケースもあるかもしれません。しかし、工夫次第で、中小・中堅企業でも効果的な原価企画を導入し、活用することができます。
例えば、ある中小・中堅製造業では、まずは一部の主力製品に絞って原価企画を試験的に導入しました。外部のコンサルタントのサポートを受けながら、進め方を学び、自社に合ったやり方を模索しました。その結果、わずかな期間でコストダウンの効果を実感し、その後、他の製品にも順次展開していきました。
また、別の中小・中堅企業では、既存の業務プロセスの中で、原価企画の考え方を少しずつ取り入れることから始めました。設計段階でのコスト意識の向上や、サプライヤーとの定期的な情報交換などを実施することで、大きな投資をすることなく、コストダウンに繋がる成果を上げています。
これらの事例は、中小・中堅企業でも原価企画は十分に導入可能であり、その効果を期待できることを示唆しています。
第5章:原価企画に関するQ&A
ここでは、原価企画に関してよく寄せられる質問とその回答をご紹介します。
5-1. 原価企画に関するよくある質問
Q:原価企画はどのような業種に向いていますか?
A:原価企画は、製品を製造するあらゆる業種で有効です。特に、自動車、電機、機械などの組み立て製造業や、部品製造業など、複数の部品や工程を経て製品が完成する業種で、その効果を発揮しやすいと言えます。多品種少量生産を行う中小・中堅製造業においても、一つ一つの製品のコストを管理し、利益を確保するために非常に役立ちます。
Q:原価企画を導入する際の注意点は?
A:原価企画を導入する際には、まず経営層の強いコミットメントを得ることが重要です。また、全社的な取り組みとなるため、関連部署との連携を密に行う必要があります。無理なコストダウンは品質低下を招く可能性があるため、品質を維持しながらコストを下げるというバランスを意識することも大切です。
Q:原価企画に必要な知識やスキルは?
A:原価企画には、原価計算の知識はもちろんのこと、製品設計や製造プロセスに関する知識、VE/VAなどの手法に関する知識など、幅広い知識とスキルが求められます。また、関係者と円滑にコミュニケーションを取り、協力体制を構築するためのコミュニケーション能力も重要です。
第6章:まとめ:今日から実践できる!原価企画の第一歩
今回のコラムでは、原価企画とは何かという基本的な知識から、進め方、そして成功のための秘訣までを詳しく解説してきました。特に、多品種少量生産を行う中小・中堅製造業の皆様に向けて、実践的な情報をお届けすることを意識して作成しました。
原価企画は、単なるコストダウンの手法ではなく、企業の利益を創出し、競争力を高めるための重要な経営戦略の一つです。製品開発の初期段階からコストを意識した取り組みを行うことで、無駄を省き、より効率的な事業運営を実現することが可能になります。
この記事を読んで、原価企画に興味を持たれた方は、ぜひ今日からできることから始めてみてください。まずは、自社の製品のコスト構造を分析し、どの部分に改善の余地があるのかを見つけることから始めてはいかがでしょうか。
そして、この記事でご紹介した進め方や成功のためのポイントを参考に、自社に合った原価企画の方法を模索してみてください。最初は小さな一歩かもしれませんが、継続していくことで、必ず大きな成果が得られるはずです。
もし、原価企画の導入や活用に関して、さらに詳しい情報やサポートが必要な場合は、お気軽に当社までお問い合わせください。中小・中堅製造業の皆様のビジネスの発展を、全力でサポートさせていただきます。
著者情報