記事公開日:2025.07.10
最終更新日:2025.07.10
【金型製造・樹脂加工業向け】生成AI活用セミナー開催!中小企業が今すぐ取り組むべきDXとAI活用の最前線
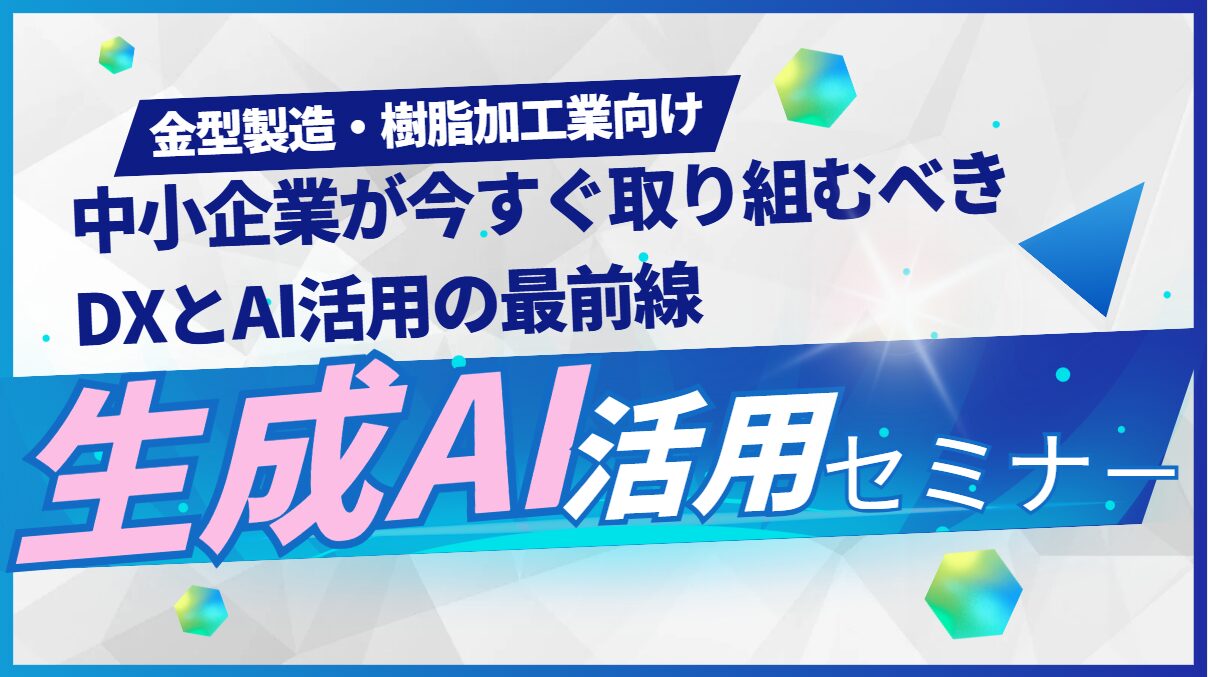
「金型カルテ」による情報共有や「IoT重量センサー」による在庫管理自動化、RPAでの部品発注自動化など、具体的な成功事例を惜しみなくご紹介 。さらに、製造業における生成AIの活用事例や、AIエージェント、MCPなどの最新動向、そして「失敗しない」AI活用戦略まで、明日から実践できるノウハウが満載です 。
現場の「面倒くさい」を「便利」に変えるDXとAIの力を、ぜひこの機会に体験し、貴社の生産性向上と成長への一歩を踏み出しましょう!
URL:https://www.funaisoken.co.jp/seminar/129747
目次
1. 厳しい時代を勝ち抜く!中小製造業のためのAI活用戦略
現代の製造業を取り巻く環境は、国内外の競争激化、人手不足、技術革新の加速など、まさに激動の時代を迎えています。このような状況下で企業が成長し続けるためには、従来のやり方を見直し、新たな技術を積極的に取り入れる「デジタルトランスフォーメーション(DX)」が不可欠です。特に近年目覚ましい進化を遂げている「生成AI」は、製造業に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。
しかし、「AIと聞くと難しそう」「ウチのような中小企業には関係ないのでは?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。本コラムでは、中小製造業こそAI活用に取り組むべき理由と、具体的な活用事例、そして来るセミナーのハイライトをご紹介します。
2. 日本のAI活用状況と中小企業が取り組むべき理由
総務省の調査(2024年)によると、日本における生成AIの利用経験がある人はわずか9.1%に留まります。また、企業においても積極的に活用方針を定めているのは15.7%と、欧米や中国と比較して低い水準にあります。これは裏を返せば、今からAI活用に取り組む企業にとっては、大きな先行者利益を得るチャンスがあるということです。
多品種少量生産を行う製造業においては、熟練技術者のノウハウの属人化、紙媒体での情報管理、非効率な業務プロセスなど、多くの課題を抱えていることと思います。AIはこれらの課題を解決し、生産性向上、コスト削減、品質改善に大きく貢献します。中小企業だからこそ、フットワークの軽さを活かし、AIを戦略的に導入することで、競合との差別化を図り、持続的な成長を実現できるのです。
3. セミナーで学べること:具体的なAI活用事例と成功の秘訣
本セミナーでは、AI活用の基礎から、具体的な導入事例、そして成功のための戦略まで、中小製造業の皆様が「明日から使える」情報を提供します。
第一講座:AI活用基礎:製造業がAI活用できる業務とは?
この講座では、市場におけるAIの最新動向と、中小企業だからこそ取り組むべきAI活用戦略について解説します。AIを活用するために具体的に何をすれば良いのか、多品種少量生産製造業における他社事例を交えながら、AI活用と原価管理の深い関係性についても掘り下げます。
第二講座:カワイ精工様登壇!従業員26名の社内DX・生成AI活用で年間1,100時間削減の秘密!
注目すべきは、従業員26名の株式会社カワイ精工様の登壇です。DX推進前のリアルな課題から、取り組み時の苦悩とそれを乗り越えた過程、そして具体的な成果についてお話しいただきます。
- 金型カルテ(実績のデジタル化):金型に関する様々な情報をデジタル化し、「電子カルテ」として統合的に管理するシステムを導入することで、年間300時間の業務削減を実現しました。顧客からの問い合わせ対応や見積もり業務、部署間の連携業務が大幅に改善されています。
- IoTを活用した在庫管理の自動化:IoT重量センサーを組み込んだ装置を自作し、在庫管理を自動化。管理工数の削減と在庫の最適化を達成しました。
- RPA活用による部品発注作業の自動化:業務の起点でデータを即時デジタル化することで、RPA(Robotic Process Automation)を導入。部品発注作業の自動化により、年間870時間の削減効果を上げています。
カワイ精工様では、DX推進により、プログラミング作業の生産性が平均約2倍に向上したほか、新しい技術の実装においては5〜10倍もの大幅な向上を見せています。さらに、教育向け教材資料の作成時間や、紙からデータ(Excel)を起こす作業も大幅に削減されており、すでにAIが「ない」と仕事にならない状態になっているとのことです。
この講座では、実際の生成AIシステムのデモンストレーションも予定しており、その可能性を肌で感じていただけます。
第三講座:多品種少量生産製造業が知っておくべきAI・IoT活用戦略
最終講座では、自社データを基盤としたAI活用による「失敗しない」DX経営のあり方と、多品種少量生産の製造業が取り組むべきAI活用戦略について深掘りします。
生成AIがもたらす製造現場の未来
生成AIは、単に文章や画像を生成するだけでなく、製造現場においても多岐にわたる活用が期待されています。
- NCプログラムの言語化:Gコードを自動解析し、各行の意味や注意点を日本語で自動生成することで、技術ノウハウの明文化、後進教育、類似品への応用、トラブル対処・防止に貢献します。
- 図面の自動読み取り:2D/3D図面のPDFや画像から、AIが寸法、公差、表面粗さ、指示内容を自動で抽出し、金型設計案などを提案する可能性もあります。
- 社内データの活用:顧客データベース、売上データベース、製造データベースといった社内データを活用し、社内ノウハウや手順書の回答、売上・在庫分析、日報の要約、資料作成などが可能になります。
さらに、「AIエージェント」と「MCP(Model Context Protocol)」の登場により、AIが自律的にPCやアプリケーション、外部サービスを操作できるようになる未来も現実味を帯びてきています。これにより、AIがCADを操作して設計を行ったり、ブラウザを操作して問い合わせや発注業務を自動で行ったりするなど、実務作業を代替する可能性も示唆されています。将来的には、機械メーカーがMCPサーバーを提供することで、AIが直接機械を操作することも可能になるかもしれません。
4. 今こそ、DXとAI活用への第一歩を踏み出しませんか?
DXは単なるITツールの導入ではなく、企業文化の変革です。変化に対する抵抗はつきものですが、目に見える成果を早期に出し、不安な感情を良い感情に変えることが成功の鍵となります。
この機会に、貴社の未来を切り拓くDXと生成AI活用の具体的なヒントを掴んでください。皆様のお申し込みを心よりお待ちしております。
URL: https://www.funaisoken.co.jp/seminar/129747
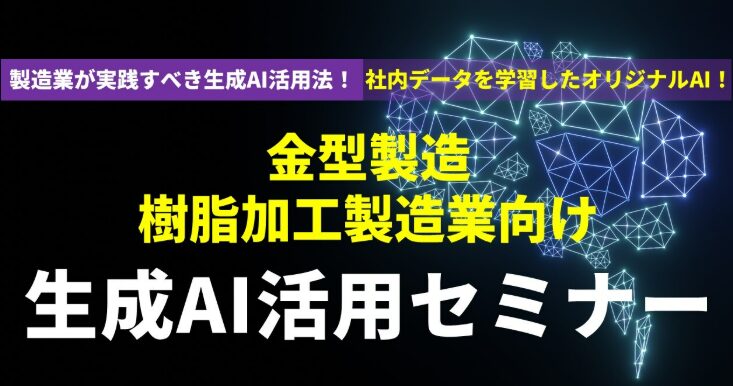
関連コラム

ロボットのティーチングとは?ティーチングの種類と概要を解説
2019.08.27

溶接ロボットで行う自動化の方法とは?
2019.08.29

産業用ロボットとは?最新動向からロボットの違いを知る
2019.09.17


