記事公開日:2025.04.17
最終更新日:2025.04.18
経産省の提言から考える「100億円企業」への挑戦とその実現戦略
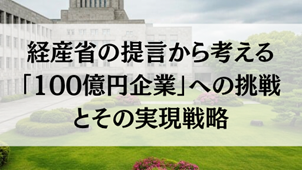
いつもコラムをご愛読いただきありがとうございます。
船井総合研究所の熊谷です。
目次
はじめに:経産省の提言「100億円企業」について
「社長、今のままで、本当に5年後、10年後も会社は大丈夫でしょうか?」
日々、多くの中小製造業の経営者の皆様とお話しする中で、このような漠然とした、しかし深刻な不安の声を耳にする機会が増えています。
- 少子高齢化による深刻な人手不足
- 原材料価格やエネルギーコストの高騰
- グローバル競争の激化
- 急速に進むデジタル化の波
等々・・・
中小製造業を取り巻く経営環境は、かつてないほど厳しく、そして変化のスピードを増しています。
「うちは技術力には自信がある」
「長年の付き合いがあるから大丈夫」
「なんとかやっていけるだろう」
そうした思い込みや現状維持の姿勢は、もはや通用しない時代に突入したと言っても過言ではありません。
変化に対応できなければ、待っているのは緩やかな衰退です。今こそ、過去の成功体験にとらわれず、未来を見据えた大胆な変革、すなわち「成長」へと舵を切るべき時なのです。
しかし、「成長」とは具体的に何を指すのでしょうか?漠然と「会社を良くしたい」と願うだけでは、具体的な行動には繋がりません。
そこで、一つの明確なマイルストーンとして「売上高100億円」という目標を掲げることを、私は強く提唱したいと思います。
「100億なんて、うちのような中小企業には夢物語だ」と感じられるかもしれません。
確かに、容易な目標ではありません。
しかし、この「100億円」という数字は、単なる売上規模を示すだけではありません。
それは、地域経済を牽引し、多くの雇用を生み出し、イノベーションを通じて社会に貢献できる「中堅企業」へと脱皮するための、質的な転換を意味するのです。
幸いなことに、国もまた、こうした意欲ある中小企業のスケールアップを強力に後押ししようとしています。
経済産業省は、中堅・中小企業の成長支援を目的とした「100億企業成長ポータル」を開設しました。
このポータルサイトでは、政府や支援機関の施策情報が一元化されているほか、成長企業の事例などが紹介されており、100億円企業を目指す上での羅針盤となり得るでしょう。
● 経済産業省 プレスリリース「「100億企業成長ポータル」をオープンしました」
https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250411006/20250411006.html
さらに、中小企業庁は「中小企業成長加速化補助金」の公募を開始するなど、企業の成長投資を具体的に支援する動きを加速させています。
こうした国の支援策は、100億円への挑戦を目指す企業にとって、大きな追い風となるはずです。
● 中小企業庁 お知らせ「「中小企業成長加速化補助金」の公募要領を公表しました」
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/koubo/2025/250314001.html
本記事では、なぜ今、中小製造業が「100億円企業」という高い目標を掲げるべきなのか、その意義と、社長自身が得られるメリットを明らかにし、そして、その目標を達成するための具体的な戦略、すなわち「100億円企業へのロードマップ」を詳細に解説していきます。
現状維持か、成長への挑戦か。
未来への分岐点に立つ経営者の皆様にとって、本記事が、勇気を持って次の一歩を踏み出すための、具体的な指針となれば幸いです。
「100億円企業」の魅力とは?社長が得られる5つのメリット
なぜ、あえて「100億円」という高い目標を掲げる必要があるのでしょうか?
それは、高い目標こそが、現状の延長線上にはない、非連続な成長、すなわち「変革」を促す原動力となるからです。
そして、その挑戦の先には、企業全体の成長はもちろんのこと、社長個人にとっても計り知れないメリットが待っています。
ここでは、社長が得られる主な5つのメリットについて解説します。
メリット1:経済的な豊かさ – 努力が報われる確かな対価
まず、最も分かりやすいメリットは経済的な側面です。
企業の利益が大幅に増加すれば、社長自身の役員報酬を引き上げる余地が生まれます。
厳しい経営判断や日々の奮闘が、目に見える形で報われることは、さらなるモチベーションに繋がるでしょう。
また、オーナー経営者であれば、企業価値の向上がそのまま自身の資産価値の向上に直結します。
非上場であっても、将来的なM&A(会社売却)やIPO(株式上場)、あるいは円滑な事業承継を考える上で、高い企業価値は極めて有利に働きます。
増加した利益から得られる配当金も、経済的な自由度を高めてくれるでしょう。
メリット2:社会的信用の獲得と影響力の拡大 – ビジネスを有利に進める力
「売上高100億円」という実績は、強力な「信用力」となります。
金融機関はより好意的に融資を検討するようになり、有利な条件での資金調達が可能になります。
大手企業を含む取引先からの信頼も厚くなり、より大規模で有利な取引に繋がる可能性が高まります。
サプライヤーとの関係においても、価格交渉力を持つことができるでしょう。
さらに、社長個人の社会的ステータスも向上します。地域社会や業界団体での発言力が増し、リーダーシップを発揮する機会が増えるでしょう。
時には、政策提言など、より大きな舞台で活躍する道も開けるかもしれません。
この高まった信用力と影響力は、ビジネスをさらに有利に進めるための強力な武器となります。
メリット3:経営者としての達成感と自己実現 – 挑戦者だけが味わえる醍醐味
100億円という高い壁を乗り越える過程は、決して平坦な道のりではありません。
幾多の困難、予期せぬトラブル、そして眠れない夜もあるでしょう。
しかし、それらを乗り越え、社員と共に目標を達成した瞬間の達成感は、何物にも代えがたいものです。
それは、自身の経営判断、リーダーシップ、そして社員とのチームワークが正しかったことの証明であり、経営者としての大きな自信と誇りを与えてくれます。
また、企業の成長ステージが上がるにつれて、経営者に求められる能力も高度化・複雑化します。
組織マネジメント、財務戦略、M&A、グローバル展開など、新たな課題に挑戦し続ける中で、経営者としての視野は広がり、スキルは飛躍的に向上します。
この自己成長の実感こそが、経営という仕事の醍醐味であり、自己実現に繋がるのです。
メリット4:より大きな社会貢献と魅力的な環境の創出 – 次世代へのレガシー
企業規模が拡大すれば、より多くの雇用を創出し、地域経済の活性化に貢献することができます。
従業員の給与水準や福利厚生を向上させ、社員とその家族の生活を豊かにすることも可能になるでしょう。
自社の事業を通じて、環境問題や社会課題の解決に貢献することも、より大きなスケールで実現できるようになります。
「社会の公器」として、より大きな責任を果たすことができるようになるのです。
また、成長し、明確なビジョンと魅力的な事業を持つ企業には、自然と優秀な人材が集まってきます。
「この会社で働きたい」「この社長のもとで成長したい」と思われるような、活気ある魅力的な職場環境を創り出すことは、社長自身の喜びであり、会社の持続的な成長の基盤となります。
メリット5:経営の安定性と新たな挑戦への扉 – 持続可能な成長のために
売上規模が拡大し、利益体質が強化されると、経営の安定性は格段に増します。
特定の取引先や事業への依存度を下げることができ、景気変動や外部環境の変化に対する抵抗力が高まります。
潤沢な内部留保やキャッシュフローは、不測の事態に備えるだけでなく、次なる成長への投資原資となります。
そして、この安定した経営基盤と豊富な経営資源があるからこそ、社長自身が本当に実現したかった新規事業への挑戦や、大胆な研究開発投資、戦略的なM&Aなど、より大きなスケールでのチャレンジが可能になります。
リスクを取る勇気と、それを支える財務基盤が、企業の持続的な成長と、社長自身の夢の実現を後押しするのです。
もちろん、これらのメリットを享受するためには、社長自身が強い覚悟を持ち、リーダーシップを発揮し続ける必要があります。
しかし、その先にある大きな果実を考えれば、挑戦する価値は十分にあると言えるでしょう。
100億円企業へのロードマップ:中小製造業が実行すべき5大戦略
では、具体的に「100億円企業」という目標を達成するために、中小製造業は何を実行すべきなのでしょうか?
ここでは、そのための具体的な戦略を5つの柱に分けて解説します。これらは独立したものではなく、相互に関連し合いながら、企業の成長を加速させるエンジンとなります。
戦略1:徹底的な生産性向上とDXによる「稼ぐ力」の最大化
製造業の基本は、いかに効率よく、高品質な製品を作り出すか、すなわち「生産性」です。
特に、人手不足とコスト高が常態化する現代において、生産性の向上なくして企業の成長はあり得ません。そして、その鍵を握るのが(デジタル・トランスフォーメーション)です。
- なぜ生産性向上が不可欠か?
- コスト削減: 無駄な工程、時間、資源を徹底的に排除し、製造原価を低減します。これは利益率の向上に直結します。
- リードタイム短縮: 生産プロセスを効率化し、顧客への納品スピードを向上させることで、顧客満足度を高め、競争優位性を確立します。
- 品質向上: データに基づいた品質管理や、自動化によるヒューマンエラーの削減により、不良率を低減し、製品の信頼性を高めます。
- 従業員満足度向上: 労働時間短縮や、付加価値の高い業務へのシフトにより、従業員の負担を軽減し、働きがいを高めます。
- スマートファクトリー化の具体像:IoT、AI、データ活用
- IoTによる「見える化」: 生産ラインの各工程にセンサーを取り付け、稼働状況、生産数、品質データなどをリアルタイムに収集・可視化します。これにより、どこにボトルネックがあるのか、何が原因で不良が発生しているのかを正確に把握できます。
- AIによる「最適化・自動化」: 収集したデータをAIが分析し、最適な生産計画の立案、設備パラメータの自動調整、品質検査の自動化、設備の故障予兆検知などを実現します。
- データに基づいた改善サイクル: 見える化されたデータとAIによる分析結果に基づき、継続的な改善活動(PDCAサイクル)を回していくことで、生産性は飛躍的に向上します。
- 事例:A社の取り組み
■ 部品加工業A社は、プレス工程にセンサーとカメラを導入し、リアルタイムで稼働状況と製品画像を監視。AIが微細なキズや変形を検知し、不良品の流出を未然に防ぐとともに、不良発生の原因となる金型の摩耗やプレス圧の異常を早期に特定。これにより、歩留まりが向上し、年間数千万円のコスト削減を実現しました。
- ロボット・自動化導入のポイント
- 導入効果の明確化: どの工程に、どのような目的でロボットを導入するのか(省人化、品質安定化、危険作業回避など)を明確にし、費用対効果を慎重に検討します。
- 段階的な導入: 最初から大規模な自動化を目指すのではなく、効果の見込める工程からスモールスタートし、ノウハウを蓄積しながら範囲を拡大していくのが現実的です。
- 人材の再配置と育成: ロボットに代替された人材を、より付加価値の高い業務(ロボットの操作・保守、生産管理、改善活動など)へシフトさせるための教育・研修が不可欠です。
- 基幹システム(ERP)導入による全体最適化
- 多くの企業では、販売、生産、在庫、購買、会計などの情報が部門ごとに分断され、Excelなどで個別に管理されています。これでは、正確な情報をリアルタイムに把握できず、迅速な意思決定の妨げとなります。
- ERP(Enterprise Resource Planning)を導入し、これらの情報を一元管理することで、部門間の連携がスムーズになり、経営状況の正確な把握、在庫の最適化、リードタイムの短縮などが可能になります。100億円企業を目指す上では、必須の経営インフラと言えるでしょう。
- DX推進体制の構築
- DXは、単なるITツールの導入ではありません。経営トップの強いコミットメントのもと、全社的な取り組みとして推進する必要があります。DX推進担当部署の設置や、外部専門家の活用も有効です。
- デジタル技術を使いこなせる人材の育成・確保も急務です。既存社員向けのリスキリングや、デジタルネイティブな若手人材の採用を積極的に行いましょう。
- 補助金の活用
- これらの設備投資やシステム導入には多額の費用がかかりますが、「中小企業成長加速化補助金」をはじめ、IT導入補助金、ものづくり補助金など、国や自治体の様々な支援策を活用することで、負担を大幅に軽減できます。「100億企業成長ポータル」などで最新情報をチェックし、積極的に活用しましょう。
戦略2:高付加価値化と新事業展開による「独自性」の確立
生産性向上によって「稼ぐ力」の土台を固めた上で、次に取り組むべきは、他社には真似できない「独自性」を確立し、収益性をさらに高めることです。
価格競争から脱却し、持続的な成長を実現するためには、高付加価値化と新事業への挑戦が不可欠です。
- 下請け構造からの脱却の必要性
- 特定の発注元に依存する下請け構造は、景気変動や発注元の都合に左右されやすく、価格決定権も持ちにくいため、利益率が低迷しがちです。自社の技術やノウハウを活かし、主体的に市場を開拓していく姿勢が求められます。
- 研究開発(R&D)への戦略的投資
- 自社のコア技術をさらに深化させ、磨き上げることはもちろん、将来の市場ニーズを見据えた新技術・新素材の開発に積極的に投資します。
- 自社単独での開発が難しい場合は、大学や公設試験研究機関との共同研究(産学官連携)や、異業種企業との連携も有効な手段です。
- 顧客インサイトに基づくソリューション提案(モノ売りからコト売りへ)
- 顧客が本当に求めているのは、単なる「モノ」ではなく、それによって得られる「価値」や「課題解決」です。顧客のビジネスや潜在的なニーズを深く理解し、製品だけでなく、コンサルティング、メンテナンス、運用支援などを組み合わせた「ソリューション」として提供することで、付加価値を高めることができます。
- サービス化(サービタイゼーション)の可能性
- 製造業でありながら、サービス領域での収益を拡大する取り組みです。例えば、自社製品の稼働状況を遠隔監視し、予兆保全サービスを提供する、消耗品の自動補充サービスを行う、顧客の生産プロセス改善を支援するコンサルティングを提供する、などが考えられます。安定的な収益源(ストック収益)を確保することにも繋がります。
- 異業種連携によるオープンイノベーション
- 自社の技術やノウハウと、他業種のアイデアや技術、販路などを組み合わせることで、単独では生み出せなかった革新的な製品やサービス、ビジネスモデルを創出できる可能性があります。積極的に外部との交流を図り、連携の機会を探りましょう。
- 知財戦略の重要性
- 独自技術や開発した製品、ブランドなどを特許権や商標権で適切に保護することは、模倣を防ぎ、競争優位性を維持するために不可欠です。また、保有する知的財産をライセンス供与するなど、新たな収益源とすることも可能です。知財戦略を経営戦略の一部として位置づけ、専門家(弁理士など)の支援も活用しましょう。
戦略3:国内外への販路拡大による「成長機会」の獲得
どれだけ優れた製品や技術を持っていても、それを買ってくれる顧客がいなければ、売上は伸びません。
100億円という目標を達成するためには、既存の販路に安住することなく、国内外の新たな市場へと積極的に打って出る必要があります。
- 国内市場の再定義
- ニッチトップ戦略: 大手が参入しにくい、特定の技術や用途に特化したニッチ市場で圧倒的なシェアを獲得し、高い利益率を確保します。
- 大手企業との共創: 単なる下請けではなく、対等なパートナーとして、大手企業と共同で製品開発や市場開拓を行うことで、新たな成長機会を掴みます。
- 新たな顧客層の開拓: これまで取引のなかった業界や、最終消費者(BtoC)への直接販売なども視野に入れ、新たな顧客層を開拓します。
- 海外展開の必要性とステップ
- 国内市場が縮小傾向にある中で、成長著しい海外市場、特にアジアなどの新興国市場は大きな魅力です。
- ステップ1:徹底した市場調査: どの国の、どの市場に、どのようなニーズがあるのかを綿密に調査します。現地の法規制、商習慣、競合状況なども把握が必要です。JETROなどの支援機関を活用するのも有効です。
- ステップ2:参入戦略の策定: 直接輸出、現地代理店との契約、現地法人の設立、現地企業との合弁など、自社の体力やリスク許容度に応じた最適な参入形態を選択します。
- ステップ3:現地化(ローカライズ): 製品仕様や価格設定、マーケティング手法などを現地のニーズや文化に合わせて調整します。
- ステップ4:リスク管理: 為替変動リスク、カントリーリスク、契約トラブルなど、海外展開特有のリスクを想定し、対策を講じておく必要があります。
- デジタルマーケティングと営業DX
- サイトの多言語化・最適化: 海外からのアクセスを想定し、英語はもちろん、ターゲット市場の言語に対応したWebサイトを構築し、SEO対策を施します。製品情報や技術情報を分かりやすく掲載し、問い合わせに繋がりやすい導線を設計します。
- オンライン展示会・商談の活用: コロナ禍を経て、オンラインでの展示会や商談が一般化しました。時間や場所の制約なく、国内外の潜在顧客にアプローチできる有効な手段です。
- CRM/SFA: 顧客情報や商談履歴を一元管理し、営業活動を効率化・可視化します。メールマーケティングやWeb広告なども活用し、リード獲得から受注までのプロセスを最適化します。
- グローバル人材の育成と獲得
- 語学力はもちろん、異文化理解力や交渉力を持った人材が不可欠です。社内での育成プログラムの実施や、外部からの採用を積極的に行いましょう。海外駐在経験者や外国人材の活用も有効です。
戦略4:GX(グリーン・トランスフォーメーション)による「持続可能性」の追求
近年、脱炭素化や環境保全への取り組みは、単なる社会貢献活動ではなく、企業の競争力や持続可能性を左右する重要な経営課題となっています。
GX(グリーン・トランスフォーメーション)への対応は、コスト増や規制強化といった側面だけでなく、新たな事業機会や企業価値向上に繋がる可能性を秘めています。
- なぜGXが成長戦略になるのか?
- 市場・顧客からの要請: 環境意識の高い顧客や、サプライチェーン全体での脱炭素化を求める大手企業が増加しており、対応できない企業は取引から排除されるリスクがあります。
- コスト削減: 省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの活用は、エネルギーコストの削減に直結します。
- 企業価値向上: 環境への貢献は、企業のブランドイメージを高め、ESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視する投資)を呼び込む要因となります。
- 新たな事業機会: 環境配慮型製品や、省エネ・再エネ関連技術の開発は、新たな市場を切り拓くチャンスとなります。
- 省エネ・再エネ導入の具体策
- 製造プロセスの見直し: エネルギー消費の多い工程を特定し、改善策を検討します(例:熱効率の改善、排熱利用)。
- 高効率設備への更新: LED照明、高効率モーター、インバータ制御の導入など、エネルギー効率の高い設備へ計画的に更新します。
- 再生可能エネルギーの導入: 工場の屋根などを活用した自家消費型太陽光発電システムの導入は、電力コスト削減とCO2排出量削減に貢献します。補助金制度も活用できます。
- サプライチェーン全体での環境負荷低減
- 自社の排出量(Scope1, 2)だけでなく、原材料調達から製品の使用・廃棄に至るまでのサプライチェーン全体の排出量(Scope3)の把握と削減が求められるようになっています。サプライヤーと協力し、環境負荷の少ない原材料の調達や、輸送効率の改善などに取り組みます。
- 環境配慮型製品・技術の開発
- リサイクル可能な素材の使用、製品の長寿命化、軽量化による輸送エネルギー削減など、製品ライフサイクル全体での環境負荷を低減する設計・開発を進めます。これは、新たな競争優位性となり得ます。
- 情報開示とコミュニケーション
- 自社のGXへの取り組み状況や成果を、Webサイトや統合報告書などで積極的に情報開示し、顧客、投資家、地域社会などのステークホルダーとのコミュニケーションを図ることが重要です。
戦略5:成長を支える経営基盤の強化
上記の4つの戦略を力強く推進し、100億円という規模の企業を運営していくためには、それにふさわしい強固な経営基盤が不可欠です。
組織、財務、人材、そして将来を見据えた備えが、持続的な成長を支えます。
- 100億企業にふさわしい組織体制
- 社長一人が全てを把握し、指示するトップダウン型の経営では限界があります。部門長などへの権限移譲を進め、各部門が自律的に意思決定し、行動できる組織を目指します。
- 部門間の壁を取り払い、スムーズな情報共有と連携を促進する仕組みが必要です(例:部門横断プロジェクト、定期的な情報共有会議)。
- 企業の成長に伴い、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化も重要になります。取締役会の機能強化、コンプライアンス体制の整備などが求められます。
- 多様な資金調達戦略
- 成長投資には資金が不可欠です。従来の金融機関からの融資に加え、補助金・助成金の活用、日本政策金融公庫などの公的融資、さらには成長資金としてベンチャーキャピタル(VC)やプライベートエクイティ(PE)ファンドからの出資受け入れ、ファクタリング(売掛債権の早期現金化)など、多様な資金調達手段を検討し、最適な組み合わせ(デット・エクイティミックス)を構築します。
- 戦略的人材マネジメント
- 企業の成長戦略を実現できる人材の採用、育成、評価、定着が極めて重要です。
- 採用: 企業のビジョンや成長性に共感し、活躍してくれるポテンシャルのある人材を、多様なチャネル(新卒、中途、リファラル、ダイレクトリクルーティングなど)を通じて獲得します。
- 育成: OJTに加え、階層別研修、専門スキル研修、DX人材育成プログラムなどを体系的に実施し、社員の能力開発を支援します。次世代の経営幹部候補の育成も計画的に行います。
- 評価・処遇: 成果や貢献度に応じた公正な評価制度と、魅力的な報酬・福利厚生制度を整備し、社員のモチベーションを高めます。
- 定着: 働きがいのある企業文化の醸成、キャリアパスの提示、働きやすい環境(柔軟な勤務体系など)の整備により、優秀な人材の流出を防ぎます。
- M&Aによる成長加速
- 自社だけでは時間のかかる技術開発、販路開拓、人材確保などを、M&A(企業の合併・買収)によって短期間で実現できる可能性があります。事業規模の拡大や、隣接分野への進出、海外展開の足掛かりとしても有効な戦略です。
- ただし、M&Aにはリスクも伴います。事前の慎重なデューデリジェンス(企業調査)、買収後の統合プロセス(PMI)の重要性を理解し、専門家の支援も得ながら進める必要があります。
- 事業承継の計画的準備
- 100億円企業という大きな目標を達成したとしても、その先の持続的な成長のためには、円滑な事業承継が不可欠です。後継者の育成(親族、役員・従業員、外部招聘)、株式の承継対策(税金対策含む)、経営権の移譲プロセスなどを、早期から計画的に準備しておく必要があります。これは、社長が安心して経営に集中するためにも重要な課題です。
これらの5つの戦略を、自社の状況に合わせてカスタマイズし、優先順位をつけ、着実に実行していくことが、100億円企業への道を切り拓く鍵となります
100億円企業化を成功させるためのマインドセットと注意点
戦略を実行し、目標を達成するためには、経営者自身のマインドセット、そして組織全体で共有すべき価値観が極めて重要になります。
- 社長自身の強いコミットメントと覚悟: 「絶対に100億円企業を実現する」という社長自身の揺るぎない決意と覚悟が、全ての原動力となります。困難に直面しても諦めず、先頭に立って社員を鼓舞し続けるリーダーシップが求められます。
- 明確なビジョンと全社への浸透: なぜ100億円を目指すのか、その先にどのような未来を描いているのか。明確なビジョンを策定し、それを社員一人ひとりに分かりやすく伝え、共感を呼ぶことが重要です。ビジョンが共有されてこそ、組織は一枚岩となって目標に向かうことができます。
- 失敗を恐れないチャレンジ精神と学習する組織文化: 新たな挑戦に失敗はつきものです。失敗を責めるのではなく、失敗から学び、次に活かす「学習する組織」の文化を醸成することが、イノベーションを生み出す土壌となります。トライ&エラーを奨励し、挑戦する社員を評価する姿勢が大切です。
- 変化への柔軟な対応力: 経営環境は常に変化します。策定した計画に固執するのではなく、市場の変化や予期せぬ事態に柔軟に対応し、戦略を修正していく俊敏性が求められます。常に外部環境にアンテナを張り、情報を収集し続けることが重要です。
- 外部リソース(専門家、コンサルタント)の積極的な活用: 全てを自社だけでやろうとする必要はありません。自社にないノウハウや知見を持つ外部の専門家(弁護士、弁理士、税理士、ITベンダーなど)や、経営戦略の策定から実行までを支援する経営コンサルタントなどを積極的に活用し、成功の確率を高めましょう。
- 短期的な成果と長期的な視点のバランス: 100億円への道のりは長期間にわたります。短期的な売上や利益目標を達成することも重要ですが、そればかりにとらわれず、人材育成や研究開発といった、長期的な成長基盤への投資も怠らないバランス感覚が求められます。
おわりに:未来を切り拓くために
「100億円企業」への挑戦。それは、単に売上という数字を追い求めることではありません。
それは、自社の持つ潜在能力を最大限に引き出し、厳しい経営環境を乗り越え、持続的な成長を遂げるための、壮大な企業変革のプロセスです。
その挑戦を通じて、貴社は地域社会に貢献し、従業員の幸福を実現し、そして何よりも、社長自身の経営者としての夢を実現することができるでしょう。
現状維持は、もはや選択肢ではありません。未来は、自らの手で切り拓くものです。
今こそ、勇気を持って、その第一歩を踏み出す時ではないでしょうか。
船井総合研究所「100億企業化プロジェクト」について
とはいえ、
「何から手をつければ良いのか分からない」
「具体的な戦略の立て方が難しい」
「実行段階で壁にぶつかってしまう」
といったお悩みをお持ちの経営者の方も多いかと存じます。
私たち船井総合研究所は、創業以来50年以上にわたり、多くの中堅・中小企業の経営支援に携わり、その成長を実現してきた経営コンサルティング会社です。
特に製造業分野においては、豊富な支援実績と専門性の高いコンサルタントを有しております。
この度、まさに「100億円企業」を目指す意欲ある製造業経営者の皆様をご支援するために、「100億企業化プロジェクト」を発足いたしました。
● 船井総合研究所 100億企業化プロジェクトhttps://10billion.funaisoken.co.jp/
このプロジェクトでは、100億円企業達成に向けた全体ロードマップの策定から、DX推進、生産性向上、新規事業開発、販路拡大、組織開発、財務戦略、M&A支援、そして現場レベルでの具体的な業務改善や施策の実行支援まで、企業の成長フェーズに合わせて一貫したコンサルティングサービスをご提供いたします。
私たちの強みは、単なる「計画屋」「分析屋」に留まらないことです。
豊富な成功事例とデータに裏打ちされた実現性の高い戦略をご提案することはもちろん、時には経営者の皆様と共に悩み、汗を流し、現場に入り込んで、改革が実行され、成果が出るまで伴走支援させていただきます。
「100億円企業」という高い頂きを目指す旅は、決して楽ではありませんが、独りで悩む必要はありません。
私たち船井総合研究所が、貴社の羅針盤となり、頼れるパートナーとして、その挑戦を全力でサポートいたします。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずは上記ウェブサイトをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
貴社の未来を共に切り拓けることを、心より楽しみにしております。
関連記事
経産省の提言から考える製造業マスタデータの重要性
https://smart-factory.funaisoken.co.jp/250403-2/
経産省の提言から考える繊維業のDX戦略:JASTIと特定技能制度が導く変革の道筋
https://smart-factory.funaisoken.co.jp/250409-3/





