記事公開日:2025.05.21
最終更新日:2025.05.23
“なぜウチのDXは進まない?ある製造部長、変革への挑戦と突破口 “
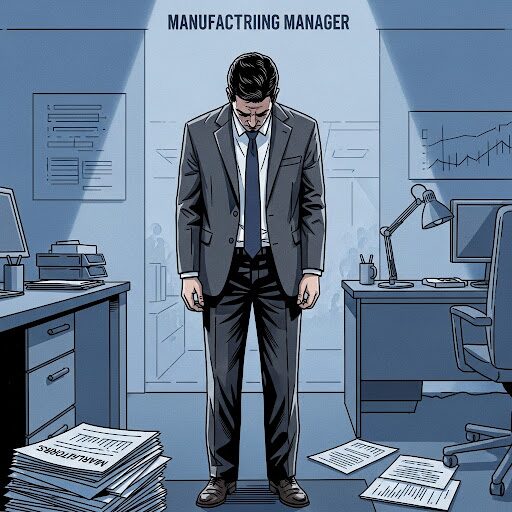
「DXを推進しようと頑張っているのに、なぜかうまくいかない…」。そんな深い悩みを抱える中堅・大手製造業の経営幹部、部門長、中間管理職の皆様に、本コラムは、暗闇の中で一筋の光を見出すような体験を提供します。主人公・田中部長の数々の失敗と、そこから這い上がるまでの苦闘の物語は、皆様ご自身の経験と重なり、深い共感を呼ぶでしょう。そして、彼が「万策尽きた」と感じた後に掴んだブレイクスルーの瞬間は、「うちの会社にも、まだやれることがあるはずだ」という強い勇気を与えてくれます。
このコラムを通じて、DX推進における具体的な障壁とその乗り越え方、社内を巻き込むための現実的なアプローチ、そして何よりも「諦めない心」の重要性を、ストーリーを通して深く理解することができます。読み終えた後には、自社で直面している課題への新たな視点と、明日から試せる具体的なアクションプラン、そして変革への情熱が再燃していることをお約束します。
※この物語はフィクションであり企業名及び登場人物は架空のものです。また、改善効果の数値などを保証するものではありません。
目次
プロローグ:DXの号令、しかし現実は「動かぬ組織」―製造部長の孤独な戦い
株式会社ネクストマニュファクチャリング、製造部長の田中一郎(48歳)の眉間には、ここ数ヶ月、深い皺が刻まれたままだった。会社は、業界でも名を知られた中堅メーカー。経営トップからは「DXを強力に推進し、生産性を飛躍的に向上させよ!」という威勢の良い号令が全社に発せられて久しい。しかし、現実はどうだ。製造現場は、相変わらず熟練工の経験と勘に頼ったオペレーションが続き、紙の帳票が飛び交う。若手は育たず、ベテランは新しい技術に抵抗を示す。生産データは各工程で分断され、リアルタイムでの状況把握など夢のまた夢。これは、決してネクストマニュファクチャリング社だけの問題ではない。私たち船井総合研究所が日々接する多くの中堅・大手製造業が、同様の「DXの壁」の前で立ち尽くしている光景を目の当たりにする。
「またDX推進会議か…もう何度目だ」。田中は、重い足取りで会議室へ向かう。役員たちが理想論をぶち上げ、各部門長が自部門の立場を主張するばかりで、具体的なアクションプランは何も決まらない。情報システム部門は「既存システムとの整合性が…」と及び腰、営業部門は「そんなことより目の前の数字だ」と非協力的、そして製造現場からは「これ以上、負担を増やさないでくれ」という悲鳴が聞こえてくる。多くの場合、その根本には、DXを「自分事」として捉える当事者意識の欠如と、変化への漠然とした不安が存在する。
田中自身、DXの必要性は痛いほど感じていた。競合他社はスマートファクトリー化を進め、コスト競争力も品質も格段に向上させている。このままでは、ネクストマニュファクチャリングが市場で生き残っていくことは難しいだろう。しかし、この巨大で、部門間の壁が厚く、変化を嫌う組織を、一体どうすれば動かせるというのか。自分は、所詮、巨大組織の一つの歯車に過ぎないのではないか。そんな無力感が、彼を苛んでいた。「何かを変えなければ…でも、何から?誰と?どうやって…?」。その答えの見えない問いが、田中の頭の中で堂々巡りを繰り返すばかりだった。この「停滞」こそが、企業にとって最も恐れるべき状況であり、状況を打破するためには、まずDX推進をリードする「核となる人材」が、正しい知識と強い意志を持つことが不可欠となるのである。
第一章:暗中模索の日々、DXの迷宮で深まる製造部長の「無力感」
トップからのDX推進の号令を受け、製造部長である田中一郎は、まず自力で何とかしようと動き出した。毎晩遅くまで専門書を読み漁り、インターネットで国内外の成功事例を検索する日々。しかし、情報が多すぎて、何が自社にとって本当に有効なのか、見極めることができない。「スマートファクトリー」「IoTプラットフォーム」「デジタルツイン」…輝かしいキーワードが躍る一方で、具体的な導入プロセスや費用対効果は曖昧なものが多かった。
彼はまず、製造現場の状況を少しでも「見える化」しようと、一部の生産ラインに安価なセンサーを取り付け、データを収集することを情報システム部門に提案した。しかし、「既存の生産管理システムとの連携は?」「収集したデータのセキュリティは誰が担保するのか?」「そもそも、そのデータを見てどうするつもりなのか?」矢継ぎ早の質問と、暗に「余計な仕事を増やすな」と言わんばかりの非協力的な態度に、田中の最初の試みはあっけなく頓挫した。
次に、現場の若手社員数名を集め、自主的な「DX勉強会」を立ち上げようとした。彼らに最新技術の情報を共有し、ボトムアップでの改善意識を高めようという狙いだ。しかし、参加者は数えるほど。ベテラン社員からは「そんな暇があったら、目の前の仕事を片付けろ」と冷ややかな視線を浴び、勉強会も数回で自然消滅してしまった。「DXへの意識が低すぎる…どうすれば彼らの心に火をつけられるんだ」。
諦めきれない田中は、今度は特定の単純作業を自動化しようと、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)ツールの無料版をダウンロードし、独学でプログラミングを試みた。数週間かけてようやく一つの帳票作成業務を自動化できたものの、その効果は微々たるもの。他の業務に応用しようにも、専門知識の壁と時間の制約が大きく立ちはだかった。何よりも、この小さな成功を社内にアピールしても、「田中部長が個人的に頑張っているだけだろう」と、全社的な動きには全く繋がらなかったのだ。
そんな中、業界紙で船井総合研究所主催の「製造業幹部社員向けDX推進研修」の広告を目にする。「DX『何から始めるか』を解決する実践手法」というキャッチコピーに一瞬心惹かれたものの、「どうせまた総論ばかりだろう」「参加費用も安くないし、今の自分が行っても意味があるのか…」と、パンフレットを机の引き出しの奥にしまい込んでしまった。自力での挑戦はことごとく失敗に終わり、社内での田中は「口先ばかりで成果を出せないDX担当」と揶揄され始めているのではないか、そんな被害妄想にさえ駆られるようになっていた。彼の心には、深い無力感と焦燥感が、暗い影のように広がっていた。
第二章:進まぬ改革、迫る危機…
第二章:進まぬ改革、迫る危機…製造部長、最後の望み
田中一郎がDXの迷宮で出口を見出せずに喘いでいる間にも、ネクストマニュファクチャリング社を取り巻く経営環境は、刻一刻と厳しさを増していた。主力製品の市場では、海外の競合メーカーが最新のデジタル技術を駆使した低コスト・高品質な製品でシェアを拡大。ネクスト社の受注は目に見えて減少し、工場の稼働率は低下の一途を辿っていた。営業部門からは、「競合はリアルタイムで在庫状況を把握し、即納体制を築いている。うちは納期回答すら数日かかる。これでは戦えない!」という悲痛な叫びが聞こえてくる。
社長は、役員会議のたびにDXの遅れを厳しく詰問するが、具体的な指示はなく、責任のなすりつけ合いに終始するばかり。田中が何度か提案した改善策も、「費用対効果が見えない」「前例がない」「関係部署の合意が得られていない」といった理由で、ことごとく却下された。「一体、どうすればこの会社は変われるんだ…」。田中は、巨大な組織の中で、自分がただ一人、空回りしているような感覚に陥っていた。彼のDX推進への情熱も、度重なる失敗と社内の無理解によって、もはや消えかかろうとしていた。自身のキャリアに対する不安も頭をよぎる。「このままでは、自分もこの会社と共に沈んでいくしかないのか…」。
そんなある晩、疲れ果てて帰宅した田中は、ふと数ヶ月前に机の引き出しにしまい込んだ、あの船井総研のDX研修のパンフレットを思い出した。藁にもすがる思いとは、まさにこのことだった。彼は、ほとんど無意識のうちにパンフレットを引っ張り出し、その内容を改めて読み返した。「同じ課題を抱える全国の製造業幹部が集結」「具体的な成功事例を多数紹介」「自社のDX戦略を立案」。その言葉の一つ一つが、今の彼には、まるで暗闇の中で遠くに見える灯台の光のように感じられた。「もう、これしかないのかもしれない…」。
翌日、田中は社長に研修への参加を直訴した。社長は、田中の憔悴しきった表情と、それでもなお諦めきれないという切実な思いを感じ取ったのか、「…分かった。田中君、これが最後のチャンスかもしれないぞ。しっかりと学んできてくれ」と、重々しく許可を出した。研修への参加は、彼にとって、まさに崖っぷちでの最後の決断だった。もし、この研修でも何も得られなければ、自分はこの会社を去るしかないだろう。そんな悲壮な覚悟を胸に、田中は研修会場へと向かった。それは、彼にとって、長く苦しいトンネルの出口を求める、最後の挑戦の始まりだった。
第三章:「これだったのか!」苦闘の経験が繋がった瞬間、見えた光明と仲間たち
重い足取りで足を踏み入れた「製造業幹部社員向けDX推進研修」の会場。田中一郎は、正直なところ、大きな期待を抱いてはいなかった。これまでの数々の失敗経験が、彼を懐疑的にさせていたのだ。しかし、研修が始まると、その雰囲気は彼の予想を良い意味で裏切るものだった。講師を務める船井総研のコンサルタントは、決して理想論や抽象論を語るのではなく、中小企業から大企業まで、数多くの製造業の現場で実際にDXを推進してきた経験に基づき、成功のポイントと陥りやすい罠を、生々しい事例と共に解説した。その言葉の一つ一つが、田中がこれまで自力で格闘し、そして打ちのめされてきた壁と、不思議なほど符合した。
「なぜ、うちの会社のDXは進まなかったのか…」。その答えが、パズルのピースがはまるように、次々と明らかになっていくのを感じた。トップのコミットメントの重要性、部門横断的な推進体制の必要性、スモールスタートと成功体験の共有、そして何よりも、DXを「技術導入」ではなく「企業変革」として捉える視点。どれも、彼が見落としていた、あるいは軽視していたことばかりだった。「これだったのか…!」。頭をハンマーで殴られたような衝撃と同時に、目の前の霧が晴れていくような感覚を覚えた。
特に大きな気づきを与えてくれたのは、グループワークだった。同じように社内の壁やDX推進の難しさに直面している他社の幹部たちと、自社の課題や失敗談を赤裸々に語り合う中で、田中は「悩んでいるのは自分だけではない」という安堵感と、彼らの真摯な取り組みから学ぶ多くのヒントを得た。精密部品メーカーの生産技術部長、佐藤氏(仮名)は、トップの理解が得られない中で、いかにして現場の若手を巻き込み、ボトムアップで小さな改善を積み重ね、それを経営層に認めさせていったか、その具体的なプロセスを共有してくれた。また、ある化学メーカーの情報システム部長は、既存システムとのしがらみの中で、いかにしてクラウド技術を段階的に導入し、データ活用の基盤を築いていったか、その苦労と工夫を語ってくれた。彼らの話は、田中にとって、まさに生きた教科書だった。
研修の最終日、田中はグループの仲間たちと協力し、自社ネクストマニュファクチャリングの「製造部門DX化 再挑戦プラン」を策定した。それは、以前彼が一人で描いたものとは全く異なり、明確な目標設定、具体的なアクションステップ、関係部署との連携方法、そして何よりも「なぜそれをやるのか」というDXの目的意識が貫かれた、地に足のついた計画となっていた。発表を終えた田中に対し、講師からは「田中さん、この二日間で素晴らしい変化を遂げられましたね。そのプランなら、必ずや御社に新しい風を吹き込むでしょう。私たちも全力でサポートします」という力強い言葉が送られた。田中は、久しぶりに心の底から湧き上がるような熱い情熱と、確かな自信を取り戻していた。暗く長いトンネルの先に、ようやく一筋の光明が見えた瞬間だった。
第四章:「仲間」と掴んだ最初の成功、DXの火種が全社を照らし出す
研修で得た新たな知識、戦略、そして何よりも「仲間」という強力な武器を手にした田中一郎は、別人のように生まれ変わって会社に戻った。彼の目には、以前のような迷いや無力感はなく、DX推進への確固たる決意がみなぎっていた。
まず彼が取り組んだのは、研修で策定した「製造部門DX化 再挑戦プラン」を、社長をはじめとする経営トップに改めて説明し、その承認と全面的な協力を取り付けることだった。以前とは異なり、彼の説明は具体的で、説得力に満ちていた。他社の成功事例や、費用対効果の明確なシミュレーション、そして何よりも彼の本気度が伝わり、社長は「田中君、君に任せる。必要なサポートは惜しまない」と、力強く約束してくれた。
次に行ったのは、社内の「仲間づくり」だった。彼は、研修で学んだチェンジマネジメントの手法を参考に、まず各部門にDXの必要性を丁寧に説いて回り、それぞれの部門が抱える課題解決にDXがどう貢献できるかを具体的に示した。そして、以前は孤立していた若手社員たちや、新しい技術に興味を持つ中堅社員たちに積極的に声をかけ、「部門横断DX推進ワーキンググループ」を立ち上げたのだ。情報システム部門に対しても、頭ごなしに協力を求めるのではなく、彼らの専門知識を尊重し、共に新しいシステム基盤を設計していくパートナーとしての関係構築を試みた。
最初の具体的な取り組みとして、田中は再び製造現場の「見える化」と「不良品削減」に挑んだ。しかし、今回は以前の失敗を踏まえ、トップダウンの押し付けではなく、現場の田中リーダー(熟練工)や若手社員たちと徹底的に話し合い、彼らの意見を最大限に尊重しながら進めた。TechSeekers社の簡易AI検査キットも、現場の意見を取り入れてカスタマイズし、まずは試験的に導入。その結果、数週間で特定のラインの不良率が目に見えて低下し、その成果がリアルタイムで工場内の大型モニターに表示されると、現場の空気は一変した。「本当に効果があるじゃないか!」「俺たちの仕事が楽になったぞ!」。
この「最初の小さな成功」を、田中は徹底的に社内に広報した。社内報で特集記事を組み、成功事例発表会を開催し、社長からも直接、関係者への労いの言葉をかけてもらった。すると、今まで懐疑的だった他部門からも、「うちの部門でも何かできないか?」という相談が舞い込むようになった。営業部門は顧客情報管理のDX化を、設計部門は3D CADとシミュレーションの連携強化を、それぞれ自主的に検討し始めたのだ。
かつては田中一人の孤軍奮闘だったDX推進の取り組みは、いつしか多くの社員を巻き込み、部門の壁を越えた「全社的なうねり」へと変わり始めていた。それは、まだ小さな火種かもしれない。しかし、確実にネクストマニュファクチャリングという巨大な組織を、内側から照らし出し、温め始めていた。田中は、この変化の兆しに、確かな手応えを感じていた。
第五章:エピローグ:そして変革は加速する、一人の幹部が見据える「会社の新たな未来図」
田中一郎が率いる「部門横断DX推進ワーキンググループ」が次々と小さな成功を積み重ねるにつれ、ネクストマニュファクチャリング社内のDXへの機運は、かつてないほど高まっていた。社長は、この動きを一過性のものに終わらせないため、正式に「全社DX推進本部」を設立し、田中をその本部長に任命した。彼には、大幅な予算と権限が与えられ、より長期的かつ全社的な視点でのDX戦略を策定・実行するミッションが課せられた。
田中は、研修で出会った仲間たちとのネットワークも最大限に活用した。他社の成功事例や失敗事例を共有し、最新技術の情報交換を行い、時には共同で外部の専門家を招いた勉強会を開催するなど、常に新しい知識と刺激を社内に取り込み続けた。
数年後、ネクストマニュファクチャリングは、業界でも注目されるほどの「DX先進企業」へと変貌を遂げていた。製造現場では、AIとIoTが高度に連携し、熟練工の匠の技とデジタル技術が融合した「スマートファクトリー」が現実のものとなっていた。生産性は飛躍的に向上し、不良率は限りなくゼロに近づき、コスト競争力も格段に強化された。営業、設計、開発、そして管理部門に至るまで、DXの波は全社に及び、データに基づいた意思決定と、部門間のシームレスな連携が当たり前の企業文化として根付いていた。
社員たちの働き方も大きく変わった。単純作業から解放され、より創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになった。リモートワークやフレックスタイム制といった柔軟な働き方も浸透し、社員一人ひとりが自律的にキャリアをデザインし、成長を実感できる環境が整った。「この会社で働くことが誇りだ」。そんな声が、社員たちから自然と聞かれるようになった。
田中一郎は、今や常務取締役DX推進本部長として、会社の変革を力強く牽引している。彼は、自社の成功体験を、業界全体の発展に繋げたいという新たな目標を抱き、講演や執筆活動を通じて、その知見を積極的に発信している。
ある日、彼は新入社員たちを前に、自社のDXの軌跡を語っていた。「私たちのDXは、決して平坦な道ではありませんでした。しかし、どんな困難な状況でも、諦めずに仲間を信じ、一歩ずつ前に進み続ければ、必ず道は拓けると信じています。DXとは、単なる技術革新ではありません。それは、人が変わり、組織が変わり、そして未来を創造していく、終わりのない素晴らしい旅なのです」。
彼の言葉を聞く若手社員たちの目は、未来への希望と情熱に輝いていた。ネクストマニュファクチャリングは、一人の幹部の挑戦から始まった静かな革命を経て、今まさに、業界の未来をリードする存在へと、力強く羽ばたこうとしていた。田中一郎が見据える先には、AIやロボットと人間が真に協調し、持続可能で、より豊かな社会を実現する、製造業の新たな未来図が、鮮やかに広がっていた。
【このコラムを読んだ後に取るべき行動】
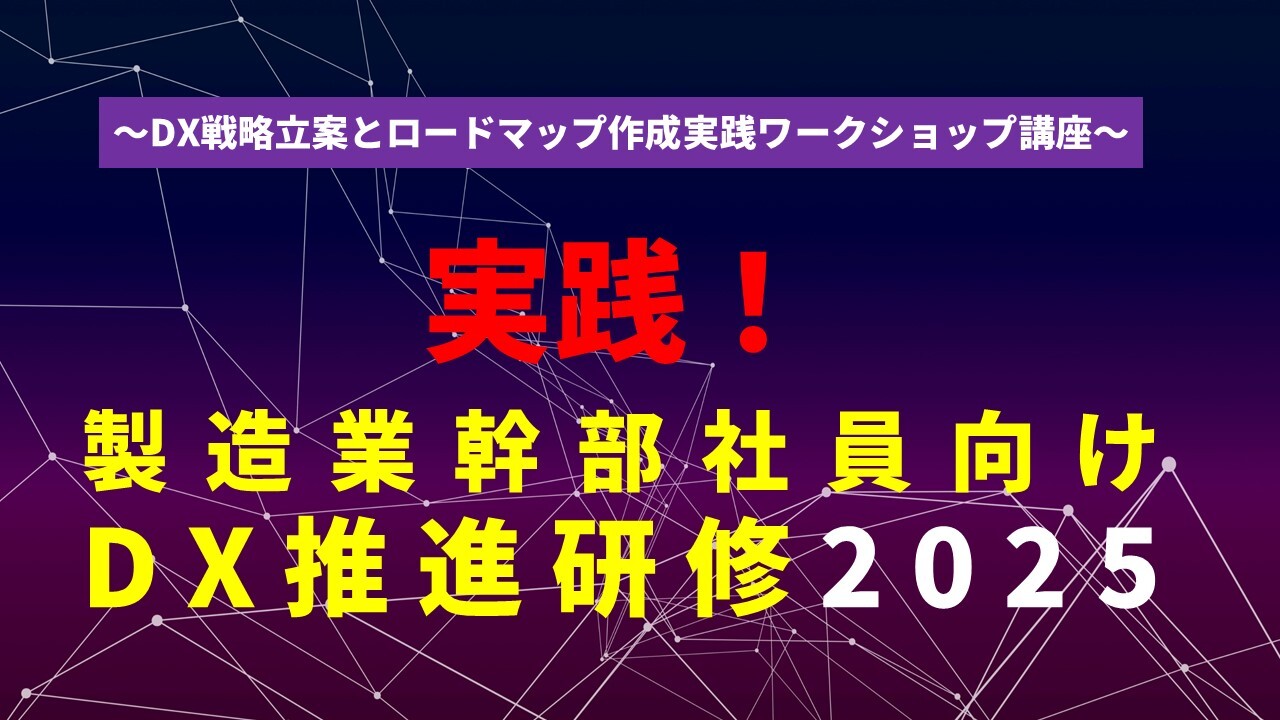
https://www.funaisoken.co.jp/seminar/129681
田中部長が、そしてネクストマニュファクチャリング社が、変革への確かな一歩を踏み出したように、次はあなたが、そして御社が、その扉を開く番です。
本コラムでご紹介した、株式会社ネクストマニュファクチャリングの製造部長、田中一郎氏(仮名)のDX奮闘記は、決して特別な才能を持つヒーローの物語ではありません。それは、多くの中堅・大手企業が直面する「組織の壁」や「変化への抵抗」といった課題に、真正面から向き合い、正しい知識と仲間を得て、諦めずに挑戦を続けた一人のビジネスパーソンのリアルな記録です。
「社内の抵抗が強くて、DXが進まない…」
「最新技術を導入したいが、何から手をつければ…」
「部門間の連携がうまくいかず、全社的な動きにならない…」
もし、御社が、そしてあなたが今、このような悩みを抱え、変革への一歩を踏み出せずにいるのであれば、田中部長がその突破口を見出した**「実践!製造業幹部社員向けDX推進研修2025」**が、必ずやその解決の糸口となるはずです。
この研修は、中堅・大手企業の経営幹部、部門長、そしてDX推進を担う中間管理職の皆様のために特化したプログラムです。
自社の組織構造や企業文化を踏まえた、現実的なDX戦略の立案方法を徹底指導します。
AI、IoT、RPA等の最新技術を、いかに既存システムと連携させ、費用対効果を最大化するか、具体的な事例と共に解説します。
部門間の壁を打破し、全社を巻き込むためのチェンジマネジメント手法、社内調整の秘訣を伝授します。
そして何よりも、同じ課題意識を持つ全国の中堅・大手企業の幹部社員と繋がり、互いに学び合い、支え合える貴重なネットワークを構築できます。
DXは、孤独な戦いではありません。正しい知識、具体的な戦略、そして信頼できる仲間がいれば、必ずや道は拓けます。
セミナー詳細ページをご覧いただき、未来への投資をご検討ください。
▼「実践!製造業幹部社員向けDX推進研修2025」の詳細・お申込みはこちら





