記事公開日:2025.10.15
最終更新日:2025.10.15
「ウチの経営陣はITに疎くて…」と諦める前に。失敗しないシステム導入計画の進め方
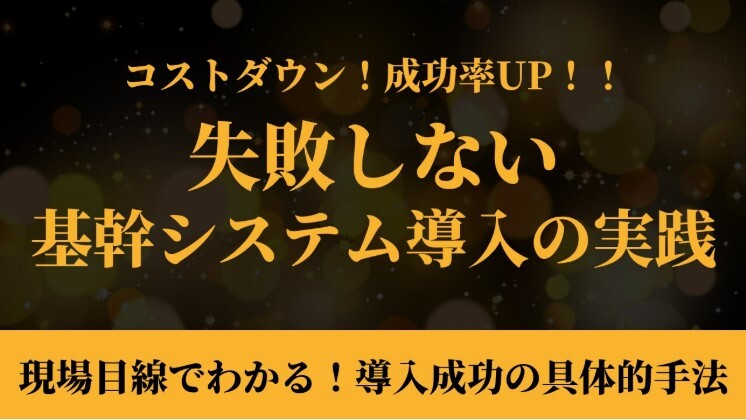
あなたのその悩み、担当者の8割が経験しています。
—————-
「全社的なDXを推進せよ」
経営陣からの号令で、あなたが会社のシステム導入担当者に任命された。
しかし、いざ計画を進めようとすると、こんな壁にぶつかっていませんか?
- IT用語で説明しても、経営会議では「で、儲かるの?」の一言で終わってしまう。
- 現場にヒアリングすれば「今のままで困ってない」「忙しい」と非協
- 結局、あなた一人で業者を探し、機能比較表を作るも、社内の誰からも「自分ごと」として捉えられていない…。
力的。
もし一つでも当てはまるなら、ご安心ください。それはあなたの能力の問題ではありません。
多くの企業が陥る、システム導入計画の「進め方」の典型的な失敗パターンです。
1.その計画、「システム導入」が目的になっていませんか?
経営や現場を巻き込めない根本原因は、実はコミュニケーションの問題以前にあります。それは、多くの導入計画が、知らず知らずのうちに「システムを導入すること」そのものをゴールに設定してしまっている、という構造的な欠陥です。
本来、システムは企業の目的を達成するための「手段」のはず。しかし、プロジェクトが始動した途端、担当者は「どの製品が良いか」「機能は足りるか」「予算内に収まるか」といった「手段の最適化」に思考を奪われてしまいます。
その結果、推進担当者であるあなたは、本来あるべき「事業を変革するチェンジマネージャー」ではなく、単なる「IT製品の評価担当者」になってしまうのです。
「評価担当者」が語る機能の優位性やコストの妥当性は、経営層にとっては「コストセンター(IT部門)の言い分」、現場にとっては「よく分からないツールの押し付け」としか映りません。これでは、計画が「他人事」にされてしまうのも当然の結果と言えるでしょう。
問題の根源は、表面的なコミュニケーションの齟齬ではありません。プロジェクトの目的設定の誤りと、推進者に求められる役割認識の欠如―――これこそが、あなたの計画を停滞させる、より高次の課題なのです。
成功する計画は、2つのロードマップ作成アプローチから生まれる
では、どうすれば良いのか?
答えは、システムの機能比較や業者選定の前に、自社の状況に合わせて「計画の描き方」そのものを戦略的に選択することです。成功する導入計画は、主に以下の2つのアプローチ、またはその組み合わせから生まれます。
パターンA:経営計画連動型ロードマップ(トップダウン・アプローチ)
これは、「会社の未来」を起点に、そこから逆算して「今、導入すべきシステムは何か」を考えるアプローチです。
- 進め方:
まずは、社長や経営幹部が策定した中期経営計画や事業戦略(例:「5年後に海外売上比率を50%にする」「新製品の市場投入サイクルを半分にする」など)を深く理解することから始めます。その上で、「この未来を実現するためには、どのような業務プロセスや情報基盤が必要か?」を定義し、システム導入計画に落とし込んでいきます。 - 担当者の役割:
このアプローチでのあなたの重要な役割は、壮大な経営ビジョンを「現場の言葉に翻訳」することです。経営層の言葉をそのまま現場に伝えても、「自分たちには関係ない遠い未来の話」と捉えられがちです。未来のビジョンが、現場一人ひとりの業務とどう繋がり、どんなメリットがあるのかを具体的に示す「通訳者」となることが求められます。
パターンB:課題解決型ロードマップ(ボトムアップ・アプローチ)
これは、「現場の今の痛み」を起点に、それを解消するための打ち手を積み上げて計画を立てるアプローチです。 - 進め方:
各部署のキーマンと共に、「在庫確認に半日かかっている」「Excelへの二重入力でミスが頻発している」といった、現場で起きている具体的な課題や無駄を徹底的に洗い出します。そして、それらの課題を解決するために「最も効果的なシステムは何か?」をボトムアップで考え、導入計画を構築していきます。 - 担当者の役割:
このアプローチでのあなたの重要な役割は、現場から出てきた個別の課題を「経営の言葉に翻訳」することです。現場の細かな課題は、そのまま経営層に伝えても「それは現場で工夫すれば?」と一蹴されかねません。個別の課題が、会社全体でどれほどの損失(コスト、時間、機会損失)に繋がっているのかを定量的に示し、経営課題として認識させることが求められます。
重要なのは、この両アプローチの「橋渡し」です。 多くの企業では、トップダウンの理想とボトムアップの現実が断絶し、計画が頓挫します。推進担当者であるあなたが、この両者を繋ぐ「翻訳者」となり、全社的な合意を形成することが、成功への唯一の道筋なのです。
3.その計画を「成功の確信」に変える
ここまで、システム導入計画における2つのアプローチと、推進担当者に求められる「翻訳者」としての役割をご紹介しました。
しかし、特に多くの部門が複雑に絡み合う製造業においては、これらを実践する上で特有の難しさが伴います。
- 「未来の経営計画と、現場の複雑な生産管理要件を、どうやって矛盾なく一つの計画にまとめ上げるのか?」
- 「Fit To Standard手法やマイクロリリースといった専門的なアプローチは、トップダウンとボトムアップ、どちらの計画と相性が良いのか?」
- 「そもそも、この2つのアプローチを繋ぐための、具体的なプロジェクト体制や会議体をどう設計すればいいのか?」
こうした専門的かつ実践的な問いへの答えが、プロジェクトの成否を分けます。
もしあなたが、机上の空論ではない、製造業のリアルな現場を知り尽くしたプロフェッショナルの知見や、他社の成功事例を具体的に学びたいとお考えなら、船井総合研究所が主催するこちらのセミナーが、あなたの疑問を解消する最適な機会となるでしょう。
このセミナーでは、我々がお伝えした「計画の進め方」の重要性をさらに深く掘り下げ、基幹システム刷新を成功に導くための具体的な手法論(ベンダー選定、組織体制構築術など)を、余すところなく解説しています。
あなたの「孤独な挑戦」を、「全社一丸のプロジェクト」へ。
その第一歩を、ここから踏み出してみませんか?
コストダウン!成功率UP!!失敗しない基幹システム導入の実践
関連コラム

データドリブンを実現する「考え方」と具体的手法を解説
2021.04.02
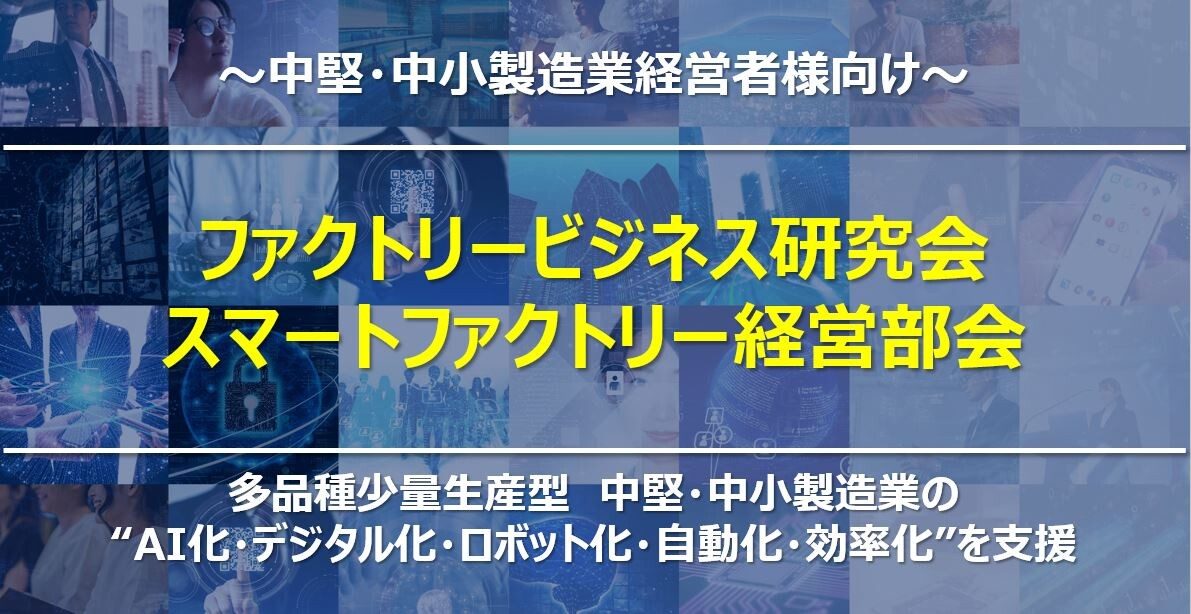
ファクトリービジネス研究会 スマートファクトリー経営部会 4月例会開催のお知らせ
2022.04.07

中堅・中小製造業の画像検査装置導入のコツ ~画像検査はここまで来ている。最新情報~
2023.04.04


