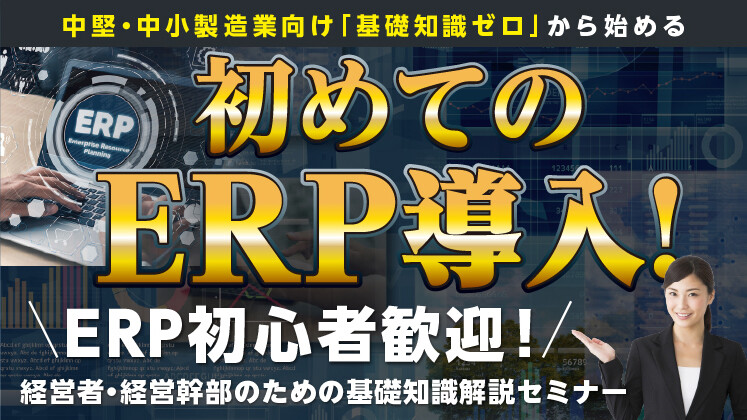記事公開日:2025.11.21
最終更新日:2025.11.21
【セミナー登壇レポート】業務効率を劇的に変える!製造業向け生成AI活用術 – NECA会員限定セミナーより

目次
はじめに:今、製造業に「生成AI」が必要な理由
この度、株式会社船井総合研究所 DXコンサルティング部 リーダーの熊谷俊作が、日本制御機器技術工業会(NECA)様主催の会員限定セミナー「Googleの生成AI『Gemini』セミナー」に講師として登壇しました。
https://www.neca.or.jp/event/13249/
本セミナーは、「日々のルーティン業務に追われ、本来注力すべき仕事に時間を割けていない」「AI活用が必須と言われるが、何から手をつければ良いかわからない」といった製造業の皆様の課題に対し、最新の生成AI「Gemini」を活用した具体的な解決策を実践的に学ぶことを目的として開催されました。
本記事では、熊谷が担当した「製造業で使える生成AI(基本編)」の内容を中心に、製造業における生成AI活用の核心とその具体的な事例をご紹介します。
生成AIは「産業革命」— 従来のAIとの違い
まず、なぜ今、これほどまでに生成AIが注目されているのでしょうか。添付資料でも強調されている通り、生成AIの登場はインターネットの登場以来の「産業革命」と位置づけられています。
従来のAIは「自動化の道具」
これまでのAI(例:不良品検知、数値予測など)は、決められた作業をこなす「自動化の道具」でした。大量のデータからパターンを見つけ出し、分類したり予測したりする役割です。
生成AIは「パートナー/エージェント」
一方、生成AIは、人間のように自然な対話を通じて、文章やアイデアを自ら創造する「パートナー/エージェント」です。例として、報告書作成や新製品のアイデア出しといった知的業務のサポートが可能になります。
生成AIの登場は、全社員に「会社の全知識を記憶した、超優秀な新人」が一人ずつ付くようなもの。面倒な仕事を「奪う」のではなく、「助ける」存在として、企業の生産性を抜本的に向上させる起爆剤となるのです。経営層は、この変化を「対岸の火事」と見ず、追い風にできるかどうかが今後の企業成長の分岐点となると警鐘を鳴らしています。
日本の生成AI活用、現状と課題
生成AIが普及し始めた2022年から2023年以降、世界各国がAI開発競争に参画する中、日本のAI利活用は十分に進んでおらず、AI関連の投資も停滞しているという現状があります。内閣府も「AIを使わないことが最大のリスク」であると指摘しており、AI投資・利活用の推進は喫緊の課題です。
製造業でのAI活用:5つのフレームワーク
漠然としたAI活用ではなく、自社の業務に合う「型」を知ることが成功の第一歩です。製造業における生成AI活用は、主に以下の5つのフレームワークに分類できます。
| No. | フレームワーク | 目的・効果 |
|---|---|---|
| ① | 専門知識・対話アシスタント型 | 熟練者や匠の技を、いつでも誰でも利用できるようにする。 |
| ② | コンテンツ・ドキュメント生成型 | 面倒な書類仕事(報告書、日報など)をAIに任せる。 |
| ③ | アイデア創出・企画支援型 | 優秀な壁打ち相手として、会社の“脳”を強化させる。 |
| ④ | 予測・最適化提案型 | “勘と経験”に、“データ”という武器を加え、生産計画や需要予測の精度を向上させる。 |
| ⑤ | コード・設計生成支援型 | 専門家の仕事を、もっと速く、もっと高精度にし、RPAやExcelマクロの作成を支援する。 |
製造業の具体的事例から学ぶAI活用
セミナーでは、このフレームワークに基づき、製造業での具体的な活用事例が紹介されました。
1. 設計技術ノウハウの共有にAI活用(専門知識・対話アシスタント型)
熟練者のノウハウの属人化解消と技術継承は、製造業の大きな課題です。
事例:シンワバネス株式会社
半導体製造装置に使われるヒーターなどの設計・開発を行うシンワバネス株式会社の事例です。
- 課題:熟練者のノウハウが属人化し、若手へのOJT(On-the-Job Training)の負担が大きかった。
- 活用:300以上の社内文書(ヒヤリハット、設計ノウハウ、マニュアル、業務研修資料など)を学習させた* AIチャットボット(KASVI, V.G.など)を導入。若手がいつでも質問できる環境を構築しました。
- 成果:OJTの負担が軽減され、年間で約414時間の人件費削減を達成。若手社員の「わからない……」を埋める環境ができ、周囲が忙しい時でも「いつでも聞ける」心理的な安全性が向上しました。
参考:中小製造業におけるAI活用×技術伝承事例:株式会社シンワバネスに学ぶ若手育成術
https://smart-factory.funaisoken.co.jp/250430/
AI活用成功の鍵:自社データの学習
世の中にあるデータのみで学習している一般的な生成AIでは、「一般的な回答」しか返ってきません。自社独自の課題を解決し、具体的な提案を得るには、世の中のビッグデータに加え、自社固有のデータ(設計ノウハウ、過去のトラブル事例、原価データなど)をAIに学習させる必要があります。
シンワバネスの事例では、RAG(Retrieval-Augmented Generation)技術により、社内ナレッジを参照した回答を生成し、ヒーター設計に関する専門性の高い問い合わせに対応できています。例えば、ヒーターの不具合に対するリスクの程度や対策、さらには湿度浸入による絶縁抵抗低下を数理モデルで記述するなど、高度な技術サポートを実現しています。
2. 生産技術ノウハウの共有にAI活用(コンテンツ・ドキュメント生成型、コード・設計生成支援型など)
新潟県の株式会社カワイ精工の事例では、9年前に入社当時、業務が紙・FAX・電話のアナログ運用で、業務の無駄や遅さ、データの活用不足が課題でした。
デジタル化の土台構築
まず、金型に関する情報(製品構造、図面、3Dデータ、部品表、実績、修理履歴など)をデジタル化し、「電子カルテ」として一元管理するデジタル化(DXの土台構築)に着手しました。
生成AIによるノウハウ活用
このデジタル化されたデータを基盤として、生成AIを以下のような業務に活用しています。
- 社内データの活用:社内ノウハウ、手順書の回答、売上・在庫分析、日報の要約、資料作成。
- 技術ノウハウの活用:後進教育、類似品への応用、トラブル対処・防止。
- 図面の自動読み取り:2D/3D図面のPDFや画像から、寸法、公差、表面粗さなどの指示内容をAIが自動で抽出・要約。さらに金型設計案を提案。
- NCプログラムの言語化:Gコードを自動解析し、各行の意味や注意点を日本語で自動生成(技術ノウハウの明文化)。
AI活用の「一番の壁」と乗り越え方
AI活用を成功させるには、データ活用に必要な視点、特にデータの「粒度」が重要です。完成品の加工時間だけでなく工程ごとの加工時間、段取時間、停止理由など、詳細なデータを取得することで、真の原因や改善箇所を特定できます。
また、AI導入の「一番の壁」は、現場の「デジタルへの抵抗感と変化を嫌う組織心理」です。これに対し、「仕事が増える」「責任が増える」といった不安な感情を、「便利になる」「毎日15分早く帰れる」といった良い感情に変えることが重要です。早期に目に見える成果を出し、現場の「納得感」を得ることが成功の鍵となります。
AI活用セミナーにご参加いただいたお客様の声
多くの皆様にご参加いただき、誠にありがとうございました。 セミナー後のアンケートでは、貴重なご意見やご感想を多数頂戴いたしました。 その中から、特に参考になった点や印象に残ったセッションについてのお声を一部ご紹介します。
1. 「具体的な活用例・導入事例が分かりやすかった」
今回のセミナーでは、実際の企業の導入例や、現場でAIをどのように活用できるのかについて、多くのご評価をいただきました。
- 「実際の企業の導入例が見れて分かりやすかったです。」
- 「実際にどういった業務にAIが利用できるのかが分かった点」
- 「現場での活用例が参考になりました 思いもよらない活用例でした」
- 「かんたんなことにしかAIを使用していなかったのでAIで何ができるかを具体的な操作で紹介してもらい参考になった。」
2. 「AI活用のための『準備』や『要件』を学べた」
AIを導入し効果を発揮するために必要な準備や、データ蓄積の重要性について、改めて実感いただけたというお声も寄せられています。
- 「AI活用でもそれなりに効果が発揮できるデータ蓄積が必要であることを改めて実感でき参考になりました。」
- 「3つのセッション全てがとても興味深く、AI活用をするために準備することがわかり大変参考になりました。」
3. 「各セッションへの高い評価」
セミナー全体や、特定のセッションに対してもご好評の声をいただきました。
- 「第3部 船井総研様が製造業の現場に向けたコンサルティング事業に取り組んでおられることを初めて知り大変勉強になりました。システムインテグレーションにおいて要件定義がとても重要であることは同意見です。」
- 「どのセッションも参考になりました」
皆様からいただきました貴重なご意見は、今後のセミナー企画や情報発信に活かしてまいります。 ご参加、ならびにアンケートへのご協力、誠にありがとうございました。
結びに
本セミナーを通じて、生成AIが製造業にもたらす変革の可能性と、それを実現するための具体的なステップをご紹介しました。AIを「知っている」段階から「使いこなせる」段階へと移行し、企業の成長を加速させるためのヒントとなれば幸いです。
工場DXの推進や生成AIの活用について、さらに具体的なご相談やご支援をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせください。
https://www.funaisoken.co.jp/form/consulting?siteno=S045