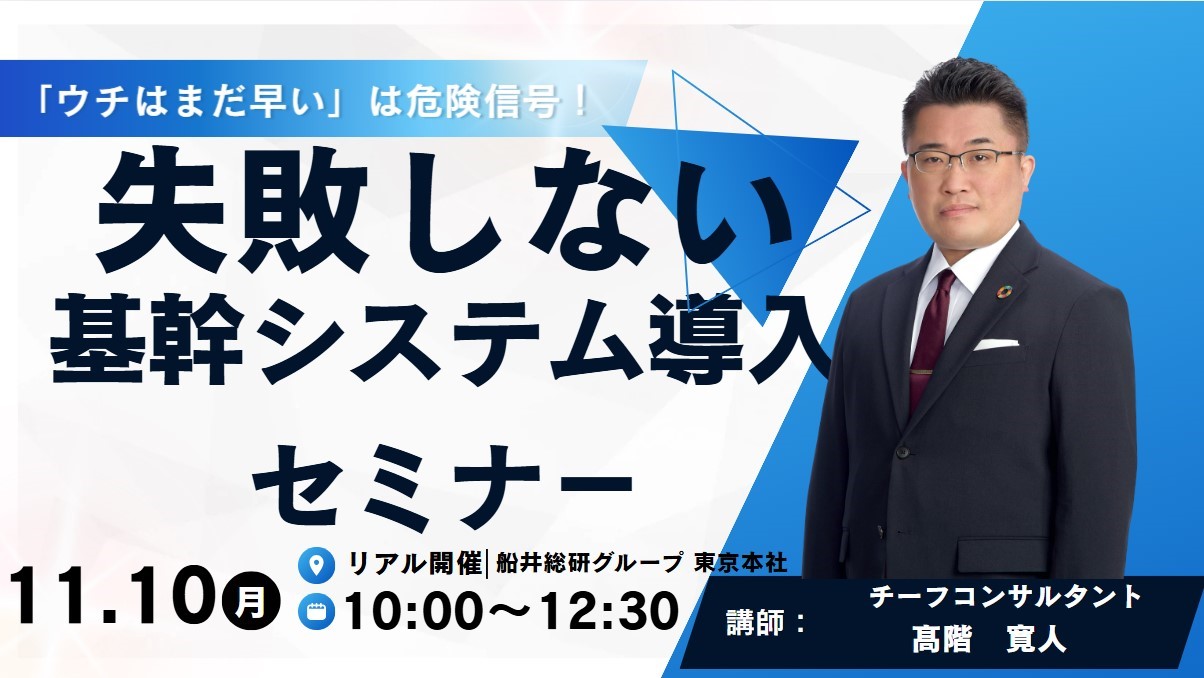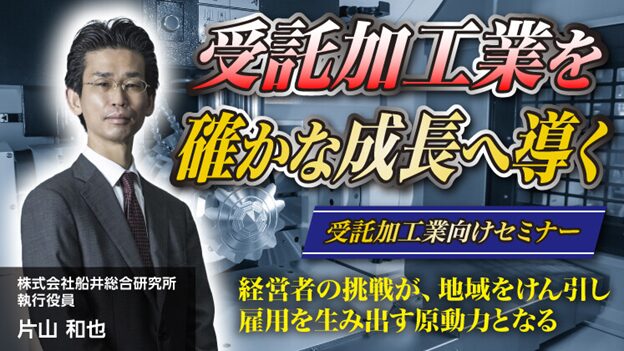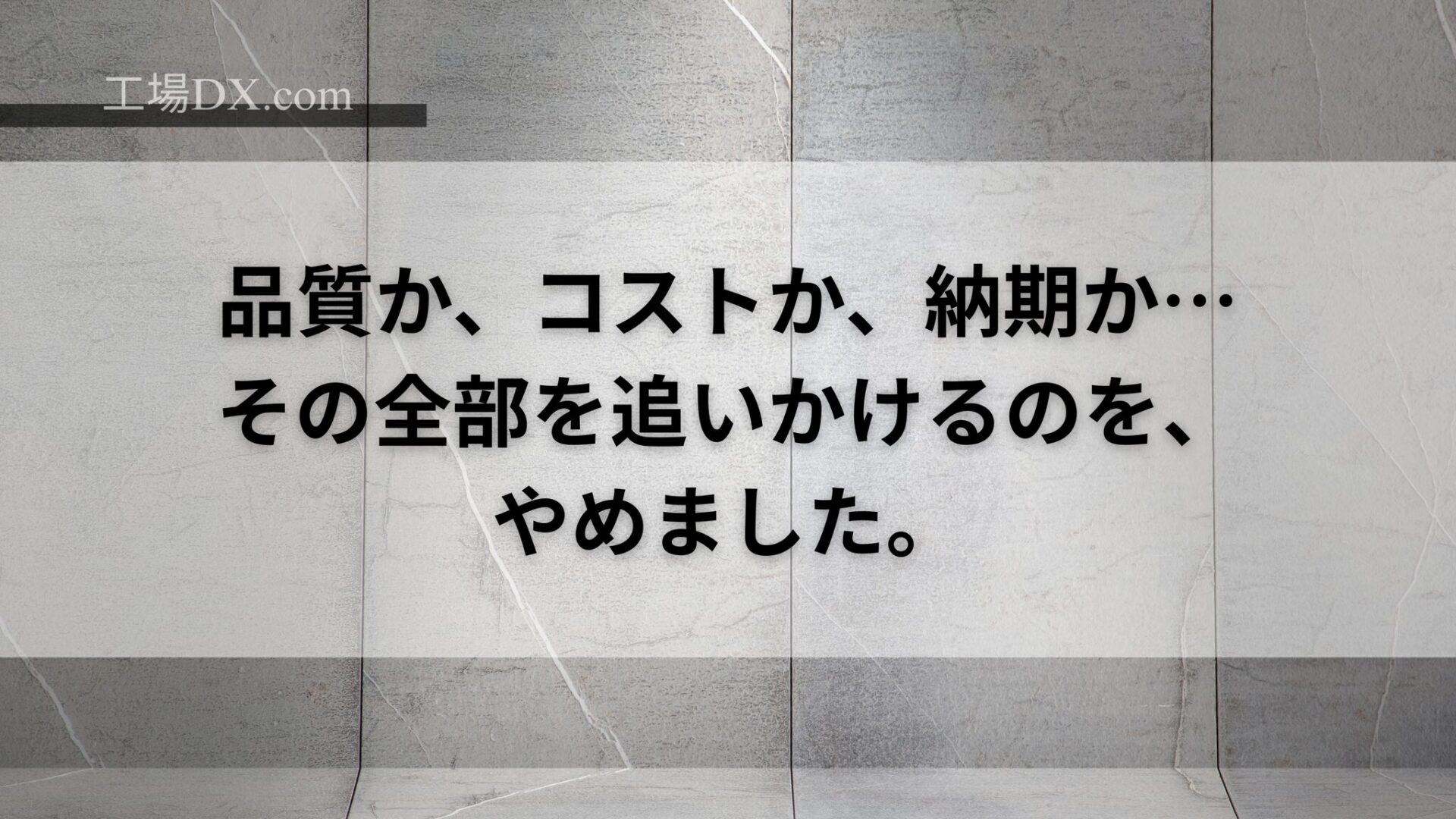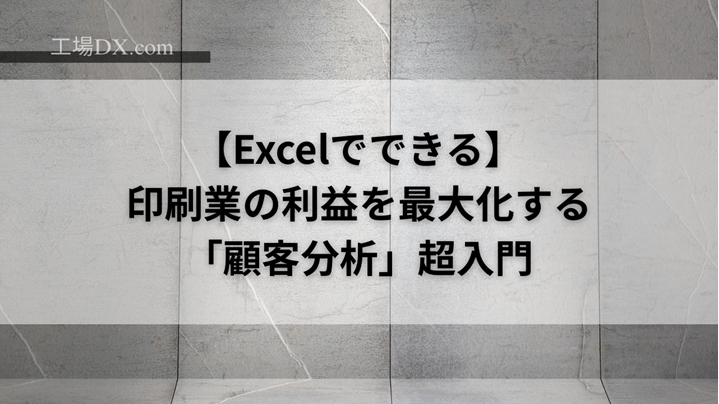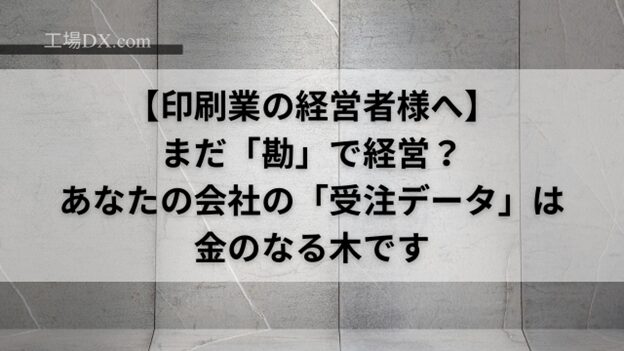【Excelでできる】印刷業の利益を最大化する「顧客分析」超入門
2025.09.18
「データが大事なのは分かった。でも、そのExcelファイルをどう使えばいいんだ?」
前回の記事をお読みいただいた方から、そんな声が聞こえてきそうです。 安心してください。この記事では、専門的な分析ツールや難しい統計知識は一切使わずに、あなたがいつも使っているExcelだけで「儲かる顧客」と「儲かる案件」を具体的に見つけ出す方法を、手順を追って解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたのExcelファイルは、ただの数字の羅列から「経営戦略を立てるための羅針盤」に変わっているはずです。
▼前回の記事はこちら
https://smart-factory.funaisoken.co.jp/20250918-2/
分析の前に:受注データに含めるべき7つの必須項目
正確な分析のためには、元となるデータが重要です。まずは、あなたの受注データに以下の項目が揃っているか確認してください。これから入力する場合は、この7項目を必ず入れましょう。
顧客ID/顧客名: どの顧客からの注文か
受注日: いつ注文されたか
商品/サービス名: 何を注文されたか
数量: いくつ注文されたか
売上金額: いくらで売れたか
原価: その案件にかかった費用(材料費、外注費など
利益額: (売上金額 - 原価)
特に「原価」と「利益額」が重要です。ここを把握することが、利益改善の第一歩です。
【手順1】SORT関数で「利益率ランキング」を瞬時に作成
まずは、どの案件が一番儲かっているのか、ズバリ見てみましょう。
データが入力された表の隣に、もう一度「顧客名」「利益額」などの見出しをコピーします。
その見出しのすぐ下のセルに、=SORT( と入力します。
元のデータ範囲(見出しを除く)をマウスで選択します。
次に、並べ替えの基準となる列を指定します。利益額の列が7番目なら ,7 と入力。
最後に、並び順を「降順(大きい順)」にするため , -1 と入力し、)で閉じます。
◦完成形: =SORT(A2:G100, 7, -1)
Enterキーを押せば、利益額が高い順に並んだランキングが自動で作成されます!
これで、「勘」では分からなかった「本当に儲かっている案件」が一目瞭然になります。
【手順2】ピボットテーブルで「隠れ優良顧客」をあぶり出す
次に、顧客ごとの傾向を分析します。少し難しそうに聞こえますが、マウス操作だけでできてしまうExcelの最強機能「ピボットテーブル」を使いましょう。
データ範囲のどこかをクリックした状態で、メニューの「挿入」→「ピボットテーブル」を選択。
「OK」を押すと、新しいシートにピボットテーブルの設計画面が表示されます。
画面右側に出てくるフィールドリストから、以下のようにドラッグ&ドロップします。
◦「顧客名」を「行」エリアへ
◦「売上金額」を「値」エリアへ
◦「利益額」を「値」エリアへ
◦もう一度「顧客名」を「値」エリアへ(これは受注回数をカウントするため)
たったこれだけで、顧客ごとの「合計売上」「合計利益」「受注回数」が一覧で表示されます。
分析結果から見えた!A社とB社の衝撃的な違い
このピボットテーブルを使えば、先日の記事で例に出したような比較が簡単にできます。
A社: 合計売上: 1000万, 合計利益: 50万, 受注回数: 50回 → 1回あたりの利益: 1万円
B社: 合計売上: 200万, 合計利益: 80万, 受注回数: 10回 → 1回あたりの利益: 8万円
一目瞭然ですね。営業リソースを割くべきはB社のような顧客であり、A社に対しては利益率改善の交渉が必要かもしれません。
まとめ:分析はゴールじゃない。行動して初めて利益が生まれる
いかがでしたか?Excelの基本的な機能だけで、これだけの分析が可能です。 大切なのは、この分析結果を見て「へぇ、そうなんだ」で終わらせないこと。
利益率の高い顧客へのフォローを手厚くする
利益率の高い案件と似たような提案を他の顧客にもしてみる
不採算案件については、価格交渉や仕様の見直しを行う
このように、具体的な「行動」に移して初めて、データは本当の「利益」に変わります。
Excel分析の、その先へ。データ活用を「仕組み」にしませんか?
Excelでの分析、お疲れ様でした。顧客ごとの利益が可視化され、多くの気づきがあったのではないでしょうか。
しかし同時に、
「このデータ入力を毎回やるのは大変だ…」
「受注データだけでなく、製造日報のデータと掛け合わせてもっと深く分析できないか?」
「分析を自分だけでなく、会社全体の文化にしたいが、どうすれば?」
といった、新たな課題や欲も生まれてきたかもしれません。
その「次の一手」を具体的に知りたい経営者の皆様へ、改めてこちらのセミナーをおすすめします。
脱!紙・Excel日報・紙図面!中小製造業が「高収益工場」に変わるデータ活用術
紙管理脱却のための中小製造業データドリブン経営入門セミナー
https://www.funaisoken.co.jp/seminar/134272
このセミナーでは、今回実践したようなExcelでの分析から一歩進み、データ活用を「仕組み化」し、持続的な利益向上につなげるための具体的な方法を学ぶことができます。
脱・手作業! 日々のデータ収集を自動化し、分析の手間を削減する方法
原価の見える化! 受注データと製造日報データを連携させ、より正確な原価管理を実現するツール
属人化からの脱却! 経験と勘に頼っていた見積業務をAIで効率化する最新事例
Excelで得た手応えを、一過性のものから会社全体の「強み」へと変えるためのヒントが満載です。ぜひ、以下のリンクから詳細をご確認ください。 「データが大事なのは分かった。でも、そのExcelファイルをどう使えばいいんだ?」
前回の記事をお読みいただいた方から、そんな声が聞こえてきそうです。 安心してください。この記事では、専門的な分析ツールや難しい統計知識は一切使わずに、あなたがいつも使っているExcelだけで「儲かる顧客」と「儲かる案件」を具体的に見つけ出す方法を、手順を追って解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたのExcelファイルは、ただの数字の羅列から「経営戦略を立てるための羅針盤」に変わっているはずです。
▼前回の記事はこちら
https://smart-factory.funaisoken.co.jp/20250918-2/
分析の前に:受注データに含めるべき7つの必須項目
正確な分析のためには、元となるデータが重要です。まずは、あなたの受注データに以下の項目が揃っているか確認してください。これから入力する場合は、この7項目を必ず入れましょう。
顧客ID/顧客名: どの顧客からの注文か
受注日: いつ注文されたか
商品/サービス名: 何を注文されたか
数量: いくつ注文されたか
売上金額: いくらで売れたか
原価: その案件にかかった費用(材料費、外注費など
利益額: (売上金額 - 原価)
特に「原価」と「利益額」が重要です。ここを把握することが、利益改善の第一歩です。
【手順1】SORT関数で「利益率ランキング」を瞬時に作成
まずは、どの案件が一番儲かっているのか、ズバリ見てみましょう。
データが入力された表の隣に、もう一度「顧客名」「利益額」などの見出しをコピーします。
その見出しのすぐ下のセルに、=SORT( と入力します。
元のデータ範囲(見出しを除く)をマウスで選択します。
次に、並べ替えの基準となる列を指定します。利益額の列が7番目なら ,7 と入力。
最後に、並び順を「降順(大きい順)」にするため , -1 と入力し、)で閉じます。
◦完成形: =SORT(A2:G100, 7, -1)
Enterキーを押せば、利益額が高い順に並んだランキングが自動で作成されます!
これで、「勘」では分からなかった「本当に儲かっている案件」が一目瞭然になります。
【手順2】ピボットテーブルで「隠れ優良顧客」をあぶり出す
次に、顧客ごとの傾向を分析します。少し難しそうに聞こえますが、マウス操作だけでできてしまうExcelの最強機能「ピボットテーブル」を使いましょう。
データ範囲のどこかをクリックした状態で、メニューの「挿入」→「ピボットテーブル」を選択。
「OK」を押すと、新しいシートにピボットテーブルの設計画面が表示されます。
画面右側に出てくるフィールドリストから、以下のようにドラッグ&ドロップします。
◦「顧客名」を「行」エリアへ
◦「売上金額」を「値」エリアへ
◦「利益額」を「値」エリアへ
◦もう一度「顧客名」を「値」エリアへ(これは受注回数をカウントするため)
たったこれだけで、顧客ごとの「合計売上」「合計利益」「受注回数」が一覧で表示されます。
分析結果から見えた!A社とB社の衝撃的な違い
このピボットテーブルを使えば、先日の記事で例に出したような比較が簡単にできます。
A社: 合計売上: 1000万, 合計利益: 50万, 受注回数: 50回 → 1回あたりの利益: 1万円
B社: 合計売上: 200万, 合計利益: 80万, 受注回数: 10回 → 1回あたりの利益: 8万円
一目瞭然ですね。営業リソースを割くべきはB社のような顧客であり、A社に対しては利益率改善の交渉が必要かもしれません。
まとめ:分析はゴールじゃない。行動して初めて利益が生まれる
いかがでしたか?Excelの基本的な機能だけで、これだけの分析が可能です。 大切なのは、この分析結果を見て「へぇ、そうなんだ」で終わらせないこと。
利益率の高い顧客へのフォローを手厚くする
利益率の高い案件と似たような提案を他の顧客にもしてみる
不採算案件については、価格交渉や仕様の見直しを行う
このように、具体的な「行動」に移して初めて、データは本当の「利益」に変わります。
Excel分析の、その先へ。データ活用を「仕組み」にしませんか?
Excelでの分析、お疲れ様でした。顧客ごとの利益が可視化され、多くの気づきがあったのではないでしょうか。
しかし同時に、
「このデータ入力を毎回やるのは大変だ…」
「受注データだけでなく、製造日報のデータと掛け合わせてもっと深く分析できないか?」
「分析を自分だけでなく、会社全体の文化にしたいが、どうすれば?」
といった、新たな課題や欲も生まれてきたかもしれません。
その「次の一手」を具体的に知りたい経営者の皆様へ、改めてこちらのセミナーをおすすめします。
脱!紙・Excel日報・紙図面!中小製造業が「高収益工場」に変わるデータ活用術
紙管理脱却のための中小製造業データドリブン経営入門セミナー
https://www.funaisoken.co.jp/seminar/134272
このセミナーでは、今回実践したようなExcelでの分析から一歩進み、データ活用を「仕組み化」し、持続的な利益向上につなげるための具体的な方法を学ぶことができます。
脱・手作業! 日々のデータ収集を自動化し、分析の手間を削減する方法
原価の見える化! 受注データと製造日報データを連携させ、より正確な原価管理を実現するツール
属人化からの脱却! 経験と勘に頼っていた見積業務をAIで効率化する最新事例
Excelで得た手応えを、一過性のものから会社全体の「強み」へと変えるためのヒントが満載です。ぜひ、以下のリンクから詳細をご確認ください。