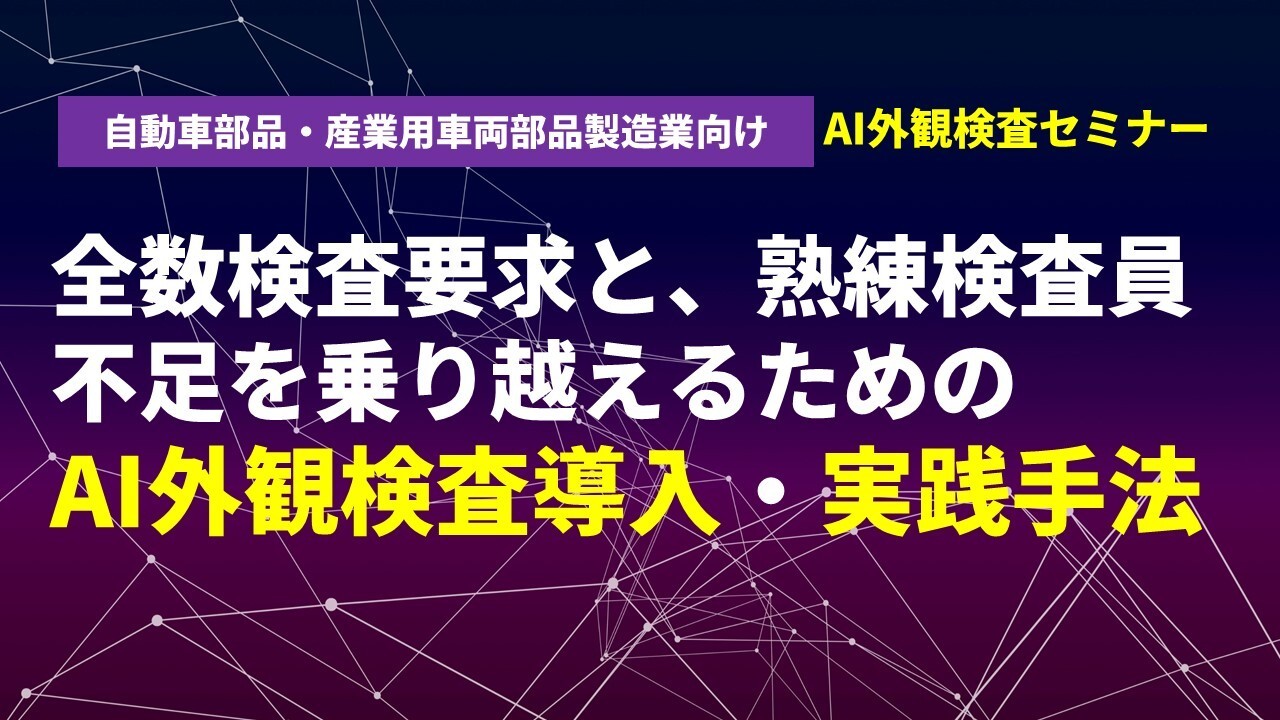記事公開日:2025.08.27
最終更新日:2025.08.27
「1000万円の画像検査装置が全く使えない…」ゲスト講師が語る失敗とV字回復の軌跡

「1000万円の画像検査装置が全く使えない…」ゲスト講師が語る失敗とV字回復の軌跡
「0.1mm未満のキズすら許されない」──これが、自動車部品・産業用車両部品製造業界
の現実です。重要保安部品として人の命に直結するこれらの部品は、まさに日本のものづくりの真髄を体現する高精度な品質管理が求められています。
しかし、多くの企業が直面する「熟練検査員不足」という深刻な課題に直面しています。今回、1000万円という投資の失敗を経験した半田重工業の松下剛幸氏が、その軌跡を語るセミナーを開催いたします。
目次
1.1000万円の画像検査装置導入に失敗した半田重工業
「大手企業の画像検査装置を1000万円かけて導入をしましたが、当社のラインでは上手く検査をすることができず、最終的に失敗という結果となってしまいました。」
この率直な告白の背景には、多くの製造業が抱える共通の課題があります。熟練検査員の高齢化、新人がなかなか育たない現実、そして根本的な人材不足。計画通りに人材確保ができず、育てる余裕もない状況で、現場には「このままでは回らなくなる」という切迫した焦りがありました。
では、なぜ1000万円の投資が無駄になったのか。
失敗の根本原因は、油圧シリンダーという製品特性への理解不足でした。独特な円筒形状と鏡面仕上げという当社独自の製品形状、実際のライン速度、そして0.1mm未満という超高精度な検査基準との相性が合わなかったのです。理論上は可能とされた検査も、実運用では大きな乖離が生じ、十分な成果を上げることができませんでした。
「当社独自の製品形状、ライン速度、検査基準との相性が合わず、十分な成果を上げることができなかった。結局、その装置は稼働せず、再び人の目に頼る日々が戻ってきました。」
—————————-
しかし、この失敗こそが転換点となりました。「自分たちで作るしかないのではないか?」という一言から始まった奇跡の逆転劇。社内にノウハウが全くない状況でしたが、「人に頼る品質管理」から「技術を育てる品質管理」という根本的な方針転換を決断したのです。
最初は当然、画像処理の知識も経験もありませんでした。しかし、外部のベンダーに依存するのではなく、自社で技術を習得し、育てていく方向に舵を切りました。この決断が、後の成功につながる重要なポイントとなったのです。
結果として誕生した半田重工業製の画像検査装置は、鏡面の外観検査という技術的難題を克服し、金属の光沢やハレーションを完全に制御することに成功。AI導入による全数検査と生産効率の両立を実現しました。
驚くべき投資効果として、本装置を導入することで、従来2名で行っていた検査作業が実質0.5名で対応可能に。これにより、年間約450万円のコスト削減効果を実現しました。
2.半田重工業の失敗から学ぶ、「AI外観検査導入において絶対に避けるべき5つの罠」
導入に失敗する企業は、以下の5つのtrapのどれかにはまっている可能性が高いです。
- 仕様ありき trap:仕様書ありきで装置を選定し、自社の実情を十分に考慮しない。
- スピード重視 trap:早期の成果を求めるあまり段階的な検証を飛ばしてしまう。
- 丸投げ trap:ベンダーに全てを任せて社内にノウハウが蓄積されない。
- 完璧主義 trap:最初から100%の精度を目指して実用化が遅れる
- コスト軽視 trap:初期投資のみを重視してランニングコストを軽視する
対して、導入に成功する企業はどのようなプロセスを実践しているのでしょうか。
実は、成功する企業には共通の導入プロセスがあります。
以下の7つのステップを段階的に進めることで、リスクを最小化しながら確実な成果を得ることができます。
【Step1】現状分析・データ化 → 【Step2】小規模POC実施
↓ ↓
【Step3】光学系最適化 → 【Step4】AI学習データ収集
↓ ↓
【Step5】段階的導入 → 【Step6】運用最適化
↓
【Step7】ノウハウ蓄積・横展開
まず現状の検査工程を徹底的に分析し、データ化することから始めます。その後、小規模なPOC(概念実証)による技術検証を行い、光学系の最適化と「欠陥の見える化」技術を確立していきます。AI学習データの戦略的な収集と品質管理を行い、段階的な導入により現場への定着を図ります。さらに、ROIを最大化するための運用最適化を継続し、社内ノウハウの蓄積と横展開体制を構築することで、持続可能なAI活用を実現しています。
3.他のセミナーでは聞けない!松下氏ゲスト講話 & 成功事例5選 & 失敗しないAI外観検査導入の進め方を解説
ここからは、プロジェクトを成功に導くための具体的な5つの秘訣を紹介します。
今回のセミナー「自動車部品・産業用車両部品製造業向けAI外観検査セミナー ~全数検査要求と、熟練検査員不足を乗り越えるためのAI外観検査導入・実践手法~」では、失敗と成功の両方を経験した当事者から直接学ぶことができます。
第1講座では、画像処理検査装置メーカー出身でAIシステム開発の実務経験を持つ船井総合研究所の川端信貴が、失敗パターンとその回避策について解説します。AI導入で陥りがちな5つの罠とその解決策、成功企業が必ず実践する段階的導入プロセスの全体像など、実践的な知識を提供いたします。
第2講座は本セミナーの核心部分です。半田重工業株式会社の松下剛幸氏が、未経験からAI画像検査装置内製化を成功させた当事者として、その軌跡を公開します。一度は失敗したAI外観検査装置導入を成功させた秘訣と導入効果、失敗から学んだ外観検査装置運用成功までの具体的な道筋、金属の光沢やハレーションを抑えて曲面の打痕を検査する具体的手法など、他では決して聞くことのできない貴重な経験談をお話しいただきます。
第3講座では、製造現場経験12年、100社を超えるDX診断実績を持つ船井総合研究所の徳竹勇兵が、明日から実行可能な導入ロードマップを提示します。ROIを最大化するAI外観検査導入の進め方、外観検査工程にAI導入して自動化を成功させるポイント、経営者・幹部社員のためのAI外観検査活用戦略など、即実践可能な内容となっています。
また、セミナーでは、5つの実証済み成功事例を詳細に解説いたします。円筒状産業用車両部品の自動AI画像検査装置導入成功事例をはじめ、既存画像検査機のAI高度化による精度向上事例、ワッシャ外観検査のAI化で検査員2名削減を実現した成功事例、自動車ボディ塗装後検査の完全AI化事例、円筒状自動車部品の半自動画像検査システム導入事例などを解説。
4.最後に – あなたの会社の未来のために
本セミナーは、1000万円の失敗を、あなたの成功に変える2時間半となっております。「同じ轍を踏まない」ための具体的な方法論と、「必ず成功させる」ための実践的ノウハウを、失敗と成功の両方を経験した当事者から直接学べる、またとない機会となっています。
今、あなたの目の前には2つの道があります。
一つ目は、現状維持という道です。熟練検査員の退職を見送り、品質問題のリスクを抱えながら、いつか限界が来る日まで従来の方法にしがみつく道。人材確保の困難さは年々増しており、この道を選択すれば、数年後には確実に経営危機に直面することになるでしょう。
二つ目は、変革への挑戦という道です。半田重工業が辿ったように、失敗を恐れず、自社の技術力向上に投資し、AI導入によって年間450万円のコスト削減を実現する道。この道を選択すれば、競合他社が苦しむ中で、あなたの会社だけが持続的な成長を手に入れることができます。
どちらの道を選ぶかは、あなた次第です。
ただし、変革への道を選ぶなら、今がそのタイミングです。なぜなら、AI外観検査の技術はまだ発展途上であり、今から取り組めば先行者利益を享受できるからです。2年後、3年後になってから慌てて導入を検討しても、その時には既に競合他社に大きく後れを取っていることでしょう。
半田重工業の松下氏も、最初は全くの未経験でした。しかし、「人に頼る品質管理」から「技術を育てる品質管理」への転換を決断し、社内でのノウハウ蓄積に取り組んだ結果、見事に成功を収めました。あなたの会社にも、同じことができないはずはありません。
このセミナーは、単なる情報収集の場ではありません。あなたの会社の未来を決める、重要な分岐点となる場です。半田重工業の生々しい失敗体験と成功への軌跡から学び、あなたの会社が同じような成功を収めるための具体的な道筋を手に入れてください。
あなたの決断が、会社の未来を変えます。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
自動車部品・産業用車両部品製造業向けAI外観検査セミナー
関連コラム

ロボットのティーチングとは?ティーチングの種類と概要を解説
2019.08.27

溶接ロボットで行う自動化の方法とは?
2019.08.29

産業用ロボットとは?最新動向からロボットの違いを知る
2019.09.17