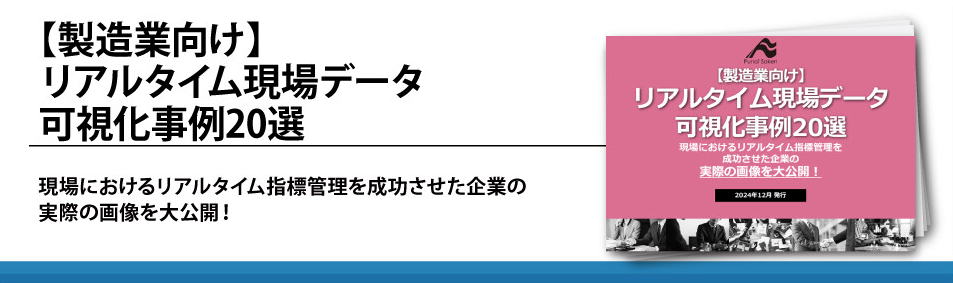記事公開日:2025.07.01
最終更新日:2025.07.01
もう手動立案は不要!生産スケジューラで計画を自動化し、生産性を劇的に改善する方法

URL: https://www.funaisoken.co.jp/dl-contents/jy-cost_S045

目次
1. はじめに:もう手動の生産計画立案は不要!
多品種少量生産を行う中小製造業の皆さま、日々の生産計画の立案に、多くの時間と負担をかけてはいませんか?急な受注変更、部品の納期遅延、そして予期せぬ設備のトラブルなど、製造業の現場では常に様々な変化が発生します。これらの変化に対応するため、手作業やExcelで生産計画を調整することに、担当者の皆さまは大きな工数を割いていることでしょう。
しかし、その業務は本当に効率的でしょうか?「工場 効率化」という大きな目的を達成するためには、生産計画の立案という業務そのものを見直すことが必要です。
この記事では、生産スケジューラというツールを活用して生産計画を自動化し、工場全体の効率化を実現する方法について、徹底的に解説します。この記事を読めば、生産計画の自動化がなぜ重要なのか、どのようなメリットがあるのか、そして自社に合ったシステムを選ぶための比較ポイントまで、すべてがわかります。
特に、多品種少量生産を行っている製造業の方々が抱える悩みや課題を解決するためのヒントを、具体的な事例やデータを交えて提供します。もう手作業での計画作成に時間をかけることは不要です。生産計画の自動化で、貴社の工場を効率的に変革していきましょう
関連記事:「【製造業向け】スマートファクトリーとは?DX実現の7つのポイント・メリット・導入成功事例をわかりやすく解説」
https://smart-factory.funaisoken.co.jp/250625-2/
2. 生産計画の自動化とは?生産スケジューラが実現する効率化
工場の効率化を実現する上で、生産計画の自動化は避けて通れないテーマです。では、生産計画の自動化とは具体的にどのような仕組みで、手動立案と比べてどのような違いがあるのでしょうか。
● 生産計画の自動化は、なぜ製造業の工場効率化に必要不可欠なのか?
生産計画の自動化とは、これまで人の手やExcelを利用して行っていた生産計画の立案や修正といった一連の業務を、生産スケジューラという専門のシステムを活用して自動で行えるようにすることです。
製造業の工場では、受注ごとに生産する製品の種類や量が変化する多品種少量生産が多くあります。このような生産方式では、生産計画の立案が非常に複雑になり、担当者の負担が増大します。例えば、ある製品の納期が急に短縮された場合、それに対応するためには、関連するすべての工程のスケジュールを見直す必要があります。手作業でこれを行うと、膨大な時間がかかるだけでなく、ミスを発生させる可能性が高まります。
生産計画の自動化は、このような課題を解決するための有効な手段です。生産スケジューラに受注情報や部品の在庫情報、設備の稼働状況などを入力すると、システムが自動で最適な生産計画を作成します。これにより、担当者は計画作成にかかる時間を大幅に削減し、より重要な業務に集中することが可能となります。
● 手動による生産計画と自動化による生産計画の決定的な違いを解説
手動による生産計画と自動化による生産計画には、決定的な違いがあります。
手動での生産計画作成は、担当者の経験や勘に基づいて行われることが多くあります。特に、長年の経験を持つベテラン担当者のスキルに依存する部分が大きく、この知識やノウハウが共有されないまま属人化してしまう問題が発生します。
一方、自動化された生産計画では、システムが持つAIやアルゴリズムが計画を作成します。システムは、納期、設備の稼働時間、人員のスキル、部品の在庫状況、工程の順序といった様々な制約条件を考慮して計画を作成します。これにより、誰が計画を作成しても同じ精度の計画を作成することが可能となります。
また、手動では修正に時間がかかった計画も、自動化システムであれば、条件を変更するだけで迅速に新しい計画を作成できます。この違いは、工場の柔軟性と対応力に大きく影響します。生産計画の自動化は、まさに工場の効率化を実現するための基盤となるのです。
関連記事:「2025年問題、中堅製造業の未来を左右する?MESが解き放つサプライチェーン強靭化の鍵」
https://smart-factory.funaisoken.co.jp/250624-2/
3. 生産計画を自動化する5つのメリット
生産計画の自動化は、工場の効率化を実現する上で様々なメリットをもたらします。ここでは、特に重要な5つのメリットについて、具体的な数字や事例を用いて詳しく解説します。
1. 生産管理業務の属人化解消と業務効率化
生産計画の立案が属人化すると、特定の担当者に業務が集中し、その人が不在の際に業務が滞るという課題が発生します。生産計画の自動化は、この課題を根本から解決します。
システムが計画を自動で作成するため、誰でも同じ品質の計画を作成することが可能となります。これにより、担当者の経験やスキルに依存することなく、業務を標準化することが可能です。
また、システムが持つデータは社内で共有されるため、担当者間での情報の共有がスムーズに行えます。これにより、人が変わっても業務が滞ることがなく、安定した生産活動を維持することが可能となります。
2. 生産性の向上とコスト削減
生産計画の自動化は、工場の生産性を劇的に向上させます。生産スケジューラは、設備の稼働時間を最大限に活用し、無駄な待ち時間や段取り時間を最小限に抑える計画を自動で作成します。
例えば、ある機械が稼働している間に、次の機械で必要な部品を準備しておくといった段取り作業の最適化を行います。これにより、ラインの稼働率を向上させ、生産能力を最大限に引き出すことが可能となります。
さらに、生産計画の最適化はコスト削減にも貢献します。無駄な在庫を抱えることがなくなり、在庫管理費用を大幅に抑えることができます。また、生産ラインの稼働状況が可視化されるため、無駄な残業時間を削減することも可能です。適切な人員配置もシステムが支援するため、人件費の削減にもつながります。
3. 計画精度と納期遵守の向上
手動での生産計画では、多くの制約条件を考慮することが困難です。しかし、生産スケジューラは、設備の制約、人員のスキル、資材の供給状況など、複雑な条件を細かく設定できます。
特に多品種少量生産では、一つの工程に関わる製品の種類が多く、工程間の連携が非常に重要です。生産スケジューラは、これらの要素をすべて考慮した上で、正確な計画を作成します。
4. 現場作業員との情報共有と意思決定の迅速化
生産計画をシステムで管理することで、現場の作業員もリアルタイムで生産情報を確認できるようになります。例えば、タブレットや専用の画面で自分が担当する作業の内容や進捗状況を確認できます。
これにより、生産計画の変更情報が迅速に共有され、現場の混乱を防止します。計画が見える化されることで、現場の作業員も次の作業を効率的に準備することが可能となります。また、管理者は工場全体の稼働状況をリアルタイムで把握できるため、問題が発生した際にも迅速な意思決定を行い、対応することが可能となります。
5. DX推進と企業の競争力向上
生産計画の自動化は、製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)の重要な一歩です。計画をデジタル化することで、生産データの収集や分析が可能となり、工場の改善活動を加速させます。
データに基づいた生産管理は、勘や経験に頼った経営から脱却し、変化の激しい市場に柔軟に対応できる強固な企業体制を構築します。これにより、競合他社との差別化を図り、企業の競争力を大幅に向上させることが可能となります。
4. 生産スケジューラ導入の「方法」と「選び方」
生産計画の自動化を実現するために、生産スケジューラの導入は必須です。しかし、様々な種類のシステムが存在するため、自社に合ったツールを選ぶことは簡単ではありません。ここでは、導入を成功させるための方法と比較ポイントを解説します。
生産計画の自動化システム導入を成功させるための4つのステップを解説
生産計画自動化システムの導入は、適切な手順を踏むことで成功の確率が高まります。
関連レポート:「製造現場の生産性を飛躍させる! 4M定量化と製造ロス可視化による 改善レポート」
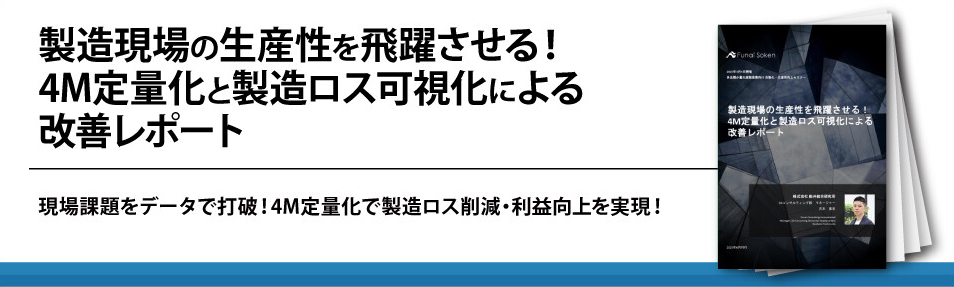
https://www.funaisoken.co.jp/dl-contents/smart-factory__00000260_S045?media=smart-factory_S045
ステップ1: 現状の課題と目的を明確にする
導入を検討する前に、まずは現状の生産計画業務で抱えている課題を明確に把握します。例えば、「計画作成に時間がかかりすぎる」「納期遅延が多い」「担当者以外計画が立てられない」など、具体的な課題をリストアップします。その上で、「計画作成時間を50%削減する」「納期遵守率を98%に向上させる」といった明確な目的を設定します。
ステップ2: 複数システムの比較検討と選定
目的が明確になったら、市場に存在する複数の生産スケジューラを比較検討します。機能、費用、サポート体制などを比較し、自社の要件に合致するシステムを選定します。この際、無料の資料をダウンロードしたり、デモンストレーションを依頼したりして、実際にシステムを確認することが重要です。
ステップ3: スモールスタートでの導入とテスト運用
いきなり工場全体にシステムを導入するのではなく、一部のラインや工程からスモールスタートで導入することをおすすめします。これにより、システムの効果を検証し、現場からのフィードバックを収集できます。テスト運用を行いながら、システムの設定を調整し、自社の業務プロセスに合った運用方法を確立します。
ステップ4: 全体展開と継続的な改善
テスト運用で成功事例が確認できたら、段階的に全体に展開していきます。導入後も、システムの利用状況を分析し、改善点を見つけて継続的に運用を最適化します。生産スケジューラは、導入して終わりではなく、活用することで真の効果を発揮します。
自社に合った生産スケジューラ選びの5つのポイント
生産スケジューラを選ぶ際に確認すべき重要な5つのポイントを紹介します。
ポイント1: スケジューリング機能の違い
生産スケジューラの最大の機能はスケジューリング機能です。AIが搭載されているシステムは、より高度な最適化が可能です。特に、多品種少量生産を行っている製造業の工場向けのシステムでは、多くの制約条件を考慮できる機能が必要です。例えば、「製品ごとに使用できる機械が決まっている」「特定の作業員しか扱えない設備がある」といった条件を細かく設定できるかを確認しましょう。
ポイント2: 既存システムとの連携性
生産スケジューラは、在庫管理システム、ERP(統合基幹業務システム)、MES(製造実行システム)など、他のシステムと連携することで、その真の力を発揮します。リアルタイムな在庫情報や受注情報を自動で取り込める機能があれば、手入力の手間が省け、データの正確性も高まります。
ポイント3: コストと費用対効果
生産スケジューラの費用は、システムの種類や機能範囲によって大きく異なります。初期費用、月額費用、導入費用、メンテナンス費用など、トータルでかかるコストを確認します。そして、導入によって得られるメリット(生産リードタイムの短縮、在庫削減、残業時間削減など)と比較し、費用対効果を検討します。中小企業向けには、助成金や補助金を活用できるケースもあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
ポイント4: サポート体制と導入実績
導入後の運用を円滑に進めるためには、ベンダーのサポート体制が重要です。操作方法の研修、トラブル発生時の対応、システムのカスタマイズ支援など、充実したサポート体制があるかを確認します。また、自社と同じ業種や規模の企業での導入実績があるかも重要な判断基準となります。
ポイント5: 操作のしやすさ(UI/UX)
現場の担当者が日常的に利用するシステムであるため、直感的に操作できるかどうかも重要です。わかりやすい画面、スムーズな操作感、見やすいガントチャートなど、利用者の視点で評価することが必要です。無料の体験会やデモンストレーションで実際に触って確認することをおすすめします。
関連レポ―ト:「失敗しない システム導入の進め方」
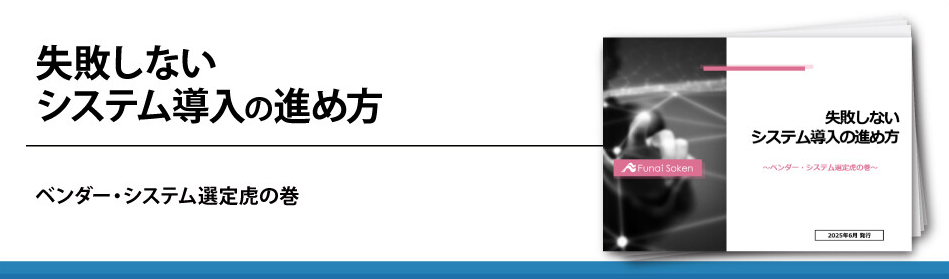
https://www.funaisoken.co.jp/dl-contents/smart-factory_smart-factory_00000271_S045?media=smart-factory_S045
● 無料ツールと有料システムの決定的な違いを解説
生産計画の自動化ツールには、Excelマクロやアドオンツールのような無料のツールから、専門の生産スケジューラシステムまで様々な種類があります。
無料のツールは、手軽に導入できる点がメリットですが、考慮できる制約条件が限られていたり、複雑な計画には対応できない場合が多いです。特に、多品種少量生産のように工程が多く、制約条件が複雑な場合は、無料ツールでは対応が困難になる可能性があります。
一方、有料の生産スケジューラシステムは、AIを搭載した高度な最適化機能や、既存システムとの連携、カスタマイズ機能など、豊富な機能が搭載されています。初期費用や運用費用はかかりますが、得られる効率化効果やコスト削減効果を考慮すると、長期的に見れば投資対効果が高くなるケースが多いです。
関連記事:「【第2回】『また新しいシステムか…』現場の嘆きを共感に変える、IT導入成功の秘訣 ~「やらされ感」を「自分ゴト」へ転換するコミュニケーション術~」
https://smart-factory.funaisoken.co.jp/250604/
5. おすすめの生産スケジューラ・自動化ツール
生産計画の自動化を検討している製造業の方向けに、市場で評価の高いおすすめの生産スケジューラを紹介し、比較します。
● 特徴別おすすめ生産スケジューラを徹底解説
生産スケジューラは、システムの特長によって様々なタイプに分類できます。自社のニーズに合ったタイプを選ぶことが重要です。
タイプ1: AI搭載型で高度な最適化を実現する生産スケジューラ
これらのシステムは、AIや機械学習技術を搭載しており、複雑な制約条件を考慮した上で、人では思いつかないような最適な生産計画を自動で作成します。多品種少量生産や納期が頻繁に変更される現場に特に向いています。
● Asprova: 国内でトップクラスのシェアを誇る生産スケジューラです。AIを搭載し、多くの制約条件を考慮した高度なスケジューリングが可能です。多くの製造業での導入実績があり、複雑な生産プロセスにも対応できます。
● SC-square isp: 日立ソリューションズ東日本が提供する生産スケジューラで、製造業の多様なニーズに合わせたカスタマイズが可能です。日立グループの製造ノウハウが詰まっており、信頼性が高いシステムです。
タイプ2: Excel連携で使いやすさを追求した生産スケジューラ
これらのシステムは、Excelとの連携機能が充実しており、Excelでの生産計画作成に慣れている担当者にとって導入障壁が低いタイプです。
● Seam: 中小企業向けに開発された生産スケジューラです。Excelライクなインターフェースで、直感的に操作できます。比較的安価に導入できる点もメリットです。
● 最適ワークス: 株式会社ワークスが提供する生産スケジューラです。Excelとの連携に特化しており、簡単に生産計画を可視化できます。
タイプ3: クラウド型で手軽に始められる生産スケジューラ
これらのシステムは、クラウド型で提供されるため、サーバーの構築やメンテナンスが不要です。インターネットに接続できる環境であれば利用できるため、場所を選ばず生産計画を管理できます。
● 日立システムズ: 日立システムズが提供するクラウド型生産スケジューラです。AI搭載の最適化エンジンを活用し、迅速な計画作成を支援します。
● smart-F nexta: 株式会社スマートが提供するクラウド型生産スケジューラです。中小企業向けの機能が充実しており、無料の体験版も提供されています。
6. 生産管理の未来:自動化の先にあるもの
生産計画の自動化は、製造業の工場が持続的に成長していくための重要なステップです。自動化によって得られたデータや効率化は、さらに高度な生産管理を実現するための基盤となります。
● 生産計画の自動化がもたらすDXと経営への効果を解説
生産計画の自動化は、製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)の一環です。計画をデジタル化することで、生産データを収集し、分析することが可能となります。
例えば、過去の生産データを分析することで、各工程のボトルネックや無駄な作業を特定できます。これにより、現場の改善活動がデータに基づいて行えるようになり、より効率的な改善が可能となります。
また、生産計画の自動化によって生産リードタイムが短縮され、納期が遵守されることで、顧客からの信頼が向上し、新規受注の獲得にもつながります。これは、売上向上という経営に直結する効果をもたらします。
● AIと生産計画のさらなる進化
生産計画の自動化は、AI技術の進化とともにさらに進化していきます。将来的には、AIが需要予測と生産計画を統合し、市場の変化に合わせて生産計画をリアルタイムで自動修正するシステムも登場するでしょう。
AIが過去の生産データや市場動向を分析し、最適な生産量やタイミングを提案することで、過剰生産や欠品をゼロにすることが可能となります。これにより、在庫コストを大幅に削減し、利益率を最大化することが可能となります。
7. まとめ:生産計画の自動化で、未来の生産管理を実現しよう
この記事では、生産スケジューラを活用した生産計画の自動化が、多品種少量生産を行っている製造業の工場にとって、いかに重要な工場効率化の手段であるかを解説しました。
手動での計画作成に伴う属人化、高い業務負担、そして計画精度の低下といった課題は、生産スケジューラを導入することで解決できます。自動化によって、生産管理業務が効率化され、生産性が向上し、コストが削減されます。
この記事で紹介した生産スケジューラの選び方や導入方法を参考に、ぜひ自社に合ったシステムを選定し、生産計画の自動化に取り組んでみてはいかがでしょうか。工場の効率化を実現し、未来に向かって成長していく一歩を踏み出しましょう。
URL:https://www.funaisoken.co.jp/dl-contents/smart-factory_smart-factory_03546_S045?media=smart-factory_S045