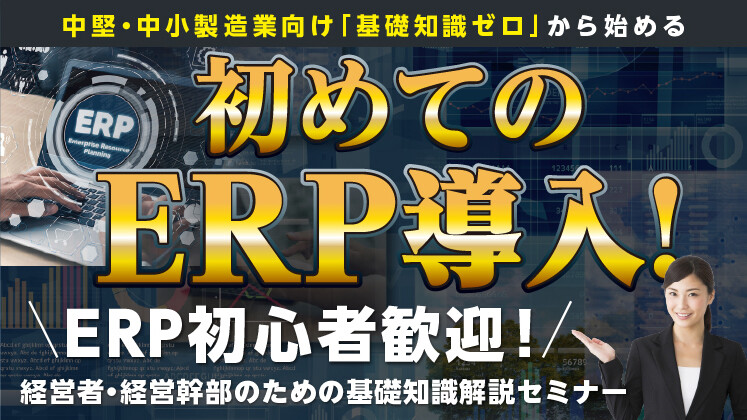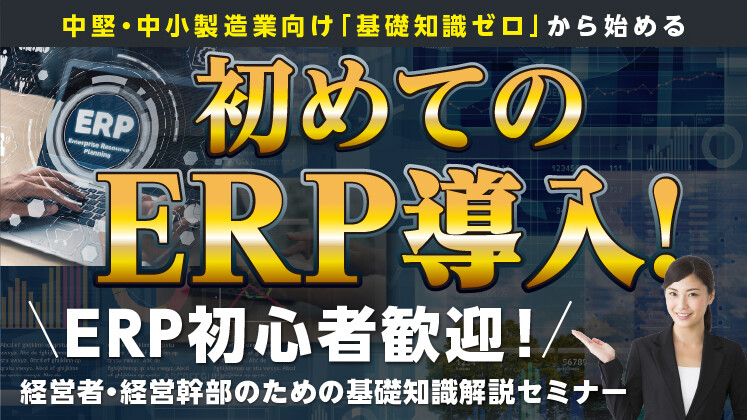なぜ今、「すぐに売上に直結しない話」を真剣に考えるべきか?~製造業の未来を守る生産基盤の話~
2025.11.07
今回のコラムは、多くの経営者が多忙の中で「重要だが緊急ではない」と判断し、後回しにしがちなテーマである「すぐに売上に直結しない業務の仕組み化」について、その本質的な重要性を考えてみたいと思います
1.「売上直結施策」の影で蝕まれる会社の体質
製造業の経営において、優先順位が高いのは「新しい受注の獲得」「不良率の改善」「納期厳守」といった、即座に売上や利益に影響する施策であることは当然です。
しかし、その「緊急の課題」に追われるあまり、「会社の未来の存続」に深く関わる基盤整備が常に後回しになっていませんか?
「ERPをはじめとしたITツールの導入は高コストで、すぐに売上に直結しないシステムの話など、尚更後回しにしてしまう」
この判断が繰り返されることで、貴社の体質は知らず知らずのうちに蝕まれていきます。
■ブラックボックス化:ベテラン社員に依存し、技術やノウハウが「暗黙知」のままになり、人材流出リスクが常に付きまとう。
■非効率の常態化:月末の原価計算や棚卸しに膨大な時間がかかり、それが「当たり前のコスト」として容認されてしまう。
これらは「売上には直結しない」かもしれませんが、「長期的な人件費の無駄」や「生産停止リスク」という形で、会社の利益を静かに削り取っています。
2.後回しにすることで失う「未来の変化への対応力」
システム導入を後回しにすることは、単に「古いやり方を続ける」こと以上のリスクを伴います。それは、「未来の変化に対応する柔軟性」を失うことです。
現在の業務がアナログで、生産計画や原価計算のデータが部署ごとにバラバラなままでは、外部環境の変化に迅速に対応できません。
■新しい技術や工法を取り入れようとしても、アナログな仕組みがボトルネックになり、導入に時間がかかる。
■顧客ニーズの変化に対応した少量多品種生産へ移行しようとしても、生産計画の調整に膨大な手作業が必要になる。
「売上に直結しない話」を後回しにするということは、「将来的に売上を大きく伸ばすチャンス」や「市場の変化に対応して生き残るための体力」を削いでいることに等しいのです。
3.「高コスト」ではなく、「未来の損失」を防ぐ仕組み
ERPが製造業にもたらす価値は、「未来の損失を防ぐための仕組み」です。
■業務の標準化:ベテランのノウハウを「仕組み」として残し、誰でも高い品質で業務を遂行できるようにすることで、従業員の定着率や生産性が向上する。
■情報の一元化:受注から生産、在庫、原価までがリアルタイムで連携し、経営層は「生きている数字」に基づいて、迅速な意思決定ができる。
導入したからと言って翌日から売上が倍になるわけではありませんが、この仕組みこそが、人手不足の時代に社員を守り、非効率なコストを最小限に抑え、持続的に利益を生み出す土台となります。
経営における「ERP」というキーワードや概念を知らない(あるいは、少し見聞きしたことはあるが、何のことかよくわからない)企業様こそ、この「未来への投資」の本質を知る必要があります。
4.基礎知識ゼロから始める、製造業のための仕組みづくり
「会社の業務の全体像が見えない…」「ITツールの導入は高コストだ」と諦めている製造業の経営者様。
下記でご紹介するセミナーは、ERPについては全くの初心者で、基礎知識がゼロの企業様を対象に、「すぐに売上に直結しない話」の裏側にある、長期的な成長と存続の鍵を、専門用語を使わずにわかりやすく解説いたします。
従業員の定着率や生産性を考慮するなら、今後の会社の業務の仕組みをアナログなやり方のままにしておくわけにはいきません。その最初の一歩を、ぜひこの機会に踏み出してください。
【11月オンライン開催】
全国どこからでも参加可能!
大手ではなく、中堅・中小製造業におけるERP導入事例がわかる!
ERPの基礎知識ゼロでもOK!
初めてのERP導入!経営セミナー
~今からでも遅くない!ERPの基礎知識を事例とともに徹底解説!~
【オンライン開催日程】
2025/10/25 (土)10:00~12:00⇒申し込み終了
2025/11/08 (土)10:00~12:00⇒申し込み終了
2025/11/15 (土)10:00~12:00⇒申し込み終了
2025/11/22 (土)10:00~12:00【今年最終開催!】
https://www.funaisoken.co.jp/seminar/133209 いつも当コラムをご愛読いただきありがとうございます。
今回のコラムは、多くの経営者が多忙の中で「重要だが緊急ではない」と判断し、後回しにしがちなテーマである「すぐに売上に直結しない業務の仕組み化」について、その本質的な重要性を考えてみたいと思います
1.「売上直結施策」の影で蝕まれる会社の体質
製造業の経営において、優先順位が高いのは「新しい受注の獲得」「不良率の改善」「納期厳守」といった、即座に売上や利益に影響する施策であることは当然です。
しかし、その「緊急の課題」に追われるあまり、「会社の未来の存続」に深く関わる基盤整備が常に後回しになっていませんか?
「ERPをはじめとしたITツールの導入は高コストで、すぐに売上に直結しないシステムの話など、尚更後回しにしてしまう」
この判断が繰り返されることで、貴社の体質は知らず知らずのうちに蝕まれていきます。
■ブラックボックス化:ベテラン社員に依存し、技術やノウハウが「暗黙知」のままになり、人材流出リスクが常に付きまとう。
■非効率の常態化:月末の原価計算や棚卸しに膨大な時間がかかり、それが「当たり前のコスト」として容認されてしまう。
これらは「売上には直結しない」かもしれませんが、「長期的な人件費の無駄」や「生産停止リスク」という形で、会社の利益を静かに削り取っています。
2.後回しにすることで失う「未来の変化への対応力」
システム導入を後回しにすることは、単に「古いやり方を続ける」こと以上のリスクを伴います。それは、「未来の変化に対応する柔軟性」を失うことです。
現在の業務がアナログで、生産計画や原価計算のデータが部署ごとにバラバラなままでは、外部環境の変化に迅速に対応できません。
■新しい技術や工法を取り入れようとしても、アナログな仕組みがボトルネックになり、導入に時間がかかる。
■顧客ニーズの変化に対応した少量多品種生産へ移行しようとしても、生産計画の調整に膨大な手作業が必要になる。
「売上に直結しない話」を後回しにするということは、「将来的に売上を大きく伸ばすチャンス」や「市場の変化に対応して生き残るための体力」を削いでいることに等しいのです。
3.「高コスト」ではなく、「未来の損失」を防ぐ仕組み
ERPが製造業にもたらす価値は、「未来の損失を防ぐための仕組み」です。
■業務の標準化:ベテランのノウハウを「仕組み」として残し、誰でも高い品質で業務を遂行できるようにすることで、従業員の定着率や生産性が向上する。
■情報の一元化:受注から生産、在庫、原価までがリアルタイムで連携し、経営層は「生きている数字」に基づいて、迅速な意思決定ができる。
導入したからと言って翌日から売上が倍になるわけではありませんが、この仕組みこそが、人手不足の時代に社員を守り、非効率なコストを最小限に抑え、持続的に利益を生み出す土台となります。
経営における「ERP」というキーワードや概念を知らない(あるいは、少し見聞きしたことはあるが、何のことかよくわからない)企業様こそ、この「未来への投資」の本質を知る必要があります。
4.基礎知識ゼロから始める、製造業のための仕組みづくり
「会社の業務の全体像が見えない…」「ITツールの導入は高コストだ」と諦めている製造業の経営者様。
下記でご紹介するセミナーは、ERPについては全くの初心者で、基礎知識がゼロの企業様を対象に、「すぐに売上に直結しない話」の裏側にある、長期的な成長と存続の鍵を、専門用語を使わずにわかりやすく解説いたします。
従業員の定着率や生産性を考慮するなら、今後の会社の業務の仕組みをアナログなやり方のままにしておくわけにはいきません。その最初の一歩を、ぜひこの機会に踏み出してください。
【11月オンライン開催】
全国どこからでも参加可能!
大手ではなく、中堅・中小製造業におけるERP導入事例がわかる!
ERPの基礎知識ゼロでもOK!
初めてのERP導入!経営セミナー
~今からでも遅くない!ERPの基礎知識を事例とともに徹底解説!~
【オンライン開催日程】
2025/10/25 (土)10:00~12:00⇒申し込み終了
2025/11/08 (土)10:00~12:00⇒申し込み終了
2025/11/15 (土)10:00~12:00⇒申し込み終了
2025/11/22 (土)10:00~12:00【今年最終開催!】
https://www.funaisoken.co.jp/seminar/133209