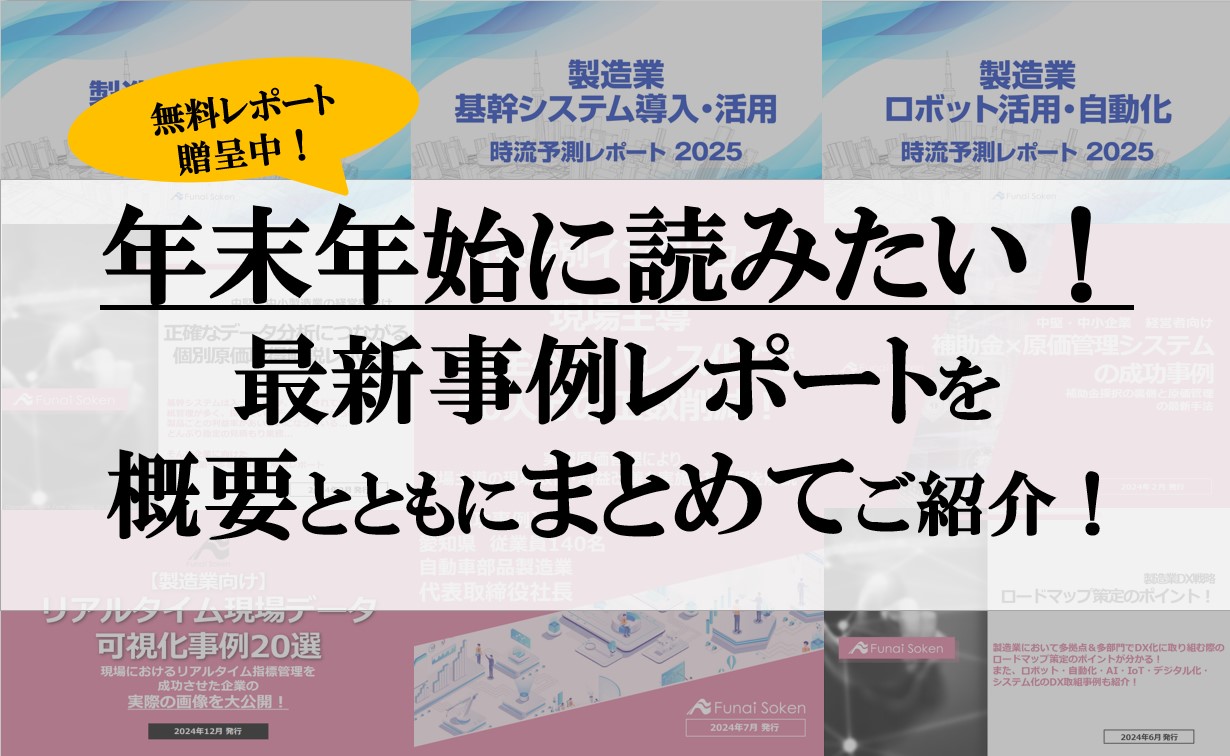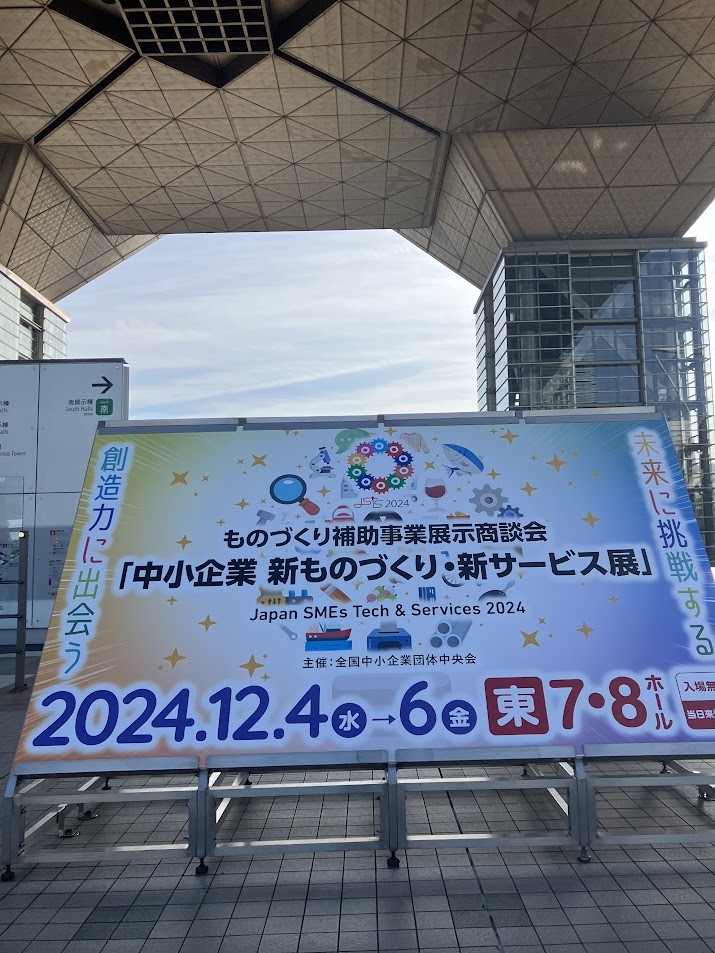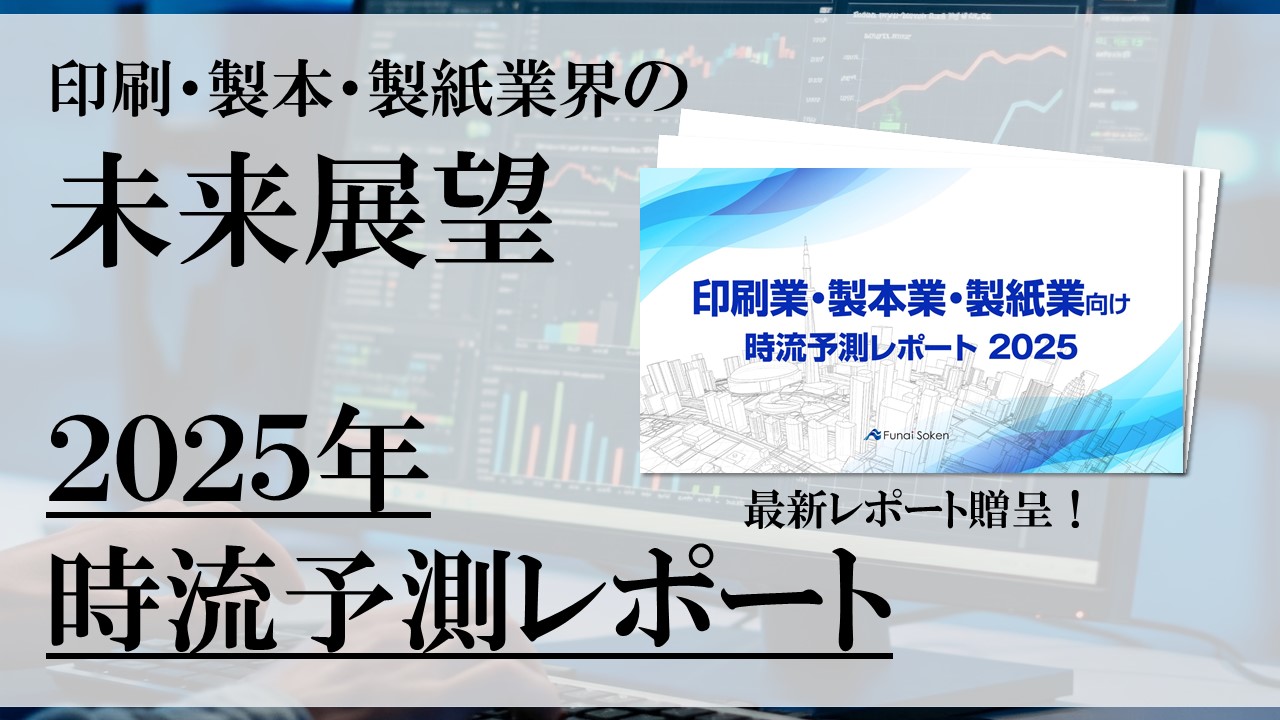金型管理の悩みを解決!改善方法とシステムでできること
2025.01.27
関連記事:工場の自動化 (ファクトリーオートメーション) とは?成功事例5選やメリット、実現の流れを一挙解説!
関連記事:工場自動化が難しいのはなぜ? 4つの課題と解決策を事例付きで解説!
関連記事:AI外観検査とは?従来の画像検査との違い、導入のメリットや注意点とは?
1. 金型管理の重要性
製造業において、金型は製品の品質と生産効率を左右する重要な資産です。しかし、金型は適切に管理されなければ、様々な問題を引き起こし、企業にとって大きなロスとなる可能性があります。
金型管理が適切に行われていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
安全ロス: 金型の保管場所が適切でないと、従業員の安全を脅かす可能性があります。
例えば、金型が落下したり、通路を塞いで避難経路を妨害したりする可能性があります。
時間ロス: 金型が整理されていないと、金型探しに時間がかかります。
これは、生産の遅延や納期の遅れに繋がります。
生産ロス: 金型の保全をおこなわず品質が劣化すると、製品に不良が発生する可能性があります。
これは、材料の無駄、手直し作業、顧客からのクレームなどに繋がります。
これらの問題は、企業の生産性や収益に大きな影響を与える可能性があるため、金型を適切に管理することは非常に重要です。
2. うまくいく金型管理の進め方
金型管理を成功させるためには、以下のステップを踏むことが重要です。
以下のレポート「樹脂成形業向け ”金型管理改善法”レポート」にて内容をまとめていますので、ご興味のある方はダウンロードしていただけますと幸いです。
STEP1:自社にある金型を把握する
まず、自社にどのような金型がどれだけあるのかを把握する必要があります。金型管理台帳を作成し、金型の保管場所、金型の名前、製造品名、製造品目コード、メンテナンス記録などを記載しましょう。最初は手書きやExcelなど、使いやすい形式で記録を始めましょう。
STEP2:金型の棚番を決める
金型の保管場所を決め、それぞれの金型に棚番を割り当てましょう。棚番を決めることで、金型の所在を特定しやすくなり、探す時間を短縮できます。金型の分類方法は、成型する樹脂製品ごと、サイズごと、使用頻度ごとなど、様々な方法があります。自社に合った方法で分類しましょう。
STEP3:金型メンテナンス情報を記録する
金型のメンテナンス情報は、金型の寿命を延ばし、品質を維持するために非常に重要です。メンテナンスを実施した日付、金型名、メンテナンス内容、累計ショット数、金型製造年月日などを記録しましょう。
STEP4:システムを導入する
金型管理システムを導入することで、金型管理を効率化し、正確性を向上させることができます。例えば、ICタグを活用した金型管理システムでは、金型の位置情報やメンテナンス履歴などを一元管理することができます。
金型管理システムには、以下のような機能を持つものがあります。
金型の登録・情報管理
金型の使用実績管理
金型のメンテナンス実績管理
金型の棚卸/在庫/廃棄/移動履歴管理
リアルタイムな金型の状態表示
データ活用機能
また、金型管理システムを導入することで、以下のような効果が期待できます。
作業工数の削減
金型の所在把握の効率化
メンテナンスの効率化
金型の使用状況の把握
金型寿命の延長
データに基づいた管理
また、金型管理を円滑に進めるためには、取引先との連携も重要です。契約時に金型の管理方法について取り決めをし、必要に応じて覚書を交わすことで、後々のトラブルを避けることができます。経済産業省が公開している「型管理の適正化に向けたアクションプラン」も参考に、取引先と適切な管理方法について協議しましょう。
3. まとめ
金型管理は、製造業にとって非常に重要な業務です。適切な金型管理を実施することで、安全性向上、時間ロスの削減、生産性向上、そして最終的には企業の収益向上に繋がるでしょう。上記で紹介したステップを参考に、自社に合った金型管理体制を構築していくことをお勧めします。
金型管理に関するお悩みや課題を解決するために、金型管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか? 多くの会社が金型管理ソリューションを提供しており、無料で資料請求や問い合わせ、相談が可能な場合も多くあります。
金型管理を効率化し、企業の成長に繋げましょう。 関連記事:工場の自動化 (ファクトリーオートメーション) とは?成功事例5選やメリット、実現の流れを一挙解説!
関連記事:工場自動化が難しいのはなぜ? 4つの課題と解決策を事例付きで解説!
関連記事:AI外観検査とは?従来の画像検査との違い、導入のメリットや注意点とは?
1. 金型管理の重要性
製造業において、金型は製品の品質と生産効率を左右する重要な資産です。しかし、金型は適切に管理されなければ、様々な問題を引き起こし、企業にとって大きなロスとなる可能性があります。
金型管理が適切に行われていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
安全ロス: 金型の保管場所が適切でないと、従業員の安全を脅かす可能性があります。
例えば、金型が落下したり、通路を塞いで避難経路を妨害したりする可能性があります。
時間ロス: 金型が整理されていないと、金型探しに時間がかかります。
これは、生産の遅延や納期の遅れに繋がります。
生産ロス: 金型の保全をおこなわず品質が劣化すると、製品に不良が発生する可能性があります。
これは、材料の無駄、手直し作業、顧客からのクレームなどに繋がります。
これらの問題は、企業の生産性や収益に大きな影響を与える可能性があるため、金型を適切に管理することは非常に重要です。
2. うまくいく金型管理の進め方
金型管理を成功させるためには、以下のステップを踏むことが重要です。
以下のレポート「樹脂成形業向け ”金型管理改善法”レポート」にて内容をまとめていますので、ご興味のある方はダウンロードしていただけますと幸いです。
STEP1:自社にある金型を把握する
まず、自社にどのような金型がどれだけあるのかを把握する必要があります。金型管理台帳を作成し、金型の保管場所、金型の名前、製造品名、製造品目コード、メンテナンス記録などを記載しましょう。最初は手書きやExcelなど、使いやすい形式で記録を始めましょう。
STEP2:金型の棚番を決める
金型の保管場所を決め、それぞれの金型に棚番を割り当てましょう。棚番を決めることで、金型の所在を特定しやすくなり、探す時間を短縮できます。金型の分類方法は、成型する樹脂製品ごと、サイズごと、使用頻度ごとなど、様々な方法があります。自社に合った方法で分類しましょう。
STEP3:金型メンテナンス情報を記録する
金型のメンテナンス情報は、金型の寿命を延ばし、品質を維持するために非常に重要です。メンテナンスを実施した日付、金型名、メンテナンス内容、累計ショット数、金型製造年月日などを記録しましょう。
STEP4:システムを導入する
金型管理システムを導入することで、金型管理を効率化し、正確性を向上させることができます。例えば、ICタグを活用した金型管理システムでは、金型の位置情報やメンテナンス履歴などを一元管理することができます。
金型管理システムには、以下のような機能を持つものがあります。
金型の登録・情報管理
金型の使用実績管理
金型のメンテナンス実績管理
金型の棚卸/在庫/廃棄/移動履歴管理
リアルタイムな金型の状態表示
データ活用機能
また、金型管理システムを導入することで、以下のような効果が期待できます。
作業工数の削減
金型の所在把握の効率化
メンテナンスの効率化
金型の使用状況の把握
金型寿命の延長
データに基づいた管理
また、金型管理を円滑に進めるためには、取引先との連携も重要です。契約時に金型の管理方法について取り決めをし、必要に応じて覚書を交わすことで、後々のトラブルを避けることができます。経済産業省が公開している「型管理の適正化に向けたアクションプラン」も参考に、取引先と適切な管理方法について協議しましょう。
3. まとめ
金型管理は、製造業にとって非常に重要な業務です。適切な金型管理を実施することで、安全性向上、時間ロスの削減、生産性向上、そして最終的には企業の収益向上に繋がるでしょう。上記で紹介したステップを参考に、自社に合った金型管理体制を構築していくことをお勧めします。
金型管理に関するお悩みや課題を解決するために、金型管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか? 多くの会社が金型管理ソリューションを提供しており、無料で資料請求や問い合わせ、相談が可能な場合も多くあります。
金型管理を効率化し、企業の成長に繋げましょう。